2023年度 第4回 SDGs「誰ひとり取り残さない」小論文・クリエィティブ コンテスト受賞者発表!
SDGsの原点「誰ひとり取り残さない」をテーマにした小論文・クリエイティブコンテストの結果を発表します。
募集要項はこちら:
https://nogezaka-glocal.com/dh4/
コンテストの特徴:
・SDGsの基本理念「誰ひとり取り残さない」視点での若者(25歳以下)の声
・小学生から高校生、大学生を中心とした実行委員会により運営
・入賞作品のみならず全作品を公開して広く社会に発信する
・LGBTQ+、障害、病気、家族との関係など
と自分がどう向き合うか真剣に考えている作品が多い
・第4回となる今回は絵、イラストなどのクリエィティブ部門も実施
<受賞者・タイトル>
大賞 作品は下部に
大賞 <小論文部門>
・奥田華恵 創価大学 1年 真剣に生きる「怠け者」ー聞いてほしい本当の気持ちー
・岡田彩花 名城大学薬学部6年 また来週。道端の君へ。
・ヤダナ(仮名) ミャンマー 私たちも取り残したくない
大賞 <クリエイティブ部門>
・谷口こころ 熊本県立大学3年 いってきのこらず
特別賞 作品は下部に
奈良東病院特別賞 <小論文部門>
・石垣心優 東北芸術工科大学1年「ひとりじゃない」を伝えるギフトomamori.
エイビス特別賞 <小論文部門>
・清野花香 創価大学3年 自己紹介
KNT特別賞 <小論文部門>
・鈴木亜優美 NTT労働組合 「障害」って、漢字から間違ってるんじゃない?
フランスベッド特別賞 <小論文部門>
・神谷綾音 早稲田大学2年 さりげなく寄り添うことの温かさ
エーザイ特別賞 <小論文部門>
・松山峻大 滋賀医科大学医学部医学科3年 人生の65周年を迎える君へ
パーソネルコンサルタント特別賞 <小論文部門>
・浅沼和 老松中学校 2年 私は妹
共和メディカル特別賞 <クリエイティブ部門>
・西山未華 立命館大学2回生 行こう

入賞 作品は追って公開
入賞 <小論文部門>
・緒方水花里 早稲田大学文化構想学部卒業 食べない奴は生きる価値なし
・上野一志 大阪大学3年/マンチェスター大学 イギリス 日本に心の点字ブロックを
・土岐梨華 石川県立金沢中央高等学校1年 多様性を認め合える社会
・三村咲綾 新潟医療福祉大学1年 誰ひとり取り残されない教育
・川上友聖 立命館大学4年 わかりやすさの暴力性
・竹谷優希 水城高等学校3年 言葉ひとつでひとりの人生が変わる
・鈴木陽菜 金城学院大学2年 あの時の覚悟は今でも忘れない。そしてあなたたちのことも。
・飛山愛梨 福井県立武生高等学校1年 少しづつ、取り残されていく
・久保姫乃 クラーク記念国際高等学校2年 置いてきた忘れ物の私
・髙村幸冠 創価大学1年 やりたいことをやれるって幸せなこと
・右遠太基 慶應義塾大学3年(パリ第一大学) フランス 障がい者だからできたことー地域社会との手の繋ぎ方ー
・宮内正枝 創価高等学校3年 逃げられない子どもたち
・エリ(仮名) 長野県立大学3年 自分と向き合う力
・須郷心桜 名取高等学校 3学年 ほんの少しの”勇気”
・田中愛梨 神戸大学附属中等教育学校3年 ”相談する難しさ〜「取り残された」ような孤独感〜”
・曽我優花 鹿島朝日高等学校2年 包摂的な社会をめざして─ 誰ひとり取り残さないために
・小笠原彩 南山大学3年 重症心身障がい者の視点から考える「誰ひとり取り残されない社会」とは
・西山心雪 四谷インターナショナルスクール2年 自分を愛すること
入賞 <クリエイティブ部門>
・丸尾隆仁 東京理科大学 勝手に特別扱いしないでね

・Min Ye Yint West Yangon Technological University ( ミャンマー) Leave no one behind

・山中友理香 アーウィンパーク小学校(カナダ) Open Options! 選択肢が増えれば、多様性が普通になっていく。

優秀作品賞
<小論文部門>
・森田菜那 立命館大学国際関係学部2年(2023年度末まで休学) 「あなたは今、幸せですか。夢はありますか。」
・二宮百可 愛知学院大学4年 多面体を愛すること
・勝山愛菜 会社員(IT業界) 多様性を問う
・坂元隼斗 早稲田大学3年 みんなと違うという価値
・能登杏奈 聖路加国際大学大学院1年 普通という価値観で取り残したり取り残されたりしていませんか?
・小段杏 創価大学文学部人間学科1年 ひとり親世帯の子どもとして生きてきて、感じること
・天野結菜 刈谷北高校2年 助け合いの花がだんだん大きく広がりますように
・高沢莉菜 宮城県名取高等学校3年 「分からなさ」を超えていくために。
・小川珠穂 公益社団法人MORIUMIUS 性別が嫌い、それでも女として幸せに生きている。
・大磯龍馬 立命館大学文学部3年 「お兄さんありがとう!」交流機会の意味合いは無限大
・佐久間未桜 東洋英和女学院高等部2年 いつも心におすそわけの精神を
・佐々木颯太 宮城県名取高校 3年 いじめの加害者と被害者を取り残さないために。
・武田結香 宮城県名取高等学校3年 あれから止まったままの時間
・田中佑京 追手門学院大学3年(休学中) 普通に囚われた結果、世界から取り残される
・森美唯菜 立命館大学1年 世界インクルーシブ駅伝
・寺田尚布 愛知学院大学文学部日本文化学科2年 みんなちがう、みんなおなじ
・渡邊二葉 神戸市立高取台中学校 学校生活で取り残されやすい私が願うこと
・横山芽 宮城県名取高等学校3年 私だから言えること
・岩間夏美 創価大学2年 教育格差と学歴主義
・磯野青哉 創価高等学校3年 「孤独」から一人でも救うために
・田代英奈 山梨県立大学2年 0地点からの一歩
・保坂優子 創価大学理工学部情報システム工学科1年 無意識のバイアス
・沈鳳璽 東京女子大学2年 暗闇の中に潜んでいる陳腐から
・塩満理恵 お茶の水女子大学4年 一人ひとりがジグソーパズルのピース
・菊池隆聖 早稲田大学社会科学部3年 居心地の良い場とは何か
・小野亜里沙 会社員 言葉の毒を花束に変えるために。
・Caytap Jennee 東濃高等学校3年 ありのままの自分を愛する
・川井和 長崎県立諫早高等学校2年 「当たり前」を超えた先に
・吉田莉恩 人間総合科学大学 1年 すべての声に耳を傾けて
・本馬愛美 富山大学3年 『日本人』クリスチャンとして生きる
・宮澤正虎 成城学園高等学校1年 性別に囚われず自分らしく生きるために
・髙野春奈 宮城県名取高等学校 3年 ありのままで
・大西花音 神戸松蔭女子学院大学4年 性別を悪にしてはいないだろうか
・山中このみ 静岡県立藤枝東高等学校 2年 あなたは他人より劣っている点はありますか?
・阿部真彩 日本大学芸術学部 優しさの責任
・跡部奏真 秋田大学2年 内面に耳をすまして
・山田優杏 成立学園高等学校 取り残されることを恐れない自分になるために
・北川桜子 東北大学3年 「孤独で寂しい」SNSでは解決できない問題にどう挑むか。
・阿部羅好恵 創価高等学校3年 知ることで変わる世界
・宮﨑一輝 和歌山大学2年 体格による取り残しが本当に“しょうがない”のか
・西村公希 山口県立大津緑洋高等学校普通科2年 本当の「多様性」
・伊藤陽香 関西外国語大学 2年 Leave No One Behind
・山崎隆斗 長崎県立鶴南特別支援学校五島分校小中学部 中学2年 僕の夢が見つかった
・髙橋幸太朗 関西学院大学3年 誰一人取り残さない住宅政策
・村上凜音 北海道苫小牧市立緑陵中学校 社会の連鎖
・鈴木日彩 群馬県立中央中等教育学校 5(高校1)年 僕を『覚え』『感謝』する。あなたを『覚え』『感謝』する。
・河角公太 東海大学国際文化学部 2年 視覚障害者とのスポーツ観戦から得られた「誰1人取り残さない」を実現する「気づき」
・春日絆那 養老町立高田中学校1年 認め合い 助け合い 自由を目指して
・中本雛詩 創価高等学校3年 Kaiaが気づかせてくれたこと
・高野美侑 宮城県名取高等学校3年 外国人だからという理由で
・野田怜弥 横浜市立大学4年 友達のともだちは友達
・市川野乃夏 宮城県名取高等学校 3年 夢に向かって進むために
・長船未玲亜 関西創価高等学校 高校三年生 多様性の本当の意味
・牧野寛太 創価大学3年 多様性を認めること
・市野澤玲衣 湘南医療大学 公衆衛生看護学専攻 保護者の孤立にどう立ち向かうか
・桐生莉緒 早稲田大学4年 取り残されないようにし合う
・音田将吾 フリーター 働きかけ
・佐藤知咲 名取高等学校3年 在留外国人を取り残さないために
・山口颯太 一橋大学 みんなが取り残された世界
・三嶋千尋 宮城県名取高校 3年 高齢者とICT
<クリエイティブ部門>
・津田愛里 大阪デザイナー専門学校 ひとりは、苦しいよ。

・相羽芽衣 中部学院大学2年 私には夢があった

・八島幸穂 静岡県立富士高等学校2年 美しい星を目指した

・原田唯花 山形県立ゆきわり養護学校5学年 わたしは、わたし
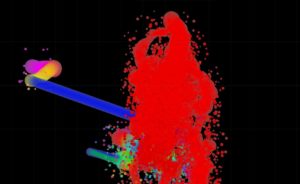
・岡村飛馬 シャモニ・サントル小学校5年生 スキーが好き

奨励作品
<今後発表>
実施の背景:
「誰ひとり取り残さない」はSDGsの基本理念であり、誰かを犠牲にしたり、取り残したうえでのSDGs達成はありえません。SDGsの宣言文でも「最も貧しく最も脆弱な人々の必要に特別の焦点をあて」「最も遅れているところに第一に」「最も貧しく最も脆弱なところから」などと繰り返し強調されています。
しかし、言葉として、あるいは総論としては理解していても、「誰ひとり取り残さない」を実際に意識して、SDGs活動を行っている人は案外多くはないかもしれません。
今目の前のできることから行うべきであり、「誰ひとり取り残さない」をあまり意識することは「非現実的」という声を聞くこともあります。
本コンテストは、今一度基本に立ち返り、SDGsの基本理念「誰ひとり取り残さない」視点をすべてのSDGs活動や社会活動に反映すべきとの観点から、若者の自由な発想や提案、計画についての小論文や作文を求め、またその声を広く社会に発信することを目的として実施するものです。
コロナ禍の2020年に第一回が開催され今回は第4回になります。
若者中心の実行委員会により運営されています。
コンテスト概要
募集内容:
【作文・小論文部門】
SDGsの基本理念、「誰ひとり取り残さない」の視点で、考えること、自分が行いたいこと、社会への提言など自由な発想で、小論文・作文を作成のうえご提出ください。文字数は問いませんが上限は2000文字とします。
【クリエイティブ部門】
SDGsの基本理念、「誰ひとり取り残さない」について、自由な発想で、A4サイズ1枚に写真、イラスト、絵、グラフィクなど自由な表現で提出ください。(提出はJPEG形式)
文字が含まれる場合は日本語40文字以内とします。
応募資格:2022年4月1日時点で25歳以下の人
【両部門共通】
大賞(3万円) 4 作品
特別賞(2万円) 6 作品
入賞(1万円) 15作品
優秀作品賞
主催:野毛坂グローカル
運営:
SDGs「誰ひとり取り残さない」エッセイ/クリエイティブ コンテスト2023実行委員会
後援:
国際協力機構(JICA)
朝日新聞社
SDGsジャパン
参考:
第一回結果:
https://nogezaka-glocal.com/sr/
第二回結果:
https://nogezaka-glocal.com/dh/
第三回結果:
https://nogezaka-glocal.com/dh/
【共同実行委員長】
金澤伶 東京大学3年生/ユースなんみんプラットフォーム前代表
鈴木知世 国際教養大学4年
呉恩愛 東京女子大学 2年
【実行委員】
有馬羽純 前原西中学校3年生
入口侑可 国際基督教大学教養学部3年
上野裕太 NTTアノートエナジー株式会社
唄野陽芽 立命館大学3年生
惠木莉菜 聖心女子学院高等科2年生
遠藤優介 奈良先端大学院大学1年
大西彩樺 University of Qeensland 1年
奥井利幸 野毛坂グローカル
小野日向汰 岡山県立倉敷青陵高等学校 三年生
形山実結 専修大学松戸高校3年
川北輝 北陸先端科学技術大学院大学2年
川田千楓 横浜隼人高校2年
工藤秋依 慶應義塾大学総合政策学部3年
河野啓子 野毛坂グローカル
小松真子 立命館大学経済学部2年
櫻井美咲 神戸市外国語大学国際関係学科1年
佐藤秋夢 法政大学1年
座間耀永 青山学院高等部2年
下平心那 横浜国際高等学校3年
柴山心花 鹿島朝日高校2年
仙田紗都 成城大学2年生
田中サラ 横浜高等学校3年
田村大樹 JR東海勤務
西岡聖奈 滋賀県立大学1年
西岡主税 済美平成中等教育学校
西川那緒 佐世保北高校2年
仁禮和希 水城高校2年
服部翠 広島叡智学園中学校1年
福田優羽 広尾学園高等学校 高校2年生
藤田咲桜里 私立鹿島朝日高等学校 2年
船津妃澄 長崎県立佐世保北高校2年
古川志帆 神奈川大学2年
本行紅美子 Japan youth Platform for Sustainability(JYPS) 共同事務局長
村田丈治 海星高校3年
山崎心優 東洋大学1年
山崎祐佳 四国学院大学社会福祉学部精神保健と福祉メジャー3年
吉田望花 DSC International School, Grade9 (高校1年生)
オフィシャルサポーター:
株式会社エイビス
エーザイ株式会社
共和メディカル株式会社
奈良東病院グループ
パーソネルコンサルタントマンパワータイランド株式会社
フランスベッド株式会社
アドバイザー:
野津隆志 兵庫県立大学名誉教授 / 野毛坂グローカル監事
秋山愛子 国連・アジア太平洋経済社会委員会 社会課題担当官
荒木田百合 横浜市社会福祉協議会会長
杉浦裕樹 横浜コミュニティデザイン・ラボ代表理事
高比良美穂 社会応援ネットワーク 代表理事
長島美紀 SDGs市民社会ネットワーク理事/ながしま笑会代表
中西由起子 アジア ディスアビリティ インスティチュート(ADI)代表
/ SDGs市民社会ネットワーク理事
藤谷健 朝日新聞東京本社デジタル機動報道部長
兼 ジャーナリスト学校デジタル推進担当部長
和田恵 SDGs-SWY共同代表
支援者(敬称略):
小笹晃子、青木憲代、石原伸一、岩佐幹生、鍵野 絢子、山崎真帆、メラ圭子、小西 伸幸
大賞・特別賞・入賞作品
大賞 <小論文部門>
・奥田華恵 創価大学 1年 真剣に生きる「怠け者」ー聞いてほしい本当の気持ちー
「今日もまた、できないことが増えていく。今日もまた、どんどん一人になっていく。」―毎日、こんな思いが私の心を締め付けた。やりたいことであふれていた青春時代。私は、鉄欠乏性貧血と起立性調節障害とともに生きた。
中学の時、鉄欠乏性貧血と診断された。体中に酸素を運ぶ役割の鉄分が不足し、体中にうまく酸素がいかず、貧血を起こしやすくなる。激しい運動が苦手で体育の時間も部活動でも他の人が涼しい顔をしている中、ひどい息切れを起こす。息切れならいいものの、過呼吸になって貧血を起こし倒れてしまうこともしばしばであった。もちろん、貧血の症状も苦しかったが、無理解から生じる周りからの冷たい言動に一番傷ついた。体力がないと勘違いされてしまうのである。部活動の剣道の練習中、息が切れて動けなくなっていたら「我慢しろ!他の人も同じようにしんどいんだぞ!」とどなられた。追い込むようなハードな練習には参加しないようにと医師から言われているため、その練習を見学すると「休めていいよね。楽でうらやましい。」と、心ないことを言われた。それでも「負けたくない」という思いで毎日剣道場へ。でも、頑張りたいのに身体が動かない。目に映る景色は練習に打ち込み頑張っているみんなと何もできず息苦しく動けなくなっている自分。「怠け者」だと思われ、みんなが離れていった。一人ぼっちになった。消えてしまいたいという思いが募った。
それから、地元を離れて都市の私立高校に入学した。貧血のような症状にまた悩まされていたところ、起立性調節障害との診断。症状は似ているが、朝起きられなくなったり、運動というきっかけがなくても急に貧血を起こしたりといった症状が加わる。症状は日を増すごとにひどくなり、朝起きて学校に行き、友達と他愛もない話で盛り上がったり、授業をみんなと受けて勉強に打ち込んだりという「当たり前」が失われた。できないことが増えていく現状に怖くなった。しかし、中学時代とは異なり、高校で出会った人たちは私を決して一人にせず、いつもそばにいてくれた。朝、体調が悪くなるという症状を知った友達は午前中の授業内容を丁寧に記録し、お昼休みや放課後に教えてくれた。過呼吸の症状が出たときには「大丈夫。ゆっくりでいいよ。」と背中をさすって落ち着くまでそばにいてくれた。そんなあたたかさにどれほど救われたことか。「生きていたい」と思えた。
鉄欠乏性貧血と起立性調節障害は特に思春期に多い。鉄欠乏性貧血は500万人、起立性調節障害は思春期の子どもの1割、100万人程度いるといわれている。珍しい病気ではないが認知度は高くない。入院の必要はなく、薬を飲んでいれば生活を送れるため、病気であることに気づかれにくかったり、患者自身は周りと自分を比べてしまい、落ち込むこともある。「入院するまででもないんだからこのくらい我慢しなくては」と自分を追い込んで、さらに症状を悪化させてしまうということもある。このように、身体的負担だけでなく、精神的負担もかなり大きいのだ。日常の中に埋もれ、知らない間に取り残されてしまう深刻な問題であると受け止めている。
だからこそ、鉄欠乏性貧血と起立性調節障害を経験した私が伝えたいのは、第一に、病気に大小はないこと。第二に、「できない」ことより「できた」ことに目を向けること。第三に、「当たり前」や「普通」なんてないと気づくことである。病気の大小や有無に関わらず、辛いときに辛いと素直に言える。「当たり前」や「普通」と言われていることができなくても嘆く必要はなく、自分基準で、自分が生きやすいように生きればいい。そう思えることが精神的負担を減らすために大切であり、社会のサポートが不可欠である。今もきっと誰かが薬を飲みながら「普通」を装って、日常を必死に生きている。誰にもいえない痛みを抱えて涙を流している。私はそういう人たちを絶対に見過ごしたくない。社会の無理解や苦しみを我慢せざるを得ない状況を社会が生み出しているのなら、私は社会に声を上げていきたい。鉄欠乏性貧血や起立性調節障害など薬で治療する病気の存在を知り、それらを軽視する風潮がなくなることを願う。
苦しい時「大丈夫だよ。」と寄り添ってくれる人がいること。苦しみを理解してくれる人がいること。それによって苦しさがあっても「生きていたい」って思えることがどれほど嬉しいことか―私は身をもって感じたからこそ、皆の「生きていきたい」を守っていきたい。それが誰ひとり取り残さない社会を築くことにつながると確信して。
・岡田彩花 名城大学薬学部6年 また来週。道端の君へ。
木曜日の夜20時.
道端では数人の男性が集まって談笑していた.
週に一度やってくる友人を待つために.
気が付かずに通り過ぎる人もいれば見て見ぬふりをするもいる.
気がついても関わろうとしないのが大半だし,何かしたいけど勇気がでないとか方法が分からないって理由で何もしなかったりする.
私もそういう大勢の中にいたし,でもそんな自分や社会に違和感を感じていた.
厚生労働省の調査によると2023年度の路上生活者は全国に3,065人。
統計的な数字としては年々減少しているが,ネットカフェやホテルを転々とする“隠された”ホームレス,怪我や病気が原因で生活ができなくなった“取り残された”ホームレスの存在は日本社会に大きな課題を問いかけている.
私はこの夏,ホームレスを支援するNPO団体の活動に同行させてもらった.
配布する食料をリアカーに積み込み,公園や高架下を巡りながらおにぎりやおかずを配布していく.
団体を立上げたHくんは私と同じ大学生.
勉強が忙しい中でも毎週欠かさずホームレスの方々に会いに行き,アルバイトで稼いだお金も使いながらでも活動を続けているという.
正直,初めはリアカーを引いて街を歩き回ることやホームレスの方々に声をかける時には周りの目が気になってしまった.
そんな様子が分かったのか「俺たちだって人間だもん.普通に話しかけてくれたらいんだよ.」と声をかけられた.
私は悲しい気持ち半分,嬉しい気持ち半分になった.
ホームレスを下に見る気持ちは全くなくて,でも何となく自分とは境界を引いていたことは認めざるを得なかった.
そして“ホームレス”という存在から距離をおいてきたのは私たちであって,向こうはいつでも相談相手や助けを求めているのだと分かった.
また,別のお兄さんは食事を受け取った際に言った.
「俺だって好きでこんな生活してるわけじゃない.
去年の夏、仕事も家もお金も無くなって…それからホームレス.
人間,誰だってこんなふうになるかもしれないんですよ?
生活保護とか受けれるのかもしれないけど,どうしても恥ずかしいって思いが頭にある.
「できることは自分でやりたい.こんな生活から抜け出したいです.」
彼の言う通り誰もが初めから望んで過酷な路上生活に至った訳がない.
一方で,彼らから抱えている事情や背景を打ち明けてもらい支援を受け入れてもらうことも簡単ではない.
自分の未来への希望や社会や他人への信頼を取り戻してもらえるよう,目線を合わせた地道な声掛けや小規模の活動こそ大切だと感じた.
その日は活動を終えて家に帰ったのは日付けが変わる頃だったが,不思議とお腹は減らなかった.
こんなにも助けや繋がりを求めて待っていてくれる人がいるんだってことに改めて気が付かされ,渡したご飯を美味しそうに食べてくれるのを見るの本当に幸せだった.
待っててくれる人がいる.またねって言える人がいるという関係性っていいなと思った.
誰かの安心を支えること,誰かの笑顔を創れることって幸せな気持ちになれるんだなと感じた経験になった.
薬学部の学生である私は,医療保険や社会保障制度に取り残された人々と出会い,これまで自分が見てきた“医療”の枠の狭さに気が付かされた.
「生きる」ってなんだろう,と思った.
ただ生命として存在していることやただ時間を過ごしているだけでは,人間としての生を満喫することは出来ない.
命の先にある生きること,つまり人間として尊厳と誇りを持って暮らすことを支えるためには,医療だけでは不十分だ.
今の日本はとても発展していて生活水準も底上げされてはいるが,まだそれぞれの事情で健康の課題を抱えていても医療にアクセスできない人達は沢山取り残されている.
本当に必要なところに,本当に必要としている人に,医療と健康を届けたい.
そして保険医療や薬を介さない面からも介入して人生を支えることができるようになりたい.
大勢の拍手より1人1人との握手を大切にできる人でいられたらと思った.
1週間に一度の食事の提供では,ホームレスの方々を完全に満たすことも生活を変えることもできない.
でも支援を通して人と繋がることで少しずつ前に進めるだろうし,支援をされる側も“自分たちは忘れられている訳じゃない,また頑張ってみようかな”という気持ちになれるはずだ.
過去も今も受け入れてこれからの未来を創ろうって思えるようになってもらいたいし,話を聞いて共に笑い共に泣くだけでも良いと思う.
何かを始めるって簡単なことじゃないし続けることはもっと大変だ.
まだ行動する勇気が無い自分と何かしなくちゃって思う自分がいて,一人じゃできないことでも仲間がいればできることがあると実感できた.
小さな一歩も歩き続ければきっと大きな力になる.
誰も取り残されない社会のために,出会った仲間とともに私にできることに取り組んでいきたい.
・ヤダナ(仮名) ミャンマー 私たちも取り残したくない
初めまして。私はミャンマー出身です。ミャンマーといえば黄金の国として知られていますが、残念ながら、現在は内戦が起こって、国民の悩みと困難に満ちた国になっています。様々な困難に遭遇し、安全とは何かと疑問になるほど毎日は不安でいっぱいです。国の人材である若者たちは国内での教育を停止し、留学できる人は留学し、家族を養うためお金を稼ぎに行く人もいます。それが原因で、パスポートオフィスの前には毎日人がいっぱいで長い列になっています。我が国は貧困、健康、経済、教育、電力など様々な問題に直面している中、私は教育に関する部分について少しお話ししたいと思います。実は、ミャンマーでは政治情勢の影響で学校に通えなくなった若者がたくさんいます。若者全員は現政府を支持していないので学校にも行かず、反対しているのです。その活動をCDM(Civil Disobedience Movement)と呼ばれています。しかし、政情が2年以上も続き、若者たちの年齢と教育の差が大きくなってしまいました。高校を卒業しても大学に進学できない人たち、他も小学校や中学校を停止した子供たち、または大学最終学年で停止した人たちなどたくさんいます。その中で、高等教育に合格した人は自分の興味のある道を見つけ、経済的に余裕のある人は海外留学し、経済的余裕のない人はここに残って働いています。他に勉強もしたいですが、仕事もしなければならないため、勉強と仕事を同時にしている若者もたくさんいます。初等中等教育を停止した子どもたちは、経済的余裕があれば、私立学校に通って、経済的余裕のない子供たちなら、親が教えることができれば勉強できますが、教えることができない親なら、その子供にとって勉強するのが難しいです。より大変になってるのは戦場のような地域だと、勉強どころか生きること、食べることさえ困難です。全国から見ると、全ての若者たちのほとんどが公平な教育を受けられていません。それはかなり大きな問題だと思います。でも、共通しているのは一つあります。皆が立ち止まらず、できる限りの方法で学ぶのを継続していることです。私もその中の一人で2020年に高校を卒業した後、大学には進学できず、興味のある日本語を勉強し始め、今は日本の大学に入学する道を歩いて続けています。皆がそれぞれの道を続けているのはうれしいことですが、その反面、国として取り残されたのも事実です。それをある日、日本のニュースで、小学生たちが夏休みの間にSDGsの学習や活動の準備に熱心に取り組んでいるのを見て強く感じました。我が国の子供たちにもそんな機会があれば、いいのにと熱く思い、ミャンマーの教育ははるかに遅れていたのかなあ…という悲しみも同時に感じました。私が気づいた限りでは、日本のニュースには、いつも SDGs に関してどのように取り組んでいるのかという記事が必ず出ています。子供たちから始まって、様々な分野でのSDGsの取り組みを見るだけで、日本はSDGsに関してどんなに熱心あるのかをよく感じられます。そんなに日本が力を入れて取り組んでいるプロジェクトですが、我が国ではまだ聞きなれない言葉であり、2030年までの17のゴールなんかはまだ遠いです。それは事実であり、私たちを取り残している原因かもしれません。心を痛めることは、一人ではなく国全体が取り残されている状態です。すべて取り残されたこの国を今後は取り残されない国、つまり誰一人取り残さない国として私たち世代の力で立て直しなければならないと思っています。
奈良東病院特別賞 <小論文部門>
・石垣心優 東北芸術工科大学1年「ひとりじゃない」を伝えるギフトomamori.
私は現在、双極性障害と解離性障害の2つの精神疾患とともに日々を歩む生活を過ごしています。高校生の時、医師から診断名と共に告げられたのは、精神疾患を患うきっかけとなった原因は、幼少期の劣悪な家庭環境によるものだったということでした。告げられた瞬間「私は普通じゃない。周りから取り残されているんだ。」と感じ、胸をぎゅっと締め付けられるような孤独感でいっぱいになりました。
そんな当時の私は、クラスにも馴染めず、高校生活を不登校の状態で過ごしました。「人生どうにでもなれ」と自暴自棄になり、生きづらい思いからオーバードーズやリストカットなどの自傷行為を繰り返す生活を送っていました。沢山薬を飲んでも、床に血が滲むくらい腕を切っても、心の傷は癒えずに残っていくだけでした。そんなある日、私にとって衝撃的な出来事が起こりました。それは、ずっと仲良くしていた友人が自殺したことでした。深々と雪が降る寒空の中、彼女が棺の中で安らかに眠っていたのを目にして、ぼろぼろと涙が止まりませんでした。そして、自分が彼女の悩みに気づき、声を掛けてあげるなどの支える存在、”ゲートキーパー”になれなかった後悔が募りました。
あの日を境に、私は「生きづらさ」について考え、調べるようになりました。そこで目にしたのは、衝撃的なデータでした。日本の子どもの死因の第1位は自殺だということ、そして自殺者は年々増え続けているということ。これをきっかけに私は「生きづらさと闘っている私だからこそ、何かできることはないのか」という想いが芽生え始めました。どうしたら生きづらさを抱える人に寄り添うことができるのか、沢山悩み考えました。
そこで私は中学生の時に貰った大切なものを思い出しました。それは、学校の先生から貰ったラベンダーの香りがするポプリでした。当時私が生きづらさを抱えていた時に、このポプリを見て、自殺を思いとどまることが何度もありました。毎日制服のポケットに入れて、ずっと大切に持ち歩いていました。今でも、私にとって大切なお守りです。そんな大切なものを思い出した時、ポプリをもらったあの日から私はひとりじゃなかったんだと、気づくことができました。私もこのお守りのように「誰かの心の灯火になるような、生きづらさを抱えている人達に寄り添うことができるもの」を作りたいと、そう考えました。
こうした経験から、私は高校2年生の時に「omamori.PROJECT」を立ち上げました。
「癒しのギフトを通して、当事者の心と当事者の身の回りにいる人の心をつなぐ」 。
これをテーマに私の想いを込めて、いい香りがするお守り「omamori.香り袋」をハンドメイドで製作し、オンラインサイトで販売を行うことになりました。何週間も夜通しかけてひとつひとつ丁寧につくった香り袋には自然と愛情が湧いてきました。実際に販売するとなると「私の想いをちゃんと届けることができるのか」という不安と緊張が募りました。
しかし、いざomamori.香り袋を販売してみると、なんとたったの2時間で完売することができ、100人以上の方に私の想いを届けることができました。届けた人の中には「自分も精神疾患の当事者で、とても元気をもらえた」と打ち明けてくださる方がいました。「友達が落ち込んでいたので購入をしてみたが、とても喜んでくれた」、「想いを届けてくれてありがとう」など、沢山の方の暖かな声を聞くことができました。omamori.香り袋を購入してくださった方一人一人がそれぞれの形で「ひとりじゃない」と感じることができる瞬間を届けられた、そう思いました。
これまでの活動を通して、今の私が描くマイビジョンは「社会にゲートキーパーの存在が増え、 10代20代の若者が「ひとりじゃない」と思うことができる社会の実現」です。このビジョンにはこれまでの私の実体験に基づいた想いが沢山詰まっています。
プロジェクトを通して、まだまだ生きづらさを抱え、闘病生活を余儀なくされている人達、昔の私のように「取り残されている」と感じている人達が沢山いることを知り、若者の自殺問題により向き合いたいと感じました。初めは1人で活動をスタートしたプロジェクトも、今では数人のメンバーに支えられて今日まで続けることができました。
私は現在も、精神科への入退院を繰り返しながらこの活動を広げています。時々、心が折れそうな瞬間はあるけれど、私はもうひとりじゃありません。沢山の人たちに支えられています。だから今度は私が、1人でも多くの生きづらさを抱えている人たちに、想いを届けていきたいと考えています。これからも「ひとりじゃない」と思える社会の実現と、誰ひとり取り残さない社会の実現に向けて、沢山の感謝と共に歩んでいきたいと考えています。
エイビス特別賞 <小論文部門>
・清野花香 創価大学3年 自己紹介
私は。そう、私は泣き虫です。
石でこけて泣きました。
飼っていた金魚が死んで泣きました。
忘れ物をして怒られて泣きました。
絵本で子どもが魔物に食べられたから泣きました。
犬に追いかけられて泣きました。
おばあちゃんが亡くなったから泣きました。
耳の治療が痛くて泣きました。
窓ガラスを割って泣きました。
オバケが怖くて泣きました。
友達を傷つけてしまって泣きました。
家族が弟を優先するので泣きました。
褒められなくて泣きました。
人と比較されて泣きました。
靴が隠されて泣きました。
無視されて泣きました。
友達に死ねよって言われて泣きました。
先生に日本語理解できないんだねと言われて泣きました。
空気を読めと言われて泣きました。
悲劇のヒロインぶるなと言われて泣きました。
鉛筆が持てなくて泣きました。
宿題がゴミ箱に捨てられて泣きました。
椅子がなくて泣きました。
何でこんなこともできないの?と言われて泣きました。
泣くなと言われて泣きました。
大好きな親友がなくなって泣きました。
毎日気楽そうでいいねと言われて泣きました。
自分だけ嘘の日程を教えられて泣きました。
もっと頑張れよと言われて泣きました。
女子って男子よりも劣ってるねと言われて泣きました。
同性愛者はきもいといわれて泣きました。
人とコミュニケーションができなくて泣きました。
朝は起きれなくて泣きました。
夜は眠れなくて泣きました。
みんな楽しそうに笑っていて泣きました。
双極性障害って免罪符になるからいいよねと言われて泣きました。
障害は隠したほうがいいよといわれて泣きました。
文章が書けなくて泣きました。
言葉が話せなくて泣きました。
絵本の文字も読めなくなって泣きました。
君の存在価値は何? と言われて泣きました。
生きる意味が分からなくて泣きました。
死ぬ勇気もなくて泣きました。
泣いて、泣いて、泣いて。
私は。そう、私は泣き虫なんです。
私の。私の存在価値は。
見つけます。自分で。今、みんなと生きていたいから。
KNT特別賞 <小論文部門>
・鈴木亜優美 NTT労働組合 「障害」って、漢字から間違ってるんじゃない?
「障がい者」と聞いて、どう思うか。人の支援が必要、かわいそうなどさまざまなイメージがあるだろう。その原因に、一般的に「障害」と書くことや、障がい者と関わる機会が少ないことが挙げられるのではないか。「害」には、損なうや傷付けるなど、マイナスなイメージがある。また、障がい者は特別支援学校などで教育を受け、障がい者のコミュニティのみで生きている。これは、障がい者が「隔離」されて、私たちと関わる機会を削られているとも言うことができる。そこで、私たちは障がい者と積極的に関わり、そのイメージを払拭していかなければならない。
私は、障がい者である。生まれつき、左目と右目の視力が異なり、立体的に物が見ることができない。そのことに気づいたのは、大学生の時。頭が時々痛くなることがあり、片頭痛だと思っていたが、ひどい痛みで病院に行った。その時に、医者から「片頭痛ではなく、目が焦点を合わせようと、力を使いすぎて頭が痛くなっていた」と言われた。これまで、腕や足をぶつけて「おっちょこちょいだね。よく周りを見て歩いてね」と両親や、友達に言われることが多かった。しかし、それは自分の「性格」ではなく、「障がい」であったと気づいた。
その瞬間に、すべてが繋がって心が軽くなった。小学生の頃、体育でとび箱をする時にとび箱までの距離が分からず、転んでもいい覚悟で跳んでいたこと。高校生の頃、車との距離が分からず、横から来る車が見えていても、まだ近くないと止まらなかったこと。すべて、自分の性格ではなく、障がいであった。一時期、なぜ自分はこんなに気を付けられないのだろうと、自分を責めていた時期があった。それは、「自分のせいではなかった」と気づけただけで、こんなに心が楽になるとはと驚いた。
それから、片目だけコンタクトを付けることになった。初めてコンタクトをすると、目の前の景色が変わった。「普通」に見えている人は、こんな世界を見ているのだと驚いた。ただ、大通りを歩いても人が「立体的」に歩いてくることに衝撃を受けた。これまで、私の世界は、平面だったからである。それが、当たり前だと思って疑いもしなかった。しかし、「当たり前」が当たり前でなく、一種の障がいと言われたものだった。実際に、自身に「障がい」があると言われて、その時まで「障がい」に支援を必要とする人というような、ざっくりとしたイメージしか持っていなかったが、軽度・重度はあるものの、誰しもが「障がい」があるのではないかと思い始めた。
その後、大学で教職課程を専攻し、「障がい」のある子供の置かれる現状を学び、交流もした。実際、その子供たちと接してみると、私たちと何も変わらない明るい子供たちで、とても元気だった。私は、聴覚に障がいのある子供と交流したが、遠足やお菓子の時間を楽しみにする、私の子供時代を思い出す子供たちだった。この経験からも、そのような子供たちを、特別支援学校に入れることや、仕事場において区別することは、やはり違うのではないかと思う。SDGsの「誰一人取り残さない」という観点からも、障がいのある人に配慮しつつ、全員が同じ場所で学んだり、仕事場で仕事ができるようにしなければいけないと考える。
そこで、私は「障がい」がある人に対して、支援だけでは十分でないことを伝えたい。SDGsの目標として掲げられている通り、誰一人取り残さないためには、誰もが輝ける場を作り、社会に居場所を作らなければならない。それは、政府や自治体の責任のみではなく、私たちも取り組んでいかなければならない課題である。私たちが、取り残されている人に気づき、積極的に関わることで、その人に居場所ができる。そこで、障がいがある人も輝く場を作り、周知・発信していく責任が、私たち一人ひとりにあり、認識しなければならないと考えている。
フランスベッド特別賞 <小論文部門>
・神谷綾音 早稲田大学2年 さりげなく寄り添うことの温かさ
一生懸命みんなの口を読む。うーん、ダメだ。やっぱり分からない。諦めて適当にみんなに合わせて笑ったり相槌を打ったりする。でも段々ずれていくのが分かる。みんな楽しそう。みんな何を話しているのだろうか。急に心臓の辺りがギュッと苦しくなる。私はどうしてここにいるんだろう。どうせみんな耳の聞こえない私のことなんか見てもないのに。私は会話の輪の中にはいるけど、やっぱり透明人間みたいだ。みんなが私だけを置いて遠くに行ってしまうような気がして、段々視界がぼやけてくる。
そのとき、何かが私の肩に優しく触れた。ふっと横を見るとAが真っすぐ前を向いたまま私の肩に手を置いていた。手が置かれた部分からジワーッと温かい何かが私の体全体に広がるのが分かった。その時、私はとてもホッとしたのをとてもよく覚えている。私は透明人間なんかじゃない、一人なんかじゃないと思えた。その時、私はみんなが話している内容を教えてくれなくても良かった。ただ、私一人だけが会話から「取り残されている」、このことに気付いてくれる人がいる、それだけで良かった。
私は生まれつき重度感音性難聴という障がいを抱えており、人工内耳と補聴器を両耳に着用している。聴覚障がいがある人の中にはろう学校に通学している人もいるが、私は小学生の時から健聴の学校に通っている。やはり健聴の学校では、私のように聴覚障がいのある人はマイノリティの立場にある。私は小学生の1年生の時から、周りの人に自分の障がいのことを積極的に伝えるようにしていた。聴覚障がいとはどんな障がいなのか、どんなことに困っていてどんな助けを求めているのか、自分から伝えないと実際に経験をしたことがない人は、理解することができず、結局自分が困るだけだからだ。私は普段、少人数での会話であれば、みんな私が理解できるようにハッキリと話すよう意識して話してくれるため、聞き取ることができる。しかし、大勢での会話では複数人の声が重なったり、口元が見えづらくなったりと、どうしても少人数の時のように正確に聞き取ることは難しくなってしまう。
きっとみんな、少人数での会話では私が普通にコミュニケーションを取ることができているために大人数でも同様に会話を理解できていると思い込んでいる、大人数だと楽しくなってついつい私が大人数での会話が苦手ということを忘れてしまうのだろう。時々タイミングを伺って、話の内容を聞くことがあるが、今までのワイワイした雰囲気を崩してしまうようで、なかなか難しい。そのため、大人数での会話では私だけが会話に入れず、取り残されているような気持ちになることが多い。
Aはそんな私の様子に気づき、それまでの会話の雰囲気を崩すことなく、さりげなく私に寄り添ってくれたのだ。それが私にとっては涙が出るほど嬉しかった。Aとは同じ部活ということもあり、元々仲良くしていたが、クールキャラであったため、その時は少し驚きもあった。しかし、確かにAはさりげなく人に寄り添うことが上手だった。みんなは先に行ってしまっているが、準備に時間が掛かってなかなか出発できていない人がいるときは一緒に準備を手伝っていたり、誰かが泣いているときには傍に行って寄り添っていたりなど、常に冷静に周りのことを見て素早く行動をしていた。それも周りの目につくようにではなく、「さりげなく」である。
今回は聴覚障がいのある当事者の立場から、自分自身が「取り残された」と感じた経験を述べたが、障害のある人やLGBTQ+、外国人など、特にマイノリティの立場にある人々は、自分のことを相手に理解してもらうことができずに「取り残されてしまう」、社会から孤立してしまう傾向にある。しかし、私は「取り残される」可能性はそういったマイノリティの立場にある人々だけでなく、全ての人々にあると考える。
誰にでも苦手なことや、コンプレックス、人には簡単に言えないような過去を抱えて生きている。また、それらは個人によって異なる。だからこそ、その人の困っていること、悩んでいることを他人が全て把握することは非常に難しい。「誰ひとり取り残さない」世の中をつくるために必要なこと。それは、みんなそれぞれが心の奥に抱えていることを少しでも吐き出せるような環境をつくり、私たちがそのサインに素早く気付けるよう、常に周りのことを観察するよう心掛けること、そしてその人にさりげなく寄り添うことであると私は考える。
私もAのように、「取り残されている」と感じている人に素早く気付いて「さりげなく」寄り添ってあげられる、そんな人になりたい。
エーザイ特別賞 <小論文部門>
・松山峻大 滋賀医科大学医学部医学科3年 人生の65周年を迎える君へ
「あんたは何の仕事をしてるんや」
昨年の冬、ご飯を食べていたら、急に祖父にそう話しかけられた。私は最初、自分に言われてるんじゃないんだろうな、と思い、ご飯を食べ続けていたが、ふと顔を上げると、祖父はこっちをぼんやりと見ていた。「僕?僕は今大学生やで!」と返すと祖父は「そうやったか」とニコッとつぶやいて、また箸を取った。2年前くらいからだろうか、祖父が「言葉が出てこないんや」と言うようになった。母から、祖父が最近、色んなことを思い出せなくなってきたという話を聞いていたが、私が大学生であることを忘れてしまっていた祖父を見て、とてもびっくりした。
その後、大学の臨床の授業で認知症の勉強をしていくと「これ、じいちゃんの症状と似ているな」と気付いた。でも気づくだけで、自分には何も出来なかった。「認知症じゃない。ちょっと物を思い出しにくくなっただけや」とずっと自分に言い聞かせてきたけど、現実は正直だ。両親に「認知症の新薬出るんやって。じいちゃんに使えへんのかな」とか「認知症対策にこんな活動もあるんやって」て言ったり。ほんとはじいちゃんには使えないし、そんなことを言っても、今の祖父にはもう難しいことも分かっているのに。
先日、私の家族と、母の弟たちの家族と、祖母を含めて話し合った。祖父を施設に入れるかどうかの話し合いだった。母も、母の弟たちも祖父も、半年間ずっと考えて話し合って出た結論だった。祖父は昔、心臓の病気を患ったことがあり、今でも毎日心臓の薬を飲まないといけない。でも、その薬を飲むことも忘れるようになった。そして、祖母も、毎回それを指摘することができなくなっていた。このままだと、祖父が心臓の病気を再発してしまうことを危惧して、薬の管理をできる環境に祖父が居てもらうための、母と母の弟たちの決断である。私も話し合いに参加していたが、何も言えなかった。母が「この薬を飲まないじいちゃんは危ないねん」と祖母に強調するために私に投げかけられた言葉に対して「そうやね」と返すことしかできなかった。施設の入居費用の話になって、費用の捻出の話になり、将来的に祖父母の家を売る話が出ると、祖母は何も言わなくなった。祖母は涙をためた瞳を話し合いからそらし、自分が住んでいる家を眺めていた。
高校を卒業して、すぐに医学部に合格することができなかった私に、祖父は予備校代を渡してくれた。「お前が医者になったら、ばあちゃんの面倒だけみてやってくれ。わしは先にいくけど、ばあちゃんはいつまでも元気やからな」と祖父に言われたことを今でも鮮明に覚えている。医学部に入学したら、何か少しでもじいちゃんのためにできることがあるのではないかと思っていた。だけど私にできるのは、週末の17時半くらいに祖父に電話をかけることと、数か月に一回実家に帰る際に、近所の祖父母家に寄ることだけだ。物心ついたころから「夜になったらじいちゃんとばあちゃんの家に電話」という習慣が身についていた。私が成長するにつれて、祖父母の晩御飯の開始時間と布団に入る時間が早くなった。だから最近は、祖母に晩御飯の時間を聞いて電話をかけている。電話に出る祖父は、私のことを思い出し、「最近はどうや」と話しかけてくれる。私は部活のこと、友人のこと、大学の授業のこと、バイトのこと。思いつくことを何でも喋る。「そうか。元気でやってねんな」という祖父の笑い声が聞こえて、話し終えたら私は電話を切る。「まずは相手と向き合って話をしてみること。まずはそれからや。」私が尊敬する先生の言葉が、胸の中にあった。
高齢化社会に伴い、認知症に罹患する患者さんの数は増えている。2025年には65歳以上の高齢者の5.4人に1人の割合で、認知症になるというデータもある(参照:日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究)。医療技術が進歩した現在でも、認知症を完全に治すことができる薬や技術は確立されていない。また、私の祖父が直面しているような、認知症や介護の人員不足や介護費の問題は大きくなっており、向き合う課題は数多く存在している。この先、長く生きれば生きるほど、生きづらくなる世界が待っているのかもしれない。
だけど、私はみんなにいつまでも元気で健康に生きていて欲しい。まだ学生で、お金の面や医療の面で、祖父を助けることができない私は、今の祖父と向き合って、今の私ができることをしている。みんなを救うことができる大きな解決策を生み出すことは難しいかもしれない。だけど、自分の目の前の相手と向き合っていくことで、一つの答えを生み出すことはできる。そして、その積み重ねが、きっと強い解決策につながっていくはずだ。
みなさんは、自分の家族や友人、大切な人がその時を迎えた時、どうしますか。そして、自分がその立場になった時、みなさんはどうしたいですか。
パーソネルコンサルタント特別賞 <小論文部門>
・浅沼和 老松中学校 2年 私は妹
私は妹だ。私には二歳上の姉がいる。
私の姉は生徒会副会長をやっていたり本を出版したりNHKに出たりしている。なので
「あの人の妹なんだ。」
「この前お姉ちゃんテレビ出てたよね。」
と言われる。妹として誇らしいと思う部分もあるが姉の影響力は大きく、妹としか覚えてもらえないことがよくある。
「あ、〇〇の妹だ」
という言葉は今まで何回言われたか数え切れないほど言われた言葉である。
姉に
「妹っていいよね。何でも許してもらえるし。」
と、言われたことがある。姉にもそれなりの苦労があるんだと思うけど何でも許してもらえるわけじゃない。
私は中学二年生だ。今年で三年生になり受験の年となる。私の姉は勉強もできる。
なので、
「私が二年生のときは内申もっと高かったよ。」
とも言われる。親にも
「お姉ちゃんはもっと成績いいのに。」
と比べられることがよくある。
妹や弟ならよくある経験だと思う。そういう細かいところから家族の中に亀裂が生まれ始める。
私は一つ姉に言われた、忘れられない言葉がある。
私が8歳、姉が10歳だったときの話だ。姉と喧嘩した時に言われた言葉だ。
「あいが生まれてこなければ、ママはわたしだけのものだったのに。」
喧嘩中にいわれた何気ない言葉だったが、私には強く心に残った。生まれてこなければという言葉を聞いてとても辛くなった。別に生まれてきたくて生まれてきたんじゃないのに。という気持ちと同時に私が生まれてこなければ姉は幸せだったのかなと思うようになった。
家族の中で私はいらない存在なんだと思い、家出したいとも思ったこともあった。
そんな実体験を活かし、誰一人取り残さないというテーマの中で私は、家族の中で一人でも辛い思いをする人がいなくなるようにしたいです。家族は学校の友達とは違いどれだけ嫌っていても、簡単に離れることのできない存在です。家族は互いを愛したり尊敬したりすることで、大人子供関係なく高め合っていける存在だと思います。妹は料理ができる、妹はきれいに字がかけるなど、姉に比べてダメな子供だなとマイナスの部分だけ伝えるのではなく褒めてあげてほしいです。
妹、弟関係なくその人はその人として見てほしいです。
この文章を読んでいる人には家族がいる人が多いと思います。その家族を大切にしてほしいです。
私も家族を大切にして誰も取り残さない、家族全員が幸せな家庭を作りたいです。
入賞 <小論文部門>
・緒方 水花里 早稲田大学文化構想学部 卒業 食べない奴は生きる価値なし “
私は取り残される。電車やバスで優先席に座ると睨まれる。ワンオーダー制ですと言われ飲食店に入れない。病気の名前を伝えたら内定が取り消しになった、がかといって障害年金も降りなかった。私は10人に1人が死ぬという最も死亡率の高い精神疾患を患っている。けれども端から見たら普通の人で、社会や制度に気遣われることはなく、寧ろ贅沢病だとか病気は甘えだとか言われる。私は摂食障害である。
ダイエットが原因だと言われるがそれだけではなく、社会的・心理的な要因があるとされている。特効薬もない。私だってなりたくてこの病気になったわけではないのに、世間の風当たりは冷たい。痩せ過ぎや体力不足で目眩がしても必死で耐えねばならず、道で倒れたことが2回ある。立っていられないので何処か中に入ろうと店の扉を開け、「飲み物だけじゃ駄目ですか?」「ワンフードお願いします」のやり取りを重ね更に意識が遠くなり、出されたものを残せば勿体無いとまた睨まれる。「ただ普通に食べることが出来ないだけなのに、どうしてそれが就職に繋がるのですか?」「うつみたいなもんでしょ? 精神科に通院してるなら、ちょっと」 一会社の社長に実際に言われて、私は泣いて泣いて、弁護士にも保健所にも相談した。けれども「うつでの訴訟事例はありますけど」「摂食障害は障害年金給付の対象外なので」とどちらでも一蹴された。働けないならせめて社会が守ってくれれば良いのに、他の精神疾患で認められるはずの権利が、私には認められない。
国内の患者数は22万人以上、こんなに大勢の人が私と同じように苦しんでいる状況をどうしたら良いのだろうか? まず摂食障害という病気が誤解なく社会に知れ渡ると良い。患者は痩せている人ばかりではない。今私は所謂「拒食症」であまり量を食べず、165cm40kg未満という超痩せ型だが、小学生の頃は体重が70kg台あった。にも関わらず摂食障害で、その中の「過食症」だった。母子家庭で家にろくに食べ物がなく、給食の余りをたらふく持って帰ったりバターや練乳を舐めたり、そんな食生活が止められなかった。過食は自分の意思には関係なく起きた。他の人のように普通の食事が出来ないだけなのに「デブ!」「ブタ!」 病気として見られるどころか非難ばかりされた。「普通の人が座れなくなる、デブが電車で座んな」 驚くことに私は太っていても痩せていても公共交通機関では座席に座れないらしい! 仕方なく立ってスマホでテレビを見ると大食い選手権があっていて、ありえない量を食べる人がもてはやされていた。でも「あ、この人病気だ」「食べた後に全部吐ける人だ」 同じ病気であるので私は見ただけでわかる。日本では拒食症のことはよく取り上げられるが、過食症も然り過食嘔吐についても全く理解が進んでいない。それどころか金儲けの手段として使われることもあって、私もYouTuberになって大食い企画をやれば、障害年金を貰えなくてもやっていけるのかしら。なんて一抹の希望を持ってレストランに行く。ワンフードすら食べ切る自信がないので店の扉の前を右往左往する。
そして、病気が社会に認知されることに加え、痩せや肥満、体型についての価値観が問い直されると良い。日本では若年層の痩せ過ぎが問題となっていて5人に1人が栄養失調とされる。その裏には痩せていること=可愛い、正義だという痩せ信仰があり、思えばテレビやSNSでも「可愛い」人は皆痩せていて、だから70kgの私も必死になってダイエットをしたのである。その甲斐あって非難は浴びなくなったが飲食店に気軽に入ることすら出来なくなった。一方海外には肥満だが生き生きと自分らしく活動しているプラスサイズモデルもいれば、痩せ過ぎのモデルの活動を制限する法律だってある。日本の価値観は少しおかしいのだ。痩せているより健康的であったり体型に関わらず自分のありのままの姿を、個性を認められたりする方がずっと良いし、誰も苦しまない。
貧困で食べられない人のことは考えるのに、裕福な国にあって上手く食べられない人や食べることしか出来なくて太っている人は無視する、というのがSDGsの支援のあり方ならば、私はずっと取り残される。22万人以上の人もずっと取り残される。それって正しい支援なのだろうか。私はいつか堂々と電車やバスの席にも飲食店の椅子にも座ってみたい。ワンフードを頼もうが頼むまいが、太っていようが痩せていようが、誰しもが笑って居座れる世界の方がずっとずっと優しい気がする。私と同じような22万人が座れる席を、どうか、作って下さい。
・上野 一志 大阪大学 学部3年/マンチェスター大学 交換留学 日本に心の点字ブロックを
「今よりもっと旅行したいのだけど目が不自由だとそういう訳にもいかないのよ~」
別れ際、発車ベルが鳴り響く新大阪駅でそう微笑まれた。優しく微笑んだ瞳の奥から『どうしようもないの』という諦めの声が聞こえた。目の不自由な方の大阪観光に同行するボランティアを終えた自分に無力感が波のように押し寄せた。
旅行が好きな自分にとって、その目の奥の諦めはなによりも辛かった。
日本は間違いなく”バリアフリー”先進国だ。海外では日本の障がい者に対するサービスは称賛されている。またこの島国では点字ブロックがない道路やホームドアのない駅を探す方が難しい。しかし『取り残されている』人がまだまだ存在するのだ。
例えば、A駅からC駅まで行く際に、B駅で別の鉄道会社に乗り換えると想定する。この際に乗り換える先の鉄道会社のB駅が離れている時、駅係員に「たった1mでも敷地外なら介助はできません」といわれることもあるそうだ。想像してみてほしい、目をつむって濁流のような人並みの中でラッシュ時の駅を歩くことを。
通いなれた場所なら介助がなくても大丈夫だろうとみなさんは思うことだろう。しかし初めての場所に旅行する際などはどうしても駅係員の介助が必要な場合が多い。そんな時には手配を利用する会社ごとに行わなければならない。
そんな視覚障がい者の『どこかへ行きたい』という想いを支えるために大阪府視覚障害者支援の会クローバーは存在する。ガイドヘルパーの利用時間を超えた人や関西に来た観光客で目が不自由な人のために交通費以外は取らずに無償で手引き歩行のボランティアを関西全域に派遣している。
でもボランティアも各々の生活がありすべての依頼には応えきれていない。そして補助金も打ち切られ存続が危うい。また無力感の波だ。
『ボランティアなんて本当はいない方がいいんです、ボランティアが必要ということは社会がまだ障がいを障がいにしているということです』
そう真剣な顔で協会長は講習会で話してくれた。
そうだ、自分の力でボランティアなんかなくても、駅員さんが乗り継ぎの時も効率よく障がい者の介助ができるようになればいい。
鉄は熱いうちに打てだ。早速、大学の研究支援事業を使って研究を始めた。手探りで日本のそして各国の状況を当たった。実際にイギリスに行って鉄道会社の障がい者支援サービスに同行した。二年目である今年からはある交通機関のバリアフリー推進の方と一緒に研究を進めた。
今はアプリで簡単に車いす利用者も視覚障がい者も介助手配を申し込めるシステムを全国で導入できないかバリアフリー推進の方と一緒に模索している。
「事業者に最小限の負担で、利用者に最大限のサービスを」
そんな目標をかなえるためにアンケート調査と事例調査に当たった。こんな途方もないことこんな一大学生にできるはずがない。そう思っていた。でもアンケート調査を通じてたくさんの障がい者の方から応援のメッセージを貰った。「あの景色がみたい」「あの人に会いたい」そんな願いは誰しもにとって簡単に実現できる願いであるべきだ。
でもそのシステムを導入できたとしても限界はあるだろう。それが研究を進めていくうちに徐々に明確な輪郭になって押し寄せてくる。まただ、無力感の波だ。
無力感とともにイギリスに来た。そこでは日本でよく見かけた「困っている視覚障がい者」が一人もいない。なぜだろう、疑問に思った。日本にいる時は駅の濁流のような人並みの中に、一人呆然と立ちつくす白杖をもつ人を毎日のように見かけた。そんな人を見つけると自分は「お手伝いしましょうか」と声をかけていた。他の何千何万人はそんなこと気にも留めない。
でもそのイギリスで得たその疑問の理由が分かった。車椅子の人が横断歩道を渡ろうとすれば通りすがりの人が絶対に声をかけ、手伝っている。イギリスにはまともな点字ブロックがない。そんなものがなくても通行人が助けてくれる。
間違いなくイギリスは日本より” バリアフリー”の面で遅れている。でもイギリスは日本より“心のバリアフリー”先進国のはずだ。
日本に足りないものは何だろうか。「点字ブロックあるし」「音声案内あるでしょ」「エスカレーターに乗れば」そんな機械や他人頼みだけでいいのか?
本当に日本はバリアフリー先進国だろうか?
「障がいを障がいとするのは遺伝でもなんでもなく私たち社会の責任である」
この言葉に従えばイギリスに視覚障がい者や身体障がいはないのかもしれない。まだまだ理想論ではなく現実を着実に一歩ずつ変えていく時だ。
僕の目標はボランティアも駅員さんによる介助もなくすことだ
・土岐 梨華 石川県立金沢中央高等学校1年 多様性を認め合える社会
私は、脊髄性筋萎縮症(SMA)という難病で歩くことができない。人工呼吸器も二十四時間つけている。私は今まで生きていて、社会から取り残されていると感じる出来事がたくさんあった。
保育園は、地域の保育園で受け入れてもらえることになり、同年代の子どもたちと遊んだり関わることができた。私が困っているときや何かをお願いしたときは、嫌な顔せず優しく手伝ってくれた。運動会のかけっこでみんながゴールした後、遅れながら先生と一緒にゴールを目指して走っていたときも、「りんちゃんがんばれー」と大きな声で応援してくれて力になった。それは、当たり前のように思えて私にとっては大事な経験だった。周りの子どもたちも、私に対して抵抗なく接してくれて、排除されている感じはあまりなかった。
しかし、小学校に入学する頃、現実に突き落とされることになる。私の希望は、地域の小学校の通常学級に在籍することだった。母が、学校や教育委員会の方などと話し合いを繰り返したが、何度も特別支援学校を勧められた。根気強く伝え続けたが、叶わなかった。結局、地域の小学校の特別支援学級になってしまった。たまに、交流クラスでみんなと授業を受けることもあったが、普段から関わることが少ないのでどう関わっていいのか、お互いによくわからなかった。どうして、みんなと同じ教室で授業を受けることができないのか不思議だった。特別支援学校や特別支援学級が悪いというわけではないが、本人が希望している学校に行けるのが当たり前になってほしいと思う。教育を受ける環境というのはすごく大事なものだと思うし、選択によってはこれからの人生にも関わってくると思う。勉強だけの場ではなく、子ども同士でのコミュニケーションや会話の中で知ったり、学んだりできる。他の人に進路を決められるのは違うと思う。地域の学校で学びたいと思っている、障がいがある人、外国人などいろいろな人がいる中で、エレベーターを設置したり、タブレットを活用したり、周りの人それぞれの考えを共有し、その子に合った教育環境を整えられるように、多様な子どもたちに対応できるような教育になってほしいと思う。現在も前よりは、考え方が変わってきていて多様性を認める動きがでてきているが、実際には詳しくわからなかったり、自分とは関係ないと関心のない人が多い。まだまだ、取り残されている人がいるということを知ってほしい。
中学校に入学する頃は、学校看護師さんや、支援員さんにもサポートしてもらって地域の中学校の通常学級になった。長い時間、みんなと授業を受けることは初めてだった。最初は、たくさん人がいる環境に緊張していたが、だんだん慣れてきて授業中にいろいろな人の意見が聞けたり、笑い声が聞こえたりしてくる環境にいられるのが楽しくて嬉しかった。一部には悪口を言ってきたり、からかってくる人がいて嫌な気持ちになるときもあった。でも、友達が話しかけてくれたりすることが嬉しかったし、前よりもスムーズに人と話せるようになった。
高校は、地域の定時制高校に入学した。ほとんどの人が、今までに不登校を経験しているので、からかってきたり、悪口を言ってくる人がいなくて気持ちは楽だ。まだ、入学してあまり経っていないのでこれから楽しいことが待っているといいなと思っている。教育を勝手な都合で分離するのではなく、それぞれの希望に沿って受け入れられる環境になることを願っている。
私は学校だけでなく、出かけるときにもいろいろな出来事があった。まず、一歩外に出て人と出会うたびに、ジロジロ見られて視線を感じる。子どもが興味津々で見ているのも気にはなるが、嫌な気持ちにはあまりならない。でも大人が、私のことをジーッと見ている子どもを叱ったり、手を引っ張っていったりする様子を見ると気持ちはわかるが心が痛くなる。見られることには慣れているが、大人が何も言わずただ叱ることによって、こういう人は見てはいけない触れてはいけないんだと間違えた認識をしてしまったら、大人になってもそういう対応をとってしまうのかなと思う。障がいがある人のことを見る機会もあまりないので知らないのも当然だと思う。だからこそ、大人が子どもにただ叱るだけでなく、教えられる範囲で「いろいろな人がいるんだよ」ということを教えてほしい。
みんなが取り残されない社会にしていくためには、まず一人一人が興味、関心を持って知ることが大事だと思う。多数の人の都合によって分離されることで、傷ついたり、人生を変えられる人もたくさんいることを知ってほしい。今、この時間も差別で苦しんでいる人がいる。今、自分ができることを考えてほしい。私も、できるだけ相手の気持ちに沿って考えて行動したい。後悔を少なくするためにも、前を向いて自分が信じた道を生きていきたい。
・三村 咲綾 新潟医療福祉大学1年 誰ひとり取り残されない教育
2022年9月国連は、障害の有無などによって分けることなく全ての子どもが共に学ぶインクルーシブ教育を推進するよう日本に勧告を出した。高校で難病や障害のある子を探究していた私は、3年前にインクルーシブ教育を知り、素晴らしいと思いアンケートを行った。当事者や家族、障害のある人に関わる職種の方々233人から回答を得たが、インクルーシブ教育を望まない声が多かった。思い返してみると、私も小中学校で過ごすことが辛かった。みんな一緒に過ごすことは良いことなのか?考えるようになっていた。
日本では50年程前に就学免除や就学猶予が原則として廃止され、養護学校の義務化により重度な障害があっても学校に通えるようになった。一方で地域の学校から障害児の排除が見られるようになった。そして、20年程前に特別支援教育が始まり分離教育が進んでいった。
私は、福島で生まれ就学相談を経て地域の学校で過ごしてきた。大学進学を機に新潟で過ごしている。歩き方を真似されたり、からかわれていることを感じた小学校1年の冬、上靴をハイカットの装具にすることになった。学校ではみんな同じような上靴を履いている。自分がみんなと違う存在になるのを感じた。
5年生になる時に進行性の難病とやっと診断がついた私にとって、中学1年から参加している患者会などで悩みを共有して過ごすのは楽しく大切な時間だ。『ごちゃまぜ』などの障害者と健常者が交流する企画には参加する気にはなれない。障害のある人の存在を感じる機会をあえて企画することに違和感があるからだ。
夏休み3年振りに対面での患者会が京都で開催され歩行器を使ってる子が大阪から参加することになった。2日前に京都入りした私はその子が移動で困らないように歩行器が移動しやすいルートを考えた。私は長時間立っていることが辛く、みんなと同じペースで歩くのは難しい。階段は大変なので、エレベーターやエスカレーターを探す。
歩行器の場合は、エレベーターしか選択肢がない。出口に近いとは限らないので、移動距離が長くなる。初めての場所では、エレベーターを探すだけで一苦労な上に移動方法に選択肢がある人達と一緒に順番を待たなければいけない。共に行動しなければ本当の大変さを知ることはできないと感じた。相手を知ること、自分と重ねて考えることは、とても大切だと思った。
しかし、私が通った小中学校では、支援学級の教室は普通学級の子が通らない場所にあった。同じ校舎にいても違う存在だった。私にとっても遠い存在になっていった。無知無関心、そして、無理解から差別や偏見が生まれるのかもしれないが、分離された教室では、お互いのことを理解することはできない。
調べてみると、本場のインクルーシブ教育は、同じ教室で一緒に学ぶために先生が複数人配置され、それぞれにあった教科書を準備することが第一歩だと分かった。平等ではなくみんなが公平なのだ。私が望んできた配慮は、特別扱いではなかった。我慢したり頑張り続けなくても、先生や友達に理解してもらえるのだ。フルインクルーシブ教育の先駆けと言われるイタリアでは、50年前から取り組まれていたことを知り日本はとても遅れていると感じた。国連に訴えたのは、支援学校の人達だった。就学前健診の判定で地域の学校に入れない時点で日本はインクルーシブ教育とかけ離れているのだろう。
私は、学校で助けてほしいことを先生に伝えても理解してもらえず辛いことがあった。発達障害など目には見えない辛さがある子も増えている。現代社会で配慮が必要なのは障害のある子だけではない。通常の学級で過ごすことが辛い子もいて、別の居場所を必要とする場合もあるのだ。そのため支援学校や支援学級を希望する子が増加しているが、その現状を日本での分離教育が成功していると考えるのは、分離教育で育った私たち日本人の弊害ではないだろうか。
インクルーシブ教育は、理想だが今の私には綺麗ごととしか思えない。しかし、長い間、分離教育を続けた日本の学校ではいじめも不登校もなくならないどころか増え続けている。日本は教育から変えなければいけない。単に分離をやめるのではなく、多様な選択肢からより自分に合う環境を選べることが大切だと考える。
障害のある子の教育は、両親や兄弟児のためではなく本人が生きていくためのものだ。私は、障害がある子と過ごすことが健常児の社会勉強としてのみ利用されず、1人の児童、生徒として同じ教室で学べる学校になって欲しい。
義務教育の大切な時間、一緒に過ごすことでお互いの理解が生まれ、分断は軽減されていくだろう。そして、10年後、20年後には他人の気持ちに寄り添える人間が育つのではないだろうか。「共に生きる」ために「共に学び、共に育つ」。誰もが自分らしく生きやすい社会のために「誰ひとり取り残されない日本の教育」をこれから作らなければならない。
・川上 友聖 立命館大学4年 / 東京大学大学院情報学環教育部1年 わかりやすさの暴力性
「被災者」はほんとうにかわいそうなのか。この問いに私が向き合ったのは、東日本大震災から11年経った2022年だった。
私の祖母は、福島県双葉郡出身で、叔父は東京電力福島第一原発にて勤務していた。東日本大震災では、多くの親族が双葉郡にて被災し、私の自宅でも避難受け入れをした。テレビで常に流れる被災した双葉郡や原発の映像、「なにもないね、帰れるのかな。」と呟く祖母、時折鳴る電話で知る親族の訃報、知らせで悲しむ親族の姿、この光景を今でも私は忘れる事はない。親族が避難先を移した後も様々な情報に触れた。メディアによる避難や放射線量、健康に関する報道、震災を記した書籍など、多くが悲しみや哀愁を孕んだ言葉で表現された。私自身も漠然と被災地と被災者に対して憐れみの印象を持つようになった。
大学入学後、大学主催のスタディツアーの参加が双葉郡と一層深く関わる契機となった。現地視察では、ハードの復興が未だ進まない廃墟混じりの報道で見た景色が眼前に広がり、親族のふるさとの現状を見つめる機会となった。被災者が身近にいる自分だからこそ、被災した方々に対して出来ることはないかと手探りしつつ、多くの方と対話を繰り返した。そんな中、双葉町役場に務める橋本靖治氏の言葉、「同情ではなく共感してほしい。」に出会う。まちとひとに憐れみや同情を抱くのではなく、まちに関わる人や取り組みに共感してもらいたいという真っ直ぐなメッセージの力強さに私は心を打たれた。同時に自分が無意識に「分断」を助長していた事実と残忍さを自覚することになった。
被災していない「非被災者」である私は、未曾有の大災害で生活が困難になる程の被害に遭った方々を「被災者」として捉え、悲しみや憐れみを無意識の内に感じていた。結果として、そんな同情心から私は彼らと出会い、言葉を投げかけていた。つまり、目の前のあなたではなく、「被災者」としてのあなたと向き合い、被災した方々の役に立とうと行動した自分は、彼らを「被災者」という枠組みに取り残し続けていたのだ。「非被災者」と「被災者」のわかりやすい二極化の暴力性は計り知れない。県外に避難した町民の方に話を聞くと、避難先では「被災者は放射能で危険」「被災者だから避難先では慎ましく暮らすべき」の言葉を投げかけられ、いつまで自分が「被災者」で居続けなければならないか悩んだと言う。
このような「わかりやすさの暴力性」は被災者に限らず、日常に多く潜んでいる。近年、ひとりひとりが違う個性を持ち、多様であるからこそ、お互いを理解し合うために多くのカテゴライズが存在する。それは16personalitiesのように性格から16に分けるものもあれば、精神病など可視化しにくい病を病名として可視化するもの、自らの特性を伝える手段としてLGBTQ +と表現するなど。本来、お互いを理解し合うためにあるカテゴライズが「わかりやすさ」となり、ひとと向き合う事から遠ざけているのではないかと感じる。「あなたはADHDだもんね」「きみってENFPだよね」「やっぱバイセクシャルってそうなの?」のように何気ない会話や行動の中に「わかりやすさの暴力性」を孕んでいないだろうか?その言葉ひとつひとつが相手をカテゴライズに縛り、苦しめていないだろうか?
ひとりひとりの持つ個性や多様性を認識し、生きやすい社会が目指されている今だからこそ、「わかりやすさ」に囚われず、ただ純粋に目の前のあなたに向き合い、対話ができる人に私はなりたい。
竹谷 優希 水城高等学校 3年 言葉ひとつでひとりの人生が変わる
あなたは、ある言葉をかけられたことで何かが変化したことがあるだろうか。私は何度かある。
私は高校に入学して興味のある部活に入部した。ある日部活中に何気ない会話の中で「偏差値が10以上違うと会話が成り立たないって本当だね、話しているとよく分かるよ」や、部室に虫が出て外に逃がしたとき、「虫を素手で触るのは気持ちが悪い、今日は触らないで」と言われたがある。私は、これらをきっかけに部員と関わるのがつらく部活に行けなくなり、好きだった部活を夏休み前に辞めることになってしまった。今でも直接言ってきた人に学校や、駅などで見かけると、思い出してしまい、辛くなる。
また、三年生に上がってから今まで高頻度で「太っているから痩せても無駄だ」「歩いただけで地面揺れる」など体形の事を言われるようになった。確かに私は、標準体重よりは重い。しかし、自分で体形の事を悪く言うのは何とも思わないが、他人に言われるのはとても重くとらえてしまう。これがきっかけで私は、「太っているから痩せないと、食べたらいけない」と思うようになってしまい、摂食障害になってしまった。
私は精神的、肉体的に悲鳴を上げ始めてきていたらしく二年生から精神科に通い続けている。しかし、上の二件や、受験のストレスなどで三年生になってから一度命を絶とうとした。生きている意味が分からない、自分がこの世に存在する必要がないと思い命を絶とうとした。幸い失敗に終わった。病院に行き診察が終わり最後に、「次も会おうね、それまでもうちょっと頑張ってみようか」と言われた。私はこのさりげない一言ですっと感じていた重荷のようなものが軽くなった気がし、もうちょっと生きてみようと思うようになった。
このように言葉ひとつで、人を「生かす」「殺める」ことができてしまう。さりげない一言で人を悲しませ、苦しい思いをしている人はたくさんいると思う。悪意のある言葉で人を傷つけることをなくすことは可能だ。しかし、悪意のない言葉で人を傷つけることをなくすのはすごく難しいことだと思う。悪意のない言葉で傷ついた人たちは、ずっと気にしてしまう事もあるだろう。人の価値観はそれぞれ違う。その価値観の違いで理解されない、傷つけることをしてしまう。嫌なら嫌だと言うことが一番の解決策なのかもしれない。しかし、言えない事がほとんどだ。周りの人が少しの変化に気づくことや、自ら「相談」という形で人に話を聞いてもらうだけでも少し楽になる。
ひとりひとりが価値観の違いを理解し合い生活していくことが人を傷つけないための第一歩だろう。
・鈴木 陽菜 金城学院大学2年 あの時の覚悟は今でも忘れない。そしてあなたたちのことも。
皆さんは自殺をしようと考えたことはありますか。自殺はSDGsの「3すべての人に健康と福祉を」に含まれる内容ですが、日本の自殺率の高さはG7の中でワースト1位という現状です。「若者の自殺者を減らすための心の電話」という広告をよく見ますが、実際あの電話はかけてもかけても繋がりません。何故それを知っているか。それは私が利用したくてもできなかった人だからです。「おかけになった電話は現在混み合っております。お時間を空けてから再度お電話ください」なんて機械音声に3回も跳ね返されればもうスマホの電源は落とします。お時間を空けてからなんて自殺者に先延ばしの願いをするな。死にそうで、それでも誰かに助けて欲しくて勇気を出して電話をかけたら機械音声に門前払い。この気持ち分かりますか。
「自殺者は心が弱い」「メンタルが弱いだけ」と言う人は少なくありません。ならば逆に問わせていただきます。ビルの屋上で下を見た時、あなたは床のない最後の1歩を踏み出せますか。その行為を正当化する気は全くありません。ただ、その場所にその窮地に追い込まれた経験のない人間が自殺を語るな。それだけは言わせてください。
私は今生きています。理由は単純です。上手くいかなかったからです。それ以上でも以下でもありません。上手くいかなかったから生きている。でも生きていて良かったことはありました。新しい友人関係や新しい趣味。楽しいことは山ほどあります。そして楽しいことの比にならないぐらい苦痛があります。生きるって本当にしんどいんですよ。
私は自殺は大きく分けて2つあると思います。1つは1つの大きな理由。主にいじめや経済的な困難。抱えている問題がどうしようもなさすぎて死ぬしかない。そんな最後の選択です。もう1つは小さなことの積み重ねです。過去の経験やストレスの蓄積、日常的な耐え難い苦痛。それが一定のラインを超えると「もういいや」となってしまいます。私の感覚ですがこれは鬱病と似ているように感じます。結局、自殺も鬱病も最後に背を押すのは第三者の心無い発言です。「俺らの時代は」や「これだから最近の若者は」という言葉を無意識にかけていませんか。それで元気になると本気で思ってますか。あなた方の何気ない一言や心無い言葉が人を殺しているのです。自殺だから自分は関係ないと本気で思っていますか。もし思っているのならば自殺者は減らないでしょうね。散々見て見ぬ振りをして、散々軽く扱っておいて死んだら「知りませんでしたごめんなさい」で終わらせるのですか。
誰ひとり取り残さないとは何なのか。
そんな綺麗事で本当にこの国は良くなりますか。
人が死なないと何も変わらない国のままでいいのですか。
人が死んでも何も変わらない国でいいのですか。
自殺を考えた人間は自殺を覚悟した時のことを一生覚えています。そして私たちの命や言葉を軽く扱ったあなた方を一生恨んでいます。
・飛山 愛梨 福井県立武生高等学校1年 少しづつ、取り残されていく
「塵も積もれば山となる」この言葉は、どんな時に使われるだろうか。少しづつでも努力すればいつかそれが実る時が来るよ。とてもポジティブで、私が好きな言葉だ。それと同時に、自分の遅れを実感させられる言葉でもある。
両親が小さい頃に離婚し、母がシングルマザーとして育ててくれた。こういう状況に当てはまる人は大勢いるだろうし、私もその一人だ。地方の生まれで、田舎暮らしが長い。こういう人も大勢いるだろう。もちろん、私もその一人だ。今あげた状況は、別に人生にとって特段大きな弊害ではないように聞こえる。だって、そんな人はたくさんいるのだから。ただ、小さな弊害も積み重なっていけば大きな弊害となりえると思う。
私は母子家庭で育って、至極一般的な生活を送らせてもらっているが、塾や習い事などの新しいことを始めたいと思ったときに金銭面の心配無しで即決できるほどでは無かった。母はそれを私に悟らせないようにしていてくれたと思うが、成長するにつれ私も気づいてきて、一時期何がしたい何が欲しいと言いづらく感じる時もあった。
そして私は高校生になり将来の進路について考えるようになり、ここで改めて地方の壁を感じることになる。大学からの告知が自分から調べていないと入ってこなかったり、イベント会場が遠すぎて参加が難しかったりするのだ。自分の将来を左右するものだから出来る限り実際に参加したいが、それがなかなかに難しい。もちろん参加できる子たちもいた。イベント会場までの遠征費や参加費を出せるという子たちだ。そういうクラスメイトを見て、後れを取ったと感じずにはいられなかった。
「取り残される人」と聞くと、遠い国の貧困など、自分の周りにはいない誰かを思い浮かべがちだ。大きな問題を抱えて困っているのだからそれは間違っていないのだけれど、灯台下暗しとはよく言ったもので、自分や自分の周りの人のことも考えてみてほしい。大したことがないと思っているものでも、山のように積もった塵のように、それは取り残される原因として姿を現していく。気づいていないものは、改善のしようがない。私たちにできることは、まず現状を自覚すること。ただ認めるだけでいい。自分が取り残される側だと自覚するのはすごく怖いことかもしれない。けれど、自覚しているからこそできる行動もきっとあるはずだ。「小さな弊害」を看過せず、一つずつ改善していこうとする姿勢が、格差のない、誰も取り残されない世界を創ることにつながっていると、私は信じている。
・久保 姫乃 クラーク記念国際高等学校 総合進学コース インターナショナル専攻 2年 置いてきた忘れ物の私
教室に足を入れた時のこの緊張感。どっと背中から噴き出てくる冷や汗。手がどんどん湿ってきて、思わずジャージのズボンに擦り付ける。息が浅く感じて 胃がキュッと掴まれたような痛みがした。私が学校へ行けなくなったのは中学2年生の時だった。世の中が一変した2020年。オンライン授業からやっといつも通りの授業に戻った時である。私は教室に入ることが怖くなってしまっていたのだ。兄に憧れて入った部活動もマスクをして行い、席は間隔を空けて分散登校になった。お昼休みも友達と共に帰るあの放課後だって奪われてしまった。友達と遊ぶということが当たり前ではなくなってしまい自分の部屋に引き篭もる毎日。必要最低限のこと以外は家から出ない生活。普通の生活に戻ってもひとりでパソコンで授業を受けていたことからいつも通りの授業には慣れなくて、誰かの視線が気になって授業には集中できず、ノートすら取れなかった。
ある日の5時間目。国語の授業だった。先生の話も聞けなくなって頭が回らないまま机にうつ伏せになってしまった。気づくと休み時間になっていて友達たちに囲まれたまま私は泣き出してしまった。今思えばその時の私はボロボロだった。既に限界を迎えていたのだ。次第に朝も起きれなくなりご飯もまともに食べれないほど偏食が過ぎていた。
いじめられているわけでもなく、外傷のあるような何かに悩んでいる訳でもない。ただ、学校に行かなければ、誰にも会わなければ元気なのに、と原因がわからない痛みが私を蝕んでいった。それは思ったよりも苦しく、原因を考えているうちに私は私を傷つけるようになった。
中学2年生の時の私は「相談すること」が難しくて、可視化できない心の痛みをどう理解していくか考えた結果、自分を痛めつけることしかできなかった。
中学3年生に上がった頃、母は私をクリニックへと連れていってくれた。不安なまま中に入ると、そこではいろんな人がいろんな想いを抱えながら待合室で呼ばれるのを待っていた。「ああ、みんな同じなんだ。」と安堵した自分がいた。
ふと、自分が今まで歩いてきた道がわからなくなり どうすれば良いのか答えを見出すことが難しくなった時 自我を保てなくなる。私には居場所がない。学校に行けないから私はダメな子。そう社会から周りの人から切り離されたような、忘れ去られたようなそんな気持ちでいた私だが、ここにいる人たちはみんな同じなんだ。私はひとりじゃなかったんだと気づけた。
「誰ひとり取り残さない」この言葉はあの待合室にいた全員に伝えてあげたい言葉だ。私はまだ17歳で、あのクリニックへ通っていた大人たちの事情はわからないし、子供だから母と一緒じゃないとクリニックへは行くことができない。病院やクリニックへ通うのは、世界から取り残されてしまったからではないと思う。私は中学2年生の私をあの教室に取り残したまま高校2年生になった。記憶の中で私はあの席でうつ伏せで泣いているままなのだ。でも今の私なら助けることができる。手を差し伸べることができる。自分が自分らしくありのままでいるために私は今日もあの時の傷と向き合いながら学校へ向かうのだ。後悔はしていない なぜならこれは私の勲章であり生きる印となったからだ。今の私が孤独に感じてしまうことがあるならそれはいつかの私を置き去りにしてしまっているからである。
この世界にも取り残されてしまった人達がいる。誰かが忘れて行った落とし物のように見て見ぬふりをするのが当たり前の世界。社会から切り離されたと感じる人が当たり前のように生活できる毎日を送れるようにするにはひとりひとりが考え方を変えていく必要がある。「見て見ぬふり、言葉だけで行動に移さない、自分じゃなくても誰かがやってくれる」他人任せのような考えが社会の切れ目を深くしていくのだと思う。簡単なことでいい。少しの勇気で手を差し伸べてみたり、泣いている人にハンカチを渡すように、誰かの忘れ物を届けに行ったり。些細な行動が誰かの命や心を救うことがある。そうこれからも伝えていきたい。自分や誰かを置き去りにしない。あの日の私と約束したからだ。
・髙村 幸冠 創価大学 1年 やりたいことをやれるって幸せなこと
「お母さん、本当に申し訳ないんだけどさ…」
これは私がいつもお金に関わる話を母にするときにまず初めに言う言葉です。
私の家庭は、私が小学校低学年の頃に両親が離婚してからずっと母と二人暮らしでしたが、私が大学生になってからは実家のある福岡を離れ、東京で寮生活をしています。そして、大学生になったらアルバイトをして少しでも自分の出費は自分で賄おうと思っていましたが、実際に入学してみると、日々の勉強や課題に追われ、毎日3、4時間しか睡眠がとれない中でアルバイトをすることは難しく、母に頼るしかありませんでした。私はいつもお金が関わる話をするときはなぜか緊張してなかなか言い出すことが出来ません。それは、「申し訳ないな」という気持ちが大きいからだと思います。でも母はいつも「大丈夫、お母さんがなんとかするから。やりたいことをやりなさい。」と言ってくれます。ですが、正直なところ、自分の将来の夢のために留学やボランティア、大学院進学などに挑戦したいと思ってもまず一番に費用のことを考えます。そして費用面の問題から断念したこともあります。
ここで私は、「うちは”見えない貧困“家庭なのではないか」と思うようになりました。この“見えない貧困”という言葉は大学に入ってからよく耳にするようになったのですが、“見えない貧困”とは相対的貧困のことを指し、特に私のようなひとり親世帯では二人に一人が相対的貧困なのだそうです。ですが、私の家庭は、母と二人暮らしになってからも父からも何かと援助をしてもらい、大学も様々な奨学金制度のおかげで通うことが出来ています。しかも普段の生活も、毎日十分にご飯は食べられるし、必要なものがあれば買ってもらえる。しかし、私がそのように過ごせていたのは、母が毎日遅くまで働いてくれていたからなのだと思います。
“見えない貧困”家庭といっても、私のようにほぼ満足に生活できる人もいれば、毎日ギリギリの生活をしている方もいます。例えば、見えない貧困家庭の中でも、ギリギリ支援の対象にならずに、自分のやりたいことを犠牲にしてお金を稼いで生活している人もいます。そして、そもそもそういった支援のことを知らない人もいます。私の友達の中にも二つのバイトを掛け持ちして自分で生活費を稼いでいる子もいます。そしてそういった子たちは長期休暇も帰省に費用が掛かるからといって、実家に帰らない子もいます。特に大学に入ってからは一冊五千円以上もする教科書を何冊も買ったり、何万もするパソコンを買ったり、私のように実家を離れる人はもっとお金がかかり、大学生になって何十万という金額をよく目にするようになりました。私はありがたいことに奨学金をいただいて大学に通えていますが、もしも奨学金なかったら大学に通うことは出来ていないと思います。
これらのことから、その人の状況によっては、見えない貧困家庭が、学生が、社会から取り残されているといえるのではないでしょうか。
現在、政府は多子世帯に対して大学無償化という制度を作ろうとしています。これに対しては賛否両論であると思いますが、もっとこのような様々な人を対象とした制度が作られ、もっと多くの人が自分のやりたいことを思う存分にできる環境を作るべきだと思います。そして、私にできることは何かと考えた時に、大学でお金がかかること、例えば教科書や参考書などの購入の負担を減らすために、教科書などを先輩から後輩に譲る制度をもっと普及させたいと考えました。この制度は実際に私の学部にもあるのですが、多くの生徒が自分で買っています。なので、この制度をもっと普及させることで、少しでも金銭的負担を減らせるのではないかと思いました。
・右遠 太基 慶應義塾大学3年(パリ第一大学へ公費派遣) 障がい者だからできたことー地域社会との手の繋ぎ方ー
「融和と共生」これは、私が地元岡山県にて実行委員として携わる「おかやま桃太郎まつりうらじゃ」のテーマである。これは、岡山県に代々伝わる桃太郎伝説に登場する鬼に扮した踊り子たちが曲に合わせて踊るというものである。私は、踊り子たちが踊る演舞場会場を運営する演舞部会の総務担当幹事として、そして会場責任者として、60万人もの観客の方々が楽しめる会場作りに尽力してきた。しかしながら、本当に全ての人たちが楽しめる環境であるのか疑問があった。夏開催であり気温も高く、体が弱い人は参加しにくい、また、駐車場が少ないため車椅子利用者等の車で移動しないといけない方々にとっては参加ハードルが極めて高かった。そこで、実行委員の私は自身の担当会場であるイオンハレマチ演舞場にて障がいを有する児童や生徒の方々を観客として誘致する施策に取り組んだ。今回、論文コンテストの機会をいただいたので、振り返りをしたい。
この施策の背景には、祭りのテーマへの不合致と吃音障がいがある障がい当事者として障碍者が社会参画しにくい環境への課題があった。前者では、「融和と共生」というテーマがあるものの、障がいがない健常者ではないと参加しにくい仕組みがあった。後者では、自身に吃音障がいがあるが故に苦労した経験がある。障がいを有していると人前に出ることがなんとなく億劫になり、社会と関わることを避けるようになり、孤立する傾向にある。大学で機会格差や経験格差を研究する社会統計学者の端くれとして、それに危機感を抱いていた。この現状を解消するため、障がい者の方々に、祭りを契機として地域に関わってもらう機会を増やすことを目的とした。
そこで我々実行委員会は定量的な目標と定性的な目標を決めた。前者では、10名以上の障がい者を誘致することを定め、後者では、教育機関、行政、実行委員会等の関係者の連携を密にすることを定めた。そして、企画を実行する上では、①関係者との目線合わせ、②実施会場の設営準備に課題があった。前者では、運営上の問題を避けたい故に、障碍者参画に否定的な意見が各関係機関から寄せられることがあった。その不安要素を払拭するために何度も会議を開き、対策を考えてマニュアルを作成した。さらに、企画を周知するために社会福祉施設を通じて、障がいを有する児童・生徒に案内をした。後者では、初めての取り組みである故に、準備の程度が未知数であった。そのため、障碍者用の駐車場を会場の裏口に確保しバスが乗り入れることができるようにし、体調不良の場合に備えて医療資格を有する会場運営ボランティアに緊急事態発生の際の対応を依頼した。
結果的に初年度の取り組みであったものの、10名程度の障がいを有する児童・生徒の方々に参加していただき、祭りの楽しさと地域に関わる面白さを実感してもらうことができた。後日施設の方からお礼の電話をいただき、来年度も引き続き実施してほしいとの嬉しい感想も得ることができた。
この取り組みを通じて私が学んだことは「同じ地域住民という当事者意識」である。障がいというセンシティブな内容に寄り添う際に、我々は一歩引いて身構えてしまう。それは障がいの経験や体験がない人がほとんどであるからであろう。しかしながら、この行動は望ましいものではない。当事者意識というものは、面と向かって向き合うのではなく、横に座ることだと考えている。困っているから何かしてあげようとするのではなく、自身に障がいがあれば如何なる環境であれば参加しやすいか、あるいは参加したいと思うかということを同じ目線で考えることにこそ価値があるのではないか。
私は吃音障がいがある当事者である。小学校時代には自身の学校には吃音障がい用の特別支援学級がなく、他校の学級に通っていた時期がある。吃って注目されるのが怖く、人々の前で何かをするのは未だに苦手である。しかしながら、吃音で悩んだ経験がある私だからこそできることがある。その思い一心で、この企画を成功まで導いた。結果的に、障がいがある児童・生徒の方々に祭りを楽しんでもらうだけでなく、地域に関わる面白さも同時に実感してもらうことに成功した。障がいを持っていると、障がいを持っている人どうしやその周りの方々としか関わる機会がないと言っても過言ではないほど、閉鎖的な環境に陥りがちである。しかしながら、地域社会はそれでは成り立たない。障がいがあろうがなかろうが、共に生きていく必要がある。それに必要なのは、向き合うこと以上に手を繋いで行くことではないか。その思いで、私はこれからも地域に携わり続けたい。
・宮内 正枝 創価高等学校3年 逃げられない子どもたち
結局、社会は何もしてくれない。
私がそう感じたのは、家族の感情面のケアについて一人で悩んでいた時だ。私の家族は障害を抱えていて、私の主なケア内容は話を聞くことだ。愚痴や他愛もない話を聞き、全てを肯定する。自分の意見は飲み込む。体調が悪くてもテスト前でも、関係なくこれをやる。相手の気持ちを理解するのが難しいことも家族の一つの特徴のため、今はやめてほしい、と言うわけにもいかない。伝わらないのだ。ある時は長文のLINEが送られてきたが、支離滅裂でわけが分からない。よく読むと「お願いだから見捨てないで」というようなものだった。振り回されることばかりで毎日クタクタになる。それでも、大切な家族が辛い思いをしているから、ケアをやめることはない。私にとってごく当たり前の日常だ。
家族はなぜこうなってしまったのか。私が悪かったのか。今すぐ逃げ出したい。学校にいてもそればかり考えていた。しかし、いくら考えても解決の糸口は見つからず悲しい現実を突きつけられるばかりだった。
そうしてコロナ禍がやってきた。一日中家族と過ごすようになった。私は眠れなくなった。首を絞められているかのような息苦しさ。得体の知れない体のだるさ。頑張りたいのに勉強に集中できない。声を出す力もなく助けを求められない。学校が再開しても、孤独感や離人感で教室にいるのが辛くなった。保健室と教室を行ったり来たりしながらかろうじて学校には通えていたが、唯一の居場所さえ安心できなくなった。本当に苦しかった。
ここまで追い詰められてはじめて「私はヤングケアラーかもしれない」と思った。もう少し早く大人に頼れていたらどれだけ良かったか。
数年がたち、状況は改善した。今は教室の後ろの席で授業を受け集中して勉強ができている。私が楽になった理由は、ケアを少し手放したからだ。スクールカウンセラーや精神科医と相談をしながら、慎重に、家族と適切な距離を置けるようにした。そうして、私の場合は精神的に安定し体調も格段に良くなった。
「過去と他人は変えられない。 変えられるのは未来と自分自身だ」
かつて精神科医のエリック・バーンはこう言った。ヤングケアラーもそうだ。ケア対象の人はなかなか変わらないし、ケアラーという存在をなくすこともできないだろう。しかし、ケアラー自身は変わることができる。周囲の人がサポートすることもできる。実際に、私を助けたのは学校の先生方だった。先生方はどんなに小さなことでも気軽に相談してほしいと、一対一で、他でもない私に言ってくれた。それは私を尊重し受け入れてくれることを意味した。勇気を持って相談できここから全てが開けていった。
このような経験から私は、ヤングケアラーの孤立化を防ぎたいと思う。そのために、あなたに伝えたいことがある。
子どもたちには、自分を評価せずに受け入れてくれる存在が必要だ。子どもたちがケアのことを人に相談しない理由に、もし家族が知ったら嫌がるだろう、分かってもらえず自分の印象が悪くなったらどうしよう、という不安がある。こうして自ら扉を閉めてしまう子たちを、どうしたら守ることができるのか。それは、扉の外に安全な居場所を作ることではないだろうか。どんな立場の人であれ、その子を一人の人間として見てほしい。一緒に好きな遊びをするだけでも挨拶を欠かさずにするだけでもいい。その子に「いい子」じゃなくてもいい、自分の気持ちを隠さなくても大丈夫、そう言ってほしい。自分のことを見てくれている、と思えることは本当に生きる力になるからだ。そして、誰か助けてほしい、と思った時にあなたがいる、と思われるような存在になっていただけたら嬉しい。
そうは言っても、ヤングケアラーが直面している課題は専門的知識や経験がないと容易には理解できない。本来、医療や福祉が担うべきことをしているため、必要な時には専門家に繋げていただきたいと思う。
幸せになることが人生の目的だとすると、ヤングケアラーやケア対象者はそれを諦めていないだろうか。ケアラーは、この人のせいで思い描いていた人生を送れなくなった、幸せを制限されたと思っていないだろうか。ケア対象者は、ケアラーの人生を変えてしまった、と自分を責めていないだろうか。誰もが自分の幸せを見つけるためには、自分と他人の幸福を心から願えるかどうかだ。あなたは、自分は幸せになる、あの人も幸せになれる、とまっすぐに信じることが出来ているか。信念を持った一人が立ち上がり、やがて増えていった時に、あらゆる差異を超えて心で繋がった理想の人間社会に近づくことが出来るだろう。私たちは、社会問題を論じる前に、自身の心の変革から始めるべきなのだ。そして、私は強く願っている。
ヤングケアラーは誰よりも幸せになってほしい。
・エリ 長野県立大学 3年生 自分と向き合う力
私は日本に生まれながらも外国人である両親のもとで6年間を過ごした。物心ついた時から2つの言語を理解していたけど、両方の言語を正確に話すことが出来なく、あまり両親と意思疎通することが困難だった。
6歳の時に喧嘩ばかりしていた両親が分かれて母と私だけが日本で取り残された。しかし、数ヶ月もしないうちに母と一緒に新しい「お父さん」と住み始めた。父が居なく寂しかった私はすぐに「お父さん」に懐いた。一緒に住んで数か月後、母がいない時にだけ「お父さん」はこれまで知らなかった“お遊び”に誘われ、“遊んだ”後に必ず母にこの“お遊び”について話さないよう何回も念を押された。私は“お遊び”の正体が分からなく、断ったらもう一度数少ない家族を失うのが怖くて母に何も言うことなく、それから何回も母が家にいない時だけ「お父さん」と“遊ぶ”ようになった。
小学校4年生の時、母にブラジルに帰ることを伝えられる。渡航前日、母にこれ以上秘密を持つのが嫌で「お父さん」がいない時に母に“お遊び”について打ち明けた。何回も詳細を聞かれたけれど、母の形相が酷く私は何も言えずにひたすら泣いた。その後、「お父さん」が家に帰った後に二人は私がいない部屋で一晩中喧嘩をし、翌日何もなかったかのようにブラジルに飛びだった。そして、翌日何ごとも無かったかのように3人揃ってブラジルにある母の実家で住み始めた。
渡航して最初の数ヶ月はポルトガル語を書くことも読むことが出来なく、話すこともあまり出来なかったのでとても苦労した。ブラジルでの初日の授業で教室に入り周りを見渡した時、全員の肌の色、目の色、髪型などの容姿が異なり皆様々な特徴があってとても戸惑った。一方、全員の容姿や国籍を気にせず、楽しく、仲良く過ごしている空間がとても感動的だった。私を快く積極的に接してきたクラスの友達の協力でポルトガル語の上達も早かった。最初の数ヶ月は覚えることも多く大変だったけど、楽しい気持ちの方が勝っていた。
しかし、渡航以降普通に過ごしていた母と「お父さん」が大きな喧嘩をして母と私の家から「お父さん」が居なくなった。後になって知ったけれど、「お父さん」が他の人と浮気をしていたことが母に知られていたらしい。そして、「お父さん」がまた居なくなった数ヶ月後、友達と話していたら話の流れで“お遊び”の正体を知った。その後、自分の身体が気持ち悪いと感じ、母に対しての罪の意識を感じた。まるで母を裏切ったようで自分の全てが汚らわしく思えるようになった。だが周りに迷惑をかけることを嫌う私は今まで以上に勉強に励み、周りに人がいるといはいつも以上に元気な振舞いをした。そのため、私のこころが病んでいることに気づく人はいなかった。
それらと同時に私の性的指向に悩み始めた。両親が同性愛に関して否定的だったため、小さい時から同性愛の内容から遠ざかれていたため、私は同性愛に対して強い差別意識があった。しかし、12歳ごろ「お父さん」とのトラウマもあり男性恐怖症になり男性に全く興味を持つことが出来なかった。一方、女性の人に対して魅力を持ち始め、そんな自分が今まで以上に嫌いになり何回も全てを終わらせようと思った。しかし、周りに弱い自分を他人に見せたくなかったため、“お遊び”のこと、自分の性的指向について誰にも相談せず自分を偽った。
そして、13歳の時、母が私に日本に渡航することを告げる。ブラジルでの滞在は地獄のような日が圧倒的に多かったので、日本に帰れることにとても安心した。しかし、現実はそこまで甘くはなかった。ブラジルで数年間過ごしたことで日本語を忘れてしまい最初から覚え直すことになった。加えて、他の人とは異なる私を苦手と思うクラスメイトが多く、いじめを受けながら一人で日本語を勉強することになった。幸いなことにアニメと出会えたことでアニメや漫画、小説を使いながら日本語を覚えることが出来たと同時に同性愛が悪いことではないと教えてくれた。そして、アニメのおかげで徐々に自分の性的指向をも受け止めることが出来た。
これらの経験の経て分かったことが幾つかある。1つ目は、正しい情報が大事なことであることだ。もし、私が“お遊び”とは何だったのかを知っていたら助けを呼んでいたかもしれない、LGBTQについて知っていたら自分を思い詰めるほどに悩まなかったかもしれない。2つ目は、容姿や年齢、国籍、性的指向、宗教などが異なっていても仲良くなることが出来ることである。そして、異なっているからこそ得られるも沢山あり、これらが異なることで取り残されえることがとても寂しくて切ないことである。私は「取り残されない」「取り残せられる」の両方の経験があるからこそ「取り残されない」社会を作りたいと考えている。私は様々なところが異なっていても全員が仲良く、楽しく協力し合える空間を作ることが最大の夢である。
・須郷 心桜 名取高等学校 3学年 ほんの少しの”勇気”
誰1人取り残さない人”と考えると私は、聴覚障がい者(難聴者)が思い浮かぶ。実際、私の友達に難聴の子がいる。 彼女は生まれつきの難聴と診断されたのだ。その彼女とは中学の時に出会い、クラスメイトになり、それから友達になった。友達と呼べるには、程遠い頃私は彼女との会話で”普通に話す”という事が出来ない事に気が付いた。単純な事だが “手話”での会話が彼女にとって当たり前の事だった。そして私は、彼女と手話で話したい思いで手話を覚えた。ありがたい事にクラスメイトに2人も手話ができる子がいた。正確には彼女の友達である。そのためその子たちとも仲良くなり、友達になった。手話を習うことも”最初は”苦では無かった。私が習ったのは、五十音順の手話だったため、例えば「あ」などの1単語から覚えていった。それから2単語、3単語と徐々に単語数が増えていった。しかし当然のことながら単語数が増えれば増えるほど難しくなっていった。それでも毎日、毎日学校で手話を覚えていくうちに自分も早く覚え、普通に会話したい。と言う気持ちの方が強くなっていった。でもある日、突然私が手話を覚えている事に対して他クラスの人から「偽善者ぶって……」と言う言葉を言われた事もあった。実際、彼女をバカにする人もいた。でもまだ、知らない事を知りたい気持ち、彼女にとって役に立ちたいという想いは果たして”偽善者”なのか、と疑問に思った。私自身、絶対に”偽善者”ではないと確信できる。誰かを助けたいと思うのは人として当たり前の事だと思う。だからこそ私は手話を習い彼女以外の誰かのためにもなるよう一生懸命頑張った。その一生懸命に覚えた甲斐あって今では”普通の会話”が出来るようになった。また手話での会話はとても楽しい。単語を並べ、話す自分自身に対して、”この瞬間が楽しい。”と感じる瞬間があるからだ。さらに、手話が出来るようになると今度は先生から「今の話を手話で通訳して」と頼まれる事もあった。その瞬間、私は人の役に立ててると感じ、嬉しかった。また、学校以外の場所でも手話は人の役になれると思った。例えば、公共の場である。公共の場では学校とは全然違う。そのため公共の場での対応は難しい。学校ではごく1部の限られた人しかいない。さらに同年代の人だ。しかし公共の場では違う。当然ながら年齢層も異なる。さらには人種も違ってくる可能性があるからだ。その公共の場で私が恐れている事がある。それは「雰囲気」である。もし、今助けを必要とする人が目の前に居てもすぐ行動する人は少ないと思う。その理由は「雰囲気」が関係してくると考える。 でも、実際、”雰囲気”だけの問題なのかと疑問を持つ。それでも雰囲気を変える、変えないは私たち一人一人の気遣いで多少の変化はできる。その”雰囲気”が変わった瞬間を私は体験した。ある駅構内での出来事だ。その構内で2人の難聴者の人が”浅草”に行きたいと駅員さんに声で伝えていたが、上手く伝わらず諦めかけた際に、男子大学生っぽい3人組の人たちが「あっちのホームが、浅草行きのホームだよ」と2人が手話で伝え、もう1人がジェスチャーで伝えていた。さらにそのホームまで一緒に行ったのだ。見送り終わった後、難聴者の2人は”笑顔”に変わっていた。その出来事を見た私は、とても嬉しい気持ちになった。自分に対しての行動では無いのに、なぜかホットしたのだ。この一連の流れは”雰囲気”を180度変えたと言っても良いと考える。たとえ、私以外の人がその状況を見ても同じ事を思うだろう。それは「誰1人嫌な思い」をせずに済んだからだ。これは「公共の場」だからこその人を想いやるほんの少しの勇気が行動に移ったからだ。もし行動していなかったら、難聴者の2人は電車乗れなかった。いやまず、ホームに辿りつけなかったかもしれない。でも、その男子大学生が人を想いやる気持ちが行動に繋がったのだと考える。 そして最後の笑顔はその想いが伝わったからだと考える。その反面、誰かがやってくれるから…と動かない人もいる。確かに、自分が行動しなくちゃいけない事は無い。それでもやはり見て見ぬふりはできないだろう。たとえ、「自分は手話が出来るから難聴者の時だけ行動する、だから他は行動しない。」では意味が無い。それは意図せずに”誰かを取り残す”に繋がってしまうからだ。その”誰か”の部分を”誰でも”に”取り残す”の部分を”取り残さない”に変えるだけで世の中は大きく変化すると思う。その”誰でも”=取り残される人はいないに繋げたい。その頃には社会全体が視野を広げ、人を想いやる事が重視されていってほしいと考えている。
・田中 愛梨 神戸大学附属中等教育学校 3年生 相談する難しさ 〜「取り残された」ような孤独感〜
学校で、何十人もの人と一緒に過ごしているのにどこか孤独、ひとりぼっちだと感じたことはあるだろうか。
多くの人が、そう感じたことがあるのではないだろうか。私もそのうちの一人だ。では、なぜそのように感じるのか。それは、悩み事があっても相談しづらい環境があるからだと考える。
私は「誰ひとり取り残さない」というメッセージの意味は、誰もが悩み事を相談できて、頼ることのできる人を持っているという状態をつくることだと考える。しかし現在、これは達成されていない。なぜなら、自分の不安や悩みを打ち明けるのは勇気が必要であり、学生にとってはさらにハードルが高いことだからだ。では、なぜ難しいことなのだろうか。それは、親しい人からどう思われるかを気にしすぎているからだと思う。悩み事を打ち明ける際、「これを話したら、友達はどう思うかな」「心配させたくないし、気をつかわせたくない」などといった気持ちがでてくる。実際に私はそのように感じたし、これらの気持ちは、「悩みについて話したり、メンタルヘルスについて考えたりするのはどことなく恥ずかしい」という考えが原因だと思う。特に十代の心は未熟で、人が自分をどのようにみるかを気にしているうえに、自分の不安を話すにはそのネガティブな気持ちに飛び込まなければならないため、精神的にしんどいかもしれない。しかし、まだ若くて成長途中だからこそ、一人で全てを抱え込むのではなく相談することが大切なのだと思う。私が、自分だけで悩みや不安を乗り越えようとした時には、その事しか考えられなくなり他のやるべきこと、例えば、勉強にもなかなか集中できなかった。けがをしたら処置するのと同じように、心が傷ついたら相談して、解決につなげられると良いと思う。
今までの私の経験から、これからどのような行動をとるかについて考えようと思う。まずは私に悩みがあれば勇気を出して、親しい人に相談しようと思う。先ほど書いたように、相談する際には悲しみに向き合う必要があるが、悩みを打ち明けて思いもしなかったアドバイスをもらったり、自分は少し考えすぎていたことに気づいたりできる方が得られるものは大きい。一度そのような話をすれば、次からも言えるかもしれないし、相談された相手も「私に心を開いてくれている」と感じ、その人の相談もしてくれるようになるかもしれない。そうすれば、二人とも頼れる存在を見つけられたことになる。これは特に学生にとって非常に意味のあることであり、この先も友達でいられそうだという安心感にもつながる。また、親しい人がまだ見つかっていなかったり、友達を作るのが苦手だったりする人はカウンセリングなどに行って、専門家の意見を聞くことができる。親しい人に話すにせよ、カウンセラーに相談するにせよ、大切なのは悩み事を自分の中だけで抱え込みすぎないことだと思う。困っていることがありストレスを感じていると、そのことばかり考えて元気もなくなってしまう。すると自分の殻に閉じこもるためひとりぼっちだと感じて、結局「取り残されている」というように思うのだ。私が友達や大切な人にできそうなことはもう一つある。それは相手が打ち明けてくれた悩み事を優しく聞くことはもちろん、元気がなさそうだと感じたら「おはよう」と声をかけたり、遊びに行こうと誘ったりすることだ。まだ自分の不安の原因を突きとめて話す準備ができていないかもしれないため、なんとなく元気がなさそうなら、一緒にいるだけでも助けになると思う。
私一人だけで「誰ひとり取り残されない」世界を作るのは難しい。しかし、親しい人の気持ちに寄り添って話を聞いたり、元気づけてあげたりすることはできる。それは世界全体から見れば小さなことかもしれないが、その行動で誰かの気持ちを少し明るくすることはできるかもしれない。私が悩んでいた時は視野も狭く、不安で混乱していたため、親しい人が話を聞いてくれたことがすごく助けになり、隣にいてくれるだけで安心感があった。これからは私が、悩みを聞くことを通して、誰かを元気づけて「取り残されている」と感じる人に、居場所があると伝えていきたい。
・曽我 優花 鹿島朝日高等学校2年 包摂的な社会をめざして─ 誰ひとり取り残さないために
社会的包摂(ソーシャル・インクルージョン)とは、社会の中でで標準とされる人だけでなく、全ての存在が排除されず社会に包み込まれるよう援助することである。
社会がこれを達成するには、今ある立場や属性による不均衡や構造的暴力を問題視し、それらを是正するよう粛々と””誰ひとり取り残さない””社会の構造を模索する必要がある。私はこうしたことができる社会を望みたい。
しかし、私は今の日本社会はこの社会的包摂から結構遠い位置にあるように感じている。
私は、現在生まれた時に割り当てられた性別の性同一性(性自認とも言われるが、自認という言葉を含むこの表現はそれを好き勝手に変えられるものかのような印象を与えるため、適切な表現でないと考えられる)を持っておらず、男女の二分・バイナリーに当てはまらないノンバイナリーの性同一性を持って生きている。
ノンバイナリーとしての私は、社会で生きる中でことごとく透明になる。
性的マイノリティとはよく言ったもので、大多数の人は性的マイノリティの当事者ではないので、””自分の周りには他人に恋愛感情を感じる、異性愛者でシスジェンダー(生まれた時に割り当てられた性別と現在の性同一性が一致している人)の男女しかいない。最近よく見聞きするLGBTQは10人だかに1人らしいけど、自分の家族や親戚や友達にはまあいない””と考えているみたいだ。或いは、””そういう人たち””は見た目や印象で分かるくらい特徴的なはずだから、と自分の認識の中で普通に当てはまる印象の相手から、無意識に当事者の可能性をなくしているのかもしれない。そのため私を認識するほぼ全ての人にとって、私は恋愛対象が男性の女性だ。私はその人たちに、ただの一度も自分が女性だとも恋愛対象が男性だとも言っていないのに、そう判断されるのだ。現状の社会では、私は構造的に排除されているということになる。
最近、リプレゼンテーションという言葉を知った。リプレゼンテーションとは、””映画やテレビ番組、広告、ゲームなどのあらゆるメディア表現において、社会を構成する人々の多様性を適切に反映させ、表現の上でマイノリティの公正な描写を目指すこと””を意味する。これは、社会が真に包摂的な社会へと進化する過程を助ける一つの手段である。
リプレゼンテーションが成されていない状態では、表現の中でマイノリティは極端に登場せずいないもの(取るに足らないもの)として扱われたり、登場したとしても特定の属性への偏見を強めるようなステレオタイプを強調された姿で面白おかしく描かれたり、実像を歪められた状態で表現される。このような表現は、世間一般のマイノリティや社会的弱者への誤認識を再生産する。そして、そのように偏ったマイノリティの表現で溢れた社会は、個人のマイノリティへの認識を矮小化させ、取るに足らない存在にされたマイノリティへの差別や排除の継続を助長するだろう。
インターネットやメディアの発達した現代において、個人の社会認識(主観的な世界)を形成するのはもはや実体験だけではない。
社会の至る所に点在する表現の世界で適切にリプレゼンテーションが成されることは、マイノリティが透明になって、笑いものに、除け者にされ、好き勝手掃き捨てられないために、どうしようもなく必要だ。
至る所の表現の中から排除や差別がなくなって、社会の中の多様な人々がいないことにされず適切に表現されるようになっても、実世間の人々の認識の中に実感としての””隣に(普遍的に)いる可能性””はすぐには現れないかもしれない。
それでも、人々の世界観の形成に関わるあらゆるメディア表現におけるリプレゼンテーションが達成され、それらの中でマイノリティや社会的弱者が実像を歪められたりステレオタイプを押し付けられることもなくのびのびと存在できたのなら、それはマイノリティへの偏見と差別意識の生産工場のうちの大きな一つが稼働が停止したのと同義である。それだけで現実に生きるマイノリティの生を阻害していたものは大分取っ払われ、そのことが、社会がマイノリティを包摂しやすい方向へと変遷していく過程を助けるだろう。
最後に…私が社会的包摂を望むのは、私のような性的マイノリティがクローゼットに押し込められず自分としてその場にいられるためだが、包摂するべき対象はマイノリティに限られない。それを望むのは、現状の””女の能力は男よりも劣っている””や””男の弱さや男らしさからの逸脱は許されない””等の呪いを含んだ、積極的に””出来損ない””を作るような構造の排他的な社会は、マジョリティも含めた全ての人を締め付けるし、本当に合理的とは言えないと思うからでもある。誰かを取り残すような社会は、その社会秩序の中でマジョリティになれた人にとっても真にフレンドリーなものとは言い難い。
だからこそ、私は全ての人に開かれた包摂的な社会を望みたい。
・小笠原 彩 南山大学3年 重症心身障がい者の視点から考える「誰ひとり取り残されない社会」とは
私は重症心身障がい児デイサービスセンターでアルバイトをしています。重症心身障がい児とは、児童福祉法上、重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している状態にある児童のことを指します。重症心身障がい児数は全国に約4万3千人いると推定され、近年、更に増加傾向にあると言われています。
皆さんは重症心身障がい者に出会ったことはありますか?この施設でアルバイトをする前、私はテレビやインターネット上でしか彼らの存在を知りませんでした。重症心身障がい児を受け入れる施設が、自分の住む地域にあることさえ、驚きを感じました。
新しいアルバイト先を探していた私は、知り合いの先輩からの紹介で、このデイサービスセンターの見学に行きました。目の前に現れた子供たちは、全員が車椅子に乗っており、約半分が胃ろう等を使用している医療ケア児でした。福祉の知識が一切ない私でさえ、この子たちの障がいが重度で、コミュニケーションをとることが一筋縄ではいかないことは、瞬時に理解しました。「みんなと一緒に遊んであげてね。」と職場の方に言われて、「会話も出来ないのに、どうやって遊ぶの!?」と戸惑いもありましたが、職場のアットホームな雰囲気と職員の優しさに惹かれて、この施設でアルバイトをすることを決めました。
私が働き初めて約1年半。利用者1人ひとりに寄り添う職員の姿や利用者と地域の方との交流から、彼らが社会から取り残されていると感じたことはありません。職員が考えてくれるゲームやイベントを通して、彼らは社会の一員として生きている空間は、とても素敵だと感じます。
ただ、私がそのように感じたからであって、利用者自身がどう思っているかは別の話です。彼らは自分自身だけで、何かアクションを起こすことは出来ません。たとえ、彼らは居心地が悪いと感じても、別の場所に車椅子を押してくれる誰かがいなければ、その場から逃げることは出来ません。
利用者は施設に来所すると、姿勢のケアが行われることがあります。重症心身障がい児は頸部や身体のねじれといった異常姿勢を取ることが多く、その異常姿勢の進行を防ぐためのケアが重要視されているからです。姿勢のケアは、子供の活動の幅を広げ、健康の増進を図れる可能性があります。
しかし、施設や当事者の家族は、そのケアを行う決断を彼らと一緒にしたのでしょうか。姿勢のケアではクッションや保持装置で体勢が決められ、固定されます。体勢が辛くてリハビリ中に泣き出す利用者もいます。あるとき、小学2年生の女の子が髪の毛がグチャグチャの状態で、うつ伏せのような体勢を取らされていました。笑顔がチャーミングポイントの子ですが、そのときは険しい顔で私の方をじっと見ていました。彼らは「NO」を言うことが出来ません。自分だけで、その現状を脱することは不可能です。私たちは彼らの声を聞く努力をする必要がありますが、彼らにとって将来的にプラスになることは、当事者の声に耳を傾けずに、突き進んでしまうことが多いのです。お絵かきをするとき、文字を赤色で描くか青色で描くかは彼らと相談して決めるのに、ケアの話になった途端、誰も彼らの声を聞かなくなってしまうのです。
重症心身障がい者を含め、社会的弱者の人々が社会から取り残されないためには、自分の考えや意見を彼らに押しつけるのではなく、彼らの真の思いに耳を傾けることではないのでしょうか。社会経済活動の選択肢を私たちが彼らに提示し、彼らの表情やわずかな身体の動きから、伝えたい言葉を理解することで、初めて重度障がい者が社会から取り残されていない世界が生まれると考えます。
将来の彼らのためを思って行うケアや支援は、施設や利用者の家族の自己満足になってしまう場面もあると思います。しかし、その行動はかえって当事者の気持ちを見捨てている可能性があります。人にはそれぞれペースがあります。障がいがあっても、私たちが当事者の思いやペースに寄り添うことが出来れば、その方は社会の一員になっているはずです。無理に健常者の考える「社会」に参入する必要はないのです。
「誰ひとり取り残されない社会」が、誰かの理想だけで完結しないように。100人いれば100通りの、1000人いれば1000通りの「誰一人取り残されない社会」の考え方があるはずです。
・西山 心雪 四谷インターナショナルスクール 2年 自分を愛すること
中学校3年の頃、私は今後の人生の価値観に大きく影響をもたらした病気、拒食症にかかりました。きっかけは受験勉強に対するストレスからでした。私は当時、どうしても入りたい志望校がありました。その学校はいわゆる難関校で、英語教育が盛んな学校でした。もともと勉強嫌いだった私でしたが、英語だけは大好きでその学校で英語を学んで話せるようになりたいと思っていました。難関校ではありましたが、努力をすれば受かるかもしれないと信じて大好きだった趣味のボルダリングもやめて友達とも遊ばず勉強に励みました。身に異変を感じたのはその年の夏休み頃。塾から帰ってきて夜ご飯を食べると、毎日のように胃が痛くなりました。最初は気にしないようにしていたものの、段々とご飯を食べることが怖くなりました。それから少しずつ食事の量が減り大好きだった学校の給食もほとんど食べずに残すようになりました。体重は半年ほどで17kg落ち学校へ行くことも勉強もできず全てのやる気と自己肯定感を失い、「勉強しなくていいや」という気持ちと「何も出来ない自分が醜い」という気持ちが自分の中でぶつかり合っていました。その後受験はなんとか無事に終わりましたが第一志望の学校は落ちてしまい、より一層自分自身を責めるようになりました。しかし悪夢はまだ続きます。4月からは第二志望の高校へ進学が決まりましたが、このままでは通学できる体重ではないため受験が終わりすぐに入院しました。5kg体重が増えれば退院と主治医から告げられ始まった入院生活。カロリー消費しないため寝たきり、携帯禁止、トイレまで歩くのも禁止のためトイレはベッド横にポータブルトイレを置かれました。今思えばこれらは思春期の女の子に取る処置として最適なものではないと思います。親にも友達にも会えず大きな部屋にポツンと1人。病室で孤独感、そして自分の惨めさに毎日涙を流しました。結局ほとんど体重は増えず精神の限界を迎え、主治医に交渉し退院しました。春が来て、ガリガリの体で新しい制服を着て高校へ入学しました。しかし細く痩せた痛々しい足では階段も登れません。またこの頃になると脳に栄養が行きとどいておらず、情緒が不安定で毎日泣いていました。そして入学した高校はほとんど通うことができず、夏休み明けに自主退学し通信制高校へ転校しました。それからは毎日家で1人通信制高校の課題をする毎日。英語が話したいという夢もどこか遠のいて、人生を諦めている自分がいました。
しかし母はそんな私を連れて楽しい場所にたくさん連れ出してくれました。正直低体重の私を連れるのは罪悪感や心配もあったでしょう。それでも私を楽しませてくれ、人生は楽しいものだと思わせてくれました。それが私の拒食症生活の転機となりました。私は人生やり直さなくてはならないと思いご飯を食べ、体重を少しずつ戻し高校2年の4月からインターナショナルスクールへ転校することになりました。そこではたくさんの友達に囲まれ、大好きな英語に毎日触れることができています。
そんな私が女の子に伝えたいことがあります。それはいつだって自信に満ち溢れて欲しいということ。どんなあなたもいつだって美しいのです。体型や得意なことは人それぞれ違うけれど、自分自身の個性を大切にしてください。
そして今拒食症で悩んでいる方へ。あなたは1人ではありません。周りを頼って、自分を大切にしてあげてください。そして自分のやりたいこと、楽しいと思えることを見つけて人生を楽しんでください。自分を愛して、褒めてあげてください。
一度きりの人生を心から楽しんでください。
優秀作品賞<小論文部門>
・森田 菜那 立命館大学国際関係学部2回(2023年度末まで休学) 「あなたは今、幸せですか。夢はありますか。」
心の中で問うてみてください。「あなたは今、幸せですか。夢はありますか。」
「いいえ。」と答えたあなたを私は取り残したくないのです。
私は「誰ひとり残さず、今この時を幸せだと感じ、夢抱いて生きる世界」を作りたい。
もちろん、ひとの幸せを阻害して自分の幸せを掴むことは許されません。しかし、そうでない場合、周囲の人からどう思われても自分が幸せだと感じていたら良いのです。いつ、どうしたら叶うのか分からない大きな夢、今すぐにでも叶いそうな小さな夢、夢にも様々な大きさがあります。どんな夢でも良いのです。その夢を叶えた時、またはその夢が叶う瞬間を思い描いて突っ走る時、ひとは幸せを感じるでしょう。そこで、私は「夢」は「向上心」であり、「未来の幸せへの原動力」となると考えました。
「“今”の幸せと“未来”の幸せを誰ひとり残さずに掴み続けられる世界」、それこそがSDGsの根本目標である、Transforming our worldの達成ではないでしょうか。
私は幼少期からセーブ・ザ・チルドレンの活動に触れ、世界には一時的欲求を満たすこと、安心安全で安定した衣食住を確保することが難しい人がいるということを学んできた。その影響で、いかにしてこの世界を「世界中の人々が幸せに生きられる世界」にするか、今の世界に足りないものは何かを多角的かつ深く学びたいと思い、大学では国際関係学を専攻している。大学1回の夏、私はフィリピン・セブ島にあるスラムに住む大学生とオンライン交流会で出会った。彼女に出会うまで、私はセブ島にスラムがあることを知らなかった。家は中国人の墓地、不法だと知りながら暮らしている、いつ強制移住させられるか分からないなど、彼女からの一言ひと言は私の想像を絶するものであった。しかし、彼女はそれを私に笑顔で話したのだ。私は彼女から出る言葉と表情のギャップがとても印象に残り、セブ島について詳しく学ぼうを決心した。そこで、私は半年間大学を休学し、セブ島に渡航してきた。私はこのエッセイをセブ島から執筆しているのだ。
セブに着いた日、車窓をノックするストリートチルドレン、砂ぼこり、沢山の野良犬、道路脇のゴミ、またローカルエリアと綺麗な高層ビル群のコントラストなど、五感で感じた全てのものが刺激的であった。そのため、セブに来て数日間は日本とのギャップに苦しんだ。日本の整ったインフラや衛生環境が恋しく、あの時の感情はジャパン・シックという言葉がぴったりだろう。日本では当たり前のものとして享受していたものがセブにはなく、逆にセブにあるものは全て日本でも手に入ると思い込んでいた。
しかし、セブでの暮らしに順応していく中で、またフィリピン人と話していく中で私は2つの大きなことに気が付いたのである。それはフィリピン人の多くが「今を幸せだと感じながらも、夢を抱いている」ということ、そして気付かぬうちに彼らに元気付けられていたということだ。健康であること、家族や友達がいること、気持ちの良い天気に幸せを感じ、海外旅行すること、家族にクリスマスプレゼントを買うこと、スターバックスに行くことを夢見る。幸せの基準、夢の大きさを人と比べていないことがとても印象的であった。
セブに移住した日本人の友人に「日本に一時帰国すると、やっぱり日本が最高だって思うのに、セブに帰ってくるとなぜか元気が出てくるんだよね。」と言われた。セブに来たばかりの時はこの言葉を理解できなかっただろうが、今となっては共感できる。幸せそうに生きているその雰囲気が、どことなく私たちに元気を与えているのだろう。
ゴミ処理システムが整っておらず道路にゴミが溢れかえっている。交通渋滞や事故は日常茶飯事で、車の排気ガスは目に見えて黒い。また、スラム街では法整備が難しく、今なお薬物が出回っている。たしかに、フィリピンはゴミ問題、排気ガス問題、スラム問題などSDGs達成のために解決しなければならない課題が多く残っている。しかし人々は夫々に抱く夢を叶えるため、この現状に変革をもたらそうと全力を尽くしている。なぜなら夢は「向上心」であり、「未来の幸せへの原動力」だからである。
私は再度、みなさんに問いたい。
「あなたは今、幸せですか。夢はありますか。」
私はフィリピン人の友人と「幸せ」について語っていた時、彼女にこう言われた。
「日本人ってよく『将来のために』って言うよね。なのに、夢を持っている人は少ない気がする。誰でも夢見ていいのに。」
私はこの言葉にはっとさせられた。「今この時を幸せだと感じ、夢を抱いて生きる世界」から取り残されているのは「いいえ。」と答えたあなたではないだろうか。日々の小さな幸せを噛みしめ、夫々の夢を追いかける。この簡単そうで難しく、難しそうで簡単なこの2つのことが私たちの心、そして世界を豊かにしていくのだろう。
「誰ひとり残さず、今この時を幸せに感じ、夢を抱いて生きる世界」を私は作りたい。
・二宮 百可 愛知学院大学4年 多面体を愛すること
誰一人取り残さない。たまたまSNS上で見た本大会の広告が忘れられず、誰一人取り残さない社会とは何か、一人で模索しました。誰一人取り残さない、どこから?今取り残さている人々とは?しかし明確な答えは見つかりませんでした。私はふと、自らに目を向け、今まで生きてきた22年間を振り返りました。そしてあることに気が付きました。私自身、周囲から取り残されないように、貧困という面を必死に隠して生きてきた、ということです。
私の家にはいつもお金がありませんでした。父が病気がちで母はパート勤務、生活はいつも苦しく、私の服は従姉妹から譲り受けていました。部活動でも公式の練習着を買うことができず、似た色合いの安価なものを着用していました。貧困家庭のかわいそうな子、という印象を受けるかもしれません。しかし、このような貧困状態は私にとって辛くはありませんでした。もっと辛かったのは、貧困という面を隠さなければならなかったということです。幼いころから、私はかわいそうな子と思われることで、周囲から孤立してしまうのではないかという恐怖がありました。だから私は自分の持ち物はできるだけ綺麗なものを、さらに言動にも気を使い、貧困状態を隠すことにいつも必死でした。
そんな中、貧困を隠す、ということ自体に疑問を抱いたある出来事がありました。それは、私が大学時代に出会った友人からの告白でした。彼女は明るく、人気者の女子大生で、大学時代にできた私の親友でした。そんな彼女と二人で話したとき、彼女から突然ある悩みを打ち明けられました。「私、小学生の頃、親族から性被害を受けていたんだ。」そう明るく話す彼女の話は衝撃でした。内容もさることながら、もっとも衝撃だったのはこの悩みを私以外、他の親族にも話したことが無い、ということでした。なぜかと理由を聞くと、「家族関係を壊すことが怖かったから。」と言いました。私は言葉が出ませんでした。そして、彼女は「当時の被害も辛かったけれど、それよりも今、家族にも話せていない状況の方が辛い。」と続けました。
私はその時、一つの大きな疑問が浮かびました。それは、なぜ、私たちは隠さなければならないのか、ということです。私は貧困状態を隠し、彼女は性被害を隠して生きてきた。本来なら周囲に助けを求めていいはずの悩みを必死に隠さなければならなかったのは、なぜでしょうか。
人間は多面体である、と思います。人間を形成する多くの面には、強さや魅力という面、中には目を覆いたくなるような過去や、弱さの面もあります。人々はそれらの面を主張したり、隠したりしながら生きていることが現状です。私も彼女も、周囲から取り残されることを恐れ、被害や貧困を隠して生きてきました。その結果、多くの不安や孤独を抱えたまま、大人になりました。周囲から取り残されないよう、弱さを隠して生きる社会は、本当に誰一人取り残されていない社会と言えるのでしょうか。
私が最初、誰一人取り残さない社会について考えたとき、明確なビジョンが浮かびませんでした。それは、私や彼女のように、いまだ多くの人が自らの弱さを隠しているからかもしれません。人の弱さに触れたとき、周囲がそれを無理に解決しようとしなくてもいい。その面がある、ということを受け止めることが大切だと思います。そして、その面もその人であると認め、さらに寄り添うことができれば、どんな面の自分でも受け止めてもらえるのだという信頼のおける社会を築くことができると考えます。そうした社会こそ、本当の意味での誰一人取り残さない社会であると私は思います。
私は4月から地域の社会福祉協議会に就職します。職員としての使命である地域福祉の活性化に努め、多くの機関と連携し、寄り添い合える社会づくりを目指します。そして将来、自らの弱い面を見せることを、もう決して誰も恐れることのない、暖かい社会づくりを目指したいと考えます。
・勝山 愛菜 会社員(IT業界) 多様性を問う
もし、2030年が誰一人取り残さないことを実現した素晴らしい世界だとしたら、その世界は「取り残されたかった人」にとっても素晴らしい世界なのだろうか。
4・5年前から耳にするようになったSDGsという言葉は、「協力」とか「思いやり」とかと同じように無条件で良い印象を抱かせる言葉になってきている。SDGsが「誰一人取り残さない」という基本理念を掲げていて、目標とターゲットに「あらゆる~」「すべての~」など仲間外れを生み出さないための文言が沢山使われているのも理由の一つかもしれない。2030年というタイムリミットを決めて、地球環境を改善するためにゴミの削減や生態系の保全活動を行ったり、多様性を認めようと声掛けしたりするのは誰から見ても良い行いに見えるだろう。悪いことだったら、SDGsへの取り組みは世界中に広がっていないだろう。
貧困も障害の有無もセクシャルマイノリティも、SDGsは取り残さないで受け入れようとしているが、一つ忘れている立場がある。それは、「取り残して欲しい人」の意見だ。
「取り残さない」とは、一つも残さずにすべてを他の場所に移動するということだ。つまり、SDGsは現在から持続可能で多様性のある2030年に人類みんなで移動しようという目標ということになる。SDGsはみんなが2030年に行きたいと思っていることが前提になっている。そのため、放っておいて欲しい人は存在しないことになっている。SDGsが目指す世界が魅力的に感じる人は、そっちの世界に喜んで移動するから問題ないだろう。しかし、全員ということは移動したくない人も移動しなくてはならない。現在から変化することが嫌な人の「移動したくない」という気持ちはどうなるのだろうか。
移動するのが嫌な人なんて本当に存在するのかと疑問に思う人もいるかもしれないが、私はそうゆう思いを抱いている人の存在を知っている。
例えば、「名前のないマイノリティ」のままでいたい人だ。ここ数年で、私たちの世界はセクシャルマイノリティへの認知度が高くなってきている。LGBTQがどんなセクシャリティを指すのかすべてわかる人も多いだろう。セクシャルマイノリティの一つに、誰にも恋愛感情や性的欲求を抱かないアセクシャルという性がある。アセクシャルの人は少し前なら、「恋愛をしない人だ」とか「結婚願望がない人だ」とか言われるだけで、マジョリティのなかの少し変わった人と見られるだけだった。マジョリティの人が向けるマイノリティの人への理解がありますという視線と、「あなたのことを理解したい」という善良な思いからくる遠慮のない質問を受けずにいられた。しかし、「あなたはアセクシャルというマイノリティですよ」とラベルが貼られたことで、マジョリティではいられなくなってしまった。アセクシャルに限らず、同じような思いを抱いている人や、これから見つかってラベリングされてマイノリティになってしまうことに恐怖を感じている人もいるかもしれない。
他にも、持続可能な世界を願っていない人もいる。みんなが未来のために環境のことを大切にしようと言うけれど、2030年というよくわからない未来のことより自分が生きている今だけを考えて生きたいと思う人もいるだろう。そういう人にとって今の社会は、自分は太く短く生きたいのに、それが出来なくて、窮屈で生きづらく感じてるのかもしれない。
私たちが生きる今は、一人一人の個性を尊重してそれを共有する「多様性の時代」だと言われている。人と違う対象に恋愛感情や性的欲求を持っていても、障害があっても、宗教や思想が人と違っても、どれも個性として受け入れられて、違うことは素晴らしいことだという結論になる。でも、多様性はどこまで許されるのだろうか。「取り残して欲しい」という立場の人は存在することを許されているのだろうか。
もし、多様性に制限があるとはするのなら、それは花壇に勝手に生えてきた花を邪魔だからと言って引っこ抜いた後の花壇を見て、「どれも違う色や形をしていて綺麗だね」と言っているようなものだ。名前が良くわからないものや存在を認めないものを排除した花壇は、はたして「多様性がある」と言えるのだろうか。
私は、このままでは2030年は整えられた花壇と同じ世界になると思っている。なぜなら、SDGsの仕組みの解説と企業や教育現場などのSDGsの取り組みはテレビで取り上げられているのをよく見るのに、否定派の意見や取り残して欲しい人の意見を紹介しているのは見たことがないからだ。SDGsに取り組むことで救われる人が沢山いるのは事実だが、その裏で消えそうになる多様性もあるのも事実だ。
取り残したくない人と取り残して欲しい人が、どうしたらわかりあえるのか、私にもわからない。ただ、2030年までの残りの6年の間に移動していく人が、たまに後ろを振り返って「取り残して欲しい人」の存在を忘れないでくれれば良いと思う。少しでも多くの多様性が未来に残ることを願う。
・坂元 隼斗 早稲田大学3年 みんなと違うという価値
「よお,精神病患者(笑)」
これは私が抑うつ状態を呈していた高校時代に,一人の同級生に投げかけられた一言だった。怒りも悲しみも感じることはなかった。ただ,この言葉をかけてきた,この一人の人間と,一生の関係を断ち切ろう,そう決意した。この経験は今の私を精力的に突き動かす原動力になった。このときから,大学で心理学を学ぶことを志し,今では大学で心理学を専攻し,研究者を目指して大学院に進学するために必死に心理学を学んでいる。私はこの場を借りて,文章として,言葉を通して,社会に訴えたいこと,多くの人に知ってほしいことがたくさんある。それは私自身のためであって,大切な家族のためであって,私を支えてくれる人全員のためであって,同じように苦しみを感じている人のためである。誰ひとり取り残されることがあってはならないためである。世界の全員が幸せになるためである。
私は双極症と呼ばれる,約1%が発症する,気分障害に分類される精神疾患を患っている。今の日本社会では,数多く見られるメジャーな精神疾患であろう。気分障害に限らず,若者をはじめ,中年層や高齢者,幅広い年代で精神疾患,精神障害は困難な問題となっているが,その数は年々増加し続けており,心理的支援の必要性は声高に叫ばれ,精神医学,臨床心理学のさらなる発展が急がれている。
では,精神疾患,精神障害を抱える人が持つ特有の心的世界を想像することはできるだろうか。本当は好きなはずものが好きでなくなる感情の喪失,頭の中に鉄球が入っているかのようにずっしりと長引く頭痛,まるで魂が抜けたかのような虚無感,そうかと思えば生じ始める異常なまでの優越感や有能感,斬新なアイデアが無限に溢れ出る想像力。このような感覚は,風邪やインフルエンザなどでは味わいようがない体験なのである。これらは当事者でなければ非常に想像が難しいだろう。というより,当事者にとっても想像を絶する世界であるのだ。言い換えるならば,この経験は当事者にしか掴みようがない体験なのである。しかし,嫌なことばかりではない。他者の心的世界の苦しみを,いくらか解像度の高い方法で想像することが出来るようになった,私の唯一のきっかけでもあるのだ。この世のものの多くに二面性が存在するように,精神疾患や精神障害もまた二面性が存在する。
しかしどうだろう。世の中には何故だか,精神疾患を患っていることをただただ悪く捉えるような人が一定数いるようだ。「あいつはメンタルが弱いから」だとか「根性が足りない」だとか,精神疾患に限らずとも,不必要な根性論に言いくるめられた経験はないだろうか。私にはそれがどうもおかしく思える。なぜ心の弱さを引き合いに出すのだろうか。この疑問を踏まえた上で,「精神疾患は心の病気だ」という文言に違和感はないだろうか。私には違和感しかない。「精神疾患は脳の病気だ」という認識の方が正しいように感じられる。心とは何かを考えたとき,答えはまだ誰にもわからない。しかしながら,心というものは,実体はない,脳という器官が生み出す機能の一つ,ではなかろうかと考えるのだ。実体なきものに,病の原因を求めるだろうか。実体なきものに弱さを考えることはできるだろうか。それでは果たして,心の病気という表現は適切なのだろうか。考えてみてほしい。
人が病気を患うこと,それは健康な人とは異なることで,ある種の区別が行われることになる。しかし,その区別は,差別になってはならない。人と違うことを責めるようなことは絶対にあってはならない。風邪を引けば休養を取るように,骨折をすれば仕事を控えるように,目には見えないけれど,精神疾患も回復の時間と心身の余裕を要するのである。
将来,私は認知神経心理学者とデータサイエンティストになりたい。そして,精神疾患や高次脳機能障害のメカニズム解明を目指すとともに,精神疾患や精神障害に対する差別意識や偏見を根絶したい。また,DXやITに強い心理の専門家として,データに基づき,日本社会における非合理的,不合理な社会制度や社会構造そのものに変革をもたらしたい。比較的軽度な症状で,少しでも当事者の気持ちを拾い上げて,声をあげることが出来る私が,メンタルヘルスへの誤解に立ち向かわなければならない。正しい知識を,当事者だけでない,幅広い人たちに届けなければならない。メンタルヘルスの正しい知識は,常識のように人々に備わらなければならない。なぜなら誰もが精神的な不調を味わい得るからだ。もちろん,今,健康なあなたも例外ではないのだから。
最後に,みんなと違うということは悪いことではないと信じている。むしろ,みんなと違うからこそ,私には価値があると信じている。この先もずっと自分らしさを誇りに強く闘って生きて,多くの人が自分らしさを大切に生きられる社会を実現すると心に決めた。
・能登 杏奈 聖路加国際大学大学院1年生 普通という価値観で取り残したり取り残されたりしていませんか?
私は、目に見えない障害がある。突然、痙攣をおこし失神してしまう。前兆はない。自分にとっても突然である。しかし、発作が起きない限りは何不自由なく日常生活を送ることができる。だから障害のことは誰にも言っていない。私が取り残されてしまうと思うからである。家族しか知らない。一度、友人の前で発作を起こしてしまったことがある。元気そうに見えていた人が突然、目の前で痙攣を起こし倒れていたら心配してしまうのは仕方のないことである。しかし、風邪をひいたときや少し挫いたときでも過剰に心配をかけてしまうようになった。その心配が日常生活の不自由さに感じてしまった。心配してくれる友人がいるだけで幸せなことなのかもしれないけど。私に対する対応が他の友人への対応とは異なることに取り残されていると感じてしまった。
その障害の影響でお酒を飲むことができない。他人にとっては小さなことでも私にとっては大きなことである。この少しのできないが取り残されていると感じることの1つである。大学生になってお酒を飲めないことがコンプレックスとなった。20歳を超えた大学生は、サークルやバイトなど事あるごとに飲み会が行われる。飲み会に行ってもお酒を飲むことができない。少しも飲むことができない私は気遣われ、心理的に取り残されてしまう。また、飲み会に誘われないことやお酒を飲めないなら会いたくないと言われることで物理的にも取り残されてしまう。そんな人とは、仲良くしなければいいと簡単に言えるかもしれないが、仲良くなる以前にその一言で孤立感を感じてしまうのである。もし、私がお酒を飲めたら、もっと仲良くなれる友人が増えたのではないかと考えてしまう。お酒を飲めないことが悪いのではないかと思ってしまう。
そんなことを考えていると、普通とは何なのか疑問に思う。誰かの普通にできていることは誰かの普通にできないことかもしれない。誰かの普通が誰かの普通ではないことなんていっぱいある。普通は自分のルールや基準でしかないだろう。私の普通はあなたの普通ではない。あなたの普通も私の普通ではないことを忘れてはいけない。普通は常識ではない。意味が異なる。普通という価値観は自分の中にとどめておくものであると思う。誰かの普通を誰かに当てはめることで誰かが取り残されてしまう。誰かの普通で自分が取り残される可能性もある。誰も取り残されない社会にしていくためには、みんなが誰かの普通という基準で誰かが取り残されてしまうことを理解していかなければならないと私は思う。自分の普通を相手の普通だと思ってはいけない。
・小段 杏 創価大学文学部人間学科1年 ひとり親世帯の子どもとして生きてきて、感じること
私は3歳から母子家庭で育ちました。そのため物心ついた時には、家に父親という存在はいませんでした。兄弟もおらず、親戚とも離れて暮らしていたため、ハロウィンやクリスマス、誕生日などのイベントはいつも母と二人きりで、私にとってはそれが当たり前の光景でした。そんな日々を送っていた最中、小学4年生の時に二分の一成人式という学校内でのイベントがありました。そこで「お父さんとお母さんにメッセージを書きましょう。」という宿題が出ました。私はその時に非常に困ったのと同時に、周りの友達にお父さんという存在が当たり前に存在していることを実感しました。もちろん、私は母にだけメッセージを書いたのですが、やはり周りの友達からは、とても不思議がられました。それから中・高では「かわいそう」という言葉を浴びました。私は「かわいそう」という言葉が苦手です。なぜなら、その言葉の裏には相手が悲しい人だと決めつけていることを暗示しているからです。父親がいなくなることに抵抗する暇もなく、その状態で過ごしてきた私にとって、今の状態が最大限の幸せであり、不満などない日々を過ごしているつもりでしたが、友達からの「かわいそう」という言葉で、私は母に対して、なんで離婚したのかという気持ちが徐々に芽生え始め、母と何気ない喧嘩をするたびにその話題が出るようになりました。このように、ひとり親世帯で育っている私にとって普通の状態でも、周りの家庭から見たら異常な光景であることを実感する日々を送りました。
私がひとり親世帯の子どもとして育ってきて感じることは、ひとり親世帯の子どもは親に迷惑をかけてはいけないと思う子どもが多いのではないかと思います。例えば、クリスマスプレゼントを自分がひとり親世帯の子どもだと認識する前はよく母にねだっていましたが、自分がひとり親世帯の子どもであり、自分の家庭は他の両親がいる家庭よりも金銭的に余裕がないと認識しだした時から、母にクリスマスプレゼントを尋ねられても、「いらないよ、大丈夫」と言うようになりました。ここで、親子間での遠慮が生まれました。私はそれが非常に悲しいことでした。母を困らせたくないという子どもなりの配慮と、せめてクリスマスプレゼントだけは…という母の気持ちがすれ違ってしまいました。
私はひとり親世帯の援助を、お金だけでなく、気持ちの面でも救ってほしいと思います。少なくとも私の家庭では、精神面でのサポートがなかったなと感じています。もしかしたら私はド田舎で生まれ育ったので、その地域まで支援が行き届いていなかったのかもしれません。私は小学6年生の時に地元である福岡県から神奈川県に引っ越してきました。ド田舎での暮らしと都会の暮らしをどちらも体験し、私が実感することは、ド田舎のひとり親世帯と都会のひとり親世帯では、生きづらさが圧倒的に違うところです。ド田舎でのひとり親世帯は「うちの家庭は」というように、自分たちから社会というコミュニティから排除されようとしてしまう傾向があるなと感じます。一方で都会での暮らしは、他のひとり親世帯の家庭の事情を知る機会があったり、相談窓口なども設けられていました。ド田舎ではそのような機会はなく、支援してくれるのはいつも金銭面のみでした。
私は、ひとり親世帯だからと言って特別扱いするのではなく、両親がいる子どもと同等の扱いを受けたかったです。近隣の方から自分を大切に思ってくれていると実感したり、地域の方々から「自分の子どものように思っている」と言っていただいた時は涙が出ました。そういう気持ちを全ひとり親世帯の子どもに体験して欲しいなと思います。自分が所属しているコミュニティ、居場所を見つけてあげ、無理に寄り添うと思わなくても良いのではないかと思います。自分が誰かに大切にされている、頑張っていこうと思える気持ちを芽生えさせてくれる人、場所があれば良いなと思います。実際に私自身も、母の友人の叔母さんがとても親切にしてくださり、私にいつも居場所を与えて下さっていました。
今や、SDGsの取り組みは世界的にも重要視されており、私も大学の授業で学び、これから私たちに出来ることは何なのかなどの対策を考えているのですが、規模が大きい目標だなといつも思います。未来の問題を解決することもとても大切なことだと思うのですが、今、目の前で困っている人、「たすけて」の4文字が言えない人や環境があることにも目を向け、私も含め、そういう身近な問題を解決することが、日本という国をもっと良くし、特にひとり親世帯が年々増加している分、精神面でサポートする内容を改める必要があるのではないかと感じました。
・天野 結菜 刈谷北高校2年 助け合いの花がだんだん大きく広がりますように
「誰一人取り残さない」は解決することが難しい問題だ。
このような問題提議をすると障がい者や、外国人のことを取り残さないようにしようと想像する人がほとんどだ。
しかし、取り残されている人はもっと身近な人にもいるはずである。
身の回りのことに目を向けていると、点字ブロックや、音が出る信号機や、さまざまな言語で書かれた看板などが見られる。
これは私たちはハンデがある人のことを特別扱いして考えて行動に移そうとしている世の中になりつつあるということだ。
ではそのような人ではない私たちはどうか。
困ることはないけれど生きにくいと感じることはあるはずだ。
ここで一つ例を挙げる。
学校で席替えをする。
もし、先生が自由に決めていいと指示したらどんな問題が起こると想定されるか。
例えば2ペアが作れずに最後まで残ってしまう人。
もしくは友達はいるのに奇数のため残ってしまう人。
それを防ぐために先生が決めたり、くじを引いたりして決めることが一般的だ。
この方法は「誰一人取り残さない」を解決する方法だ。
しかし生徒は一人も残さないから自由がいいと言うのだ。
そのため自由にさせる。
だがうまく決まらない。
しかしこの問題の解決案は簡単だ。
このような決め方をしなければ良いからだ。
全員が過ごしやすくするための最善の方法だといい、自由をなくせばいいだけだ。
しかしここでさらに問題が生まれるのだ。
それがルールで縛り付けられた固定概念だ。
さらにそれが差別につながり、誰かを取り残すことにつながるのだ。
表裏一体している自由とルールがこの問題を生み出しているのだ。
だがもう一度根本を見直してみると、これは自己中心的な行動をとった場合のことだ。
もし相手を思いやり1人になる人がいなければその仕方ないため作られたルールというものは必要でない。
つまりこの問題の解決策は思いやりを持つことだ。
しかしこれが一番難しいことだ。
なぜなら人間は自分を犠牲にしてまで他の人に尽くすことをすることはできないからだ。
今の世の中に必要なことは相手の良さに気づき助け合いで溢れる社会にすることだ。
そして相手を自分と同じように大切い思う人になれば助けようと行動する人も増えるはずだ。
そして助けられた人が他の人を助ける。
その助け合いで繋がった円が全員を過ごしやすくするのだ。
「誰1人として取り残されない」社会になるのだ。
ここで大切なことは1人が始めることだ。
私がその1人目だ。
その人の良さに気づき、認め、尊重することである。
この小さな花がだんだん大きなものに成長し、生きやすい世の中になることがこの問題の解決策である。
・高沢 莉菜 宮城県名取高等学校3年 「分からなさ」を超えていくために。
皆さんは、多発性硬化症という病気を聞いたことがあるだろうか。多発性硬化症は通称、MSとも呼ばれ、症状が神経に生じる病気の為、他人の目からは気付きにくい事が多い。また、現在の医療では完治させることのできない難病のひとつとされている。以前私は、この病気に関する中外製薬のショート動画を偶然目にした事がある。「分からなさを、超えていこう。」このスローガンがすごく印象的だった。
突然目に違和感を感じた母親が病院へ行くと多発性硬化症と診断され、子供の授業参観の日に、偶然母親が車椅子で階段を登るのを補助されている姿を目にした息子が「卒業式来なくていいからね…」と言った。その母親のどこか悲しむような、わだかまりが残るような表情が強く脳裏に焼き付いている。もし、この病気と共に自分以外の家族、大切な友達が闘っていることを知らずに、心無い言葉をかけてしまったらと想像してみてほしい。それぞれどんな場面が想像できただろうか。私は、事実を知らないことばかりにかけてしまった言葉に対し謝ると、友達から「気にしなくて大丈夫だよ。この病気理解してもらえないこと多いから。」と、切なそうにしている姿がイメージできた。確かに多発性硬化症は目に見えづらく、どんな病気かは周囲へと伝わりづらい。しかし、分からないことを分からないままにしたのではいつまでも
「分からないから」の壁を越えることはできないだろう。「分からないことの壁を越える人生」と「壁の中で生きる人生」貴方にとってどっちが輝いていると感じるだろうか。多発性硬化症に限らず、病気の症状が目に見えることばかりではない。表面上では普通に見えるが、実はどこかで我慢していたり理解してもらえない辛さを感じて生きる患者だって少なくはない。周りに理解してもらえないことが原因で、苦しい時でも言い出せず、無理をしてしまい症状の悪化に繋がる場合だってあるのだ。このように、他人の目からは気づきにくい病気を抱えて生きる患者が一定数いるという現状を一人でも多くの人に覚えておいてもらいたい。私は、分からなさの壁と闘う病気を抱えた患者が学校生活を送ったり、社会で働いたりする中で病気に対する理解と必要な補助についての必要性を伝えたい。病気を抱えて生きる患者が社会生活の中で我慢するのではなく、周囲が分からなさを越えることで、今まで周囲へと病気である事を隠してきた人たちの打ち明けるきっかけへと繋がる。
また、今まであまり認知されていなかった病気についても理解が深まったりするのだ。このように、「わからなさ」はコミュニケーションのスタートなのだ。私も偶然このショート動画に出会っていなかったら、多発性硬化症という病気を耳にしたことがなかったし、こうしてより多くの人に知って貰おうとも思っていなかったかもしれないから。知らないことが多いまま、ただ病気として単純に捉えていたかもしれない。わからないことは決して恥ずかしいことではない。だからこそ、「わからない」事から、「わかる事」へと変えるためにコミュニケーションを取るべきだと私はこのショート動画に出会ってから改めて感じた。難病を抱える人だけでなく、治せる病気を患う人でも周囲に私はこんな病気を患っている。時に助けが必要な時がある。だから、力を貸してほしいと言える大きなチャンスにもなるのだ。
確かに、多発性硬化症のような目に見えにくい病気を抱える人が自身の病気を公表する事でより多くの人に病気のことについて知ってもらうきっかけ作りができたらいいなと思う。中外製薬の掲げる「分からなさを、超えていこう。」を実現するためにも、私たちの見えない場所で不安と戦い闘病を続ける難病患者だけでなく、治療をすることで完治できる病気でも打ち明けやすい環境作りを心がけていきたい。中学生だから、高校生だから、子供だからと年齢を決めずにできる事を見つけ、その年齢にしかできない事や気付けない事から何ができるのかを考えていきたい。その場に応じた環境で自分は病気と闘っている人に何ができるだろうか。言動や手助け、気づきや思いやりなどできることはたくさんある。分からなさから目を逸らさずに向き合う努力をしていきたい。日々のコミュニケーションから誰も取り残さない為の糸口が見つかるだろう。相手が誰であろうと現実から目を背けずに取り残さないための方法を見つけ、実践していきたい。
・小川 珠穂 公益社団法人MORIUMIUS 性別が嫌い、それでも女として幸せに生きている。
「性別とはなんなのだろう。」
わたしの性別は女である。しかし自分の中でこの問いはずっと離れなかった。お菓子づくりが好きで作ったお菓子を配れば、「女子力高いよね」。夏にワンピースが好きで着ていれば、「女子はワンピースあるから涼しそうでいいよね」。お菓子を作ることにもワンピースを着ることにも性別は関係あるのだろうか。自分が好きだからやる、どうしてそれで完結しないのだろうか。ずっとずっとモヤモヤしていた。すぐに女性と男性という枠に押し込められるのが嫌だった。
漠然とこの想いを持ったまま大学生になった。大学生になる少し前くらいから社会ではLGBTQという言葉が認知され始めた。わたしは男性を好きになるし、男性になりたいわけでもないから関係ないと思っており、深くは調べなかった。しかし、「性別とはなんなのだろう」という問いだけは自分の中でずっとあった。わたしは女である、しかし女という枠に当てはめられたくない。その想いが強く募るようになり、髪は短くツーブロックに、服はユニセックスのものを纏い、性別というものを自分の中から排除しようとした。しかしその格好で、女子トイレに入ればギョッとした顔で一度振り向かれる。生理が来れば女であることを突きつけられる。また同じように性別を排除したいわたしにはセックス、妊娠は自分には無理だと感じ、誰かとともに人生を歩むことは無理だと絶望する。この時期のわたしは性別が当たり前となっている世の中に絶望していた。
そんなとき、大学の授業の中でLGBTQについて学び、Qのクエスチョニングという概念があることを知った。クエスチャニングとは自分の性が定まってない、または意図的に決めていない人のことを指す。こんな価値観があったのか!と目を見張る衝撃だった。性別を決められない人も同じようにいる、その事実がとても嬉しかった。そしてさらに調べていくうちに、Xジェンダーという、性自認が男性にも女性にも当てはまらないセクシュアリティがあることを知った。このセクシュアリティに出会ってからは、自分はXジェンダーであると自認している。
女性でも男性でもありたくない。これがわたしの願いであり、理想であると感じている。わたしはわたし。言葉だけ聞くと当たり前のように思えるが、性別という枠にさえわたしを押し込めたくないという想いを自分の中に納得して落とし込むまでにたくさんの時間がかかった。性別という概念が当たり前としてある社会に苦しむ人がいる。このことが少しでも広まってほしい。そして今わたしには男性のパートナーがいる。もちろんわたしは、髪型はツーブロックにして、生理もきて、セックスもするし、性別が嫌いだ。それでもこの想いを受け止めてくれわたしの存在まるまる愛してくれて、わたしもそれを受け入れている。これまでたくさん悩みもがき苦しんだ。その末に自分を受け入れ、愛する人ともに幸せに過ごしているという今があるということも、同じように知ってもらいたい。
・大磯 龍馬 立命館大学文学部3年 「お兄さんありがとう!」交流機会の意味合いは無限大
「取り残される」ことは、他人にとっては微塵に感じるかもしれないが、当事者である自己にとっては一生心に刻まれる苦しいものだ。しかし、そのような場合でも同じ境遇を経験している人との交流は、人生を大きく変えるクッションであるといっても過言ではないと断言できる。以下は実際に取り残されていると感じていた僕自身の経験である。
『では、自己紹介をしてください。』「ぼ、ぼぼぼぼく、ぼくのなまえは、・・・りょ、りょうま・・・です。」小学3年生のクラス会での出来事は今思えば、心に金づちで殴られているかのような衝撃的な瞬間だった。周囲から聞こえる嘲笑いや鋭く突き刺さる目線、よくここまで生きてこれたよな。
私は小学校3年生のころから「吃音症」という、言葉を滑らかにスムーズに発することが難しい発話障害を持っている。特に初めの第一声を言い出しづらいように感じていた。吃音は日本の総人口の100人に1人ほど持ってると推定され、多くは2歳から4歳のころに発症し、大部分はすぐに治りますが治らずに大人へと成長する人もいる。小学生や中学生に発症する人も少なからずですがいらっしゃる。その吃音ですが、親の遺伝やケガなどで発症するものでなく、突如何の前触れもなくやってくる。朝起きると昨日までスラスラ話すことができていた言葉も発声しづらくなってしまうのだ。吃音というハンデを持っているなと強く感じるのは、小学校の国語の授業にて行われる教科書の音読の時間だ。出席番号順に前から1人2,3文ずつその場で立って読んでいき、少しでも言葉に詰まったら即終了という、私にとっても吃音当事者にとっても地獄のような時間です。頭の中では字も読めるのに、いざ言葉を発すると詰まってしまう。そうして何も読まずに座り、周りから冷たい視線と笑い声を浴びるといったことを繰り返し、「なぜ僕だけみんなのように普通に話すことができないの?」「なぜ僕だけこんなに辛い思いをしなくちゃいけないの?」と、家に帰った後は一人で泣いていることもあった。「普通の人と僕は違うんだ」と思い始め、一時期は誰にも相談することができずにいた。勇気が出なかったこともあり、当時の小学校のクラスメイトにも私の症状について話すこともできず、1人でいることが多かった。中学校に進学してからも長い間私が吃音を持っていることを隠していたのだ。しかしそんな私にも一筋の光が差し込んできた。中学3年生になり、同じ学年にもう1人吃音を持っている男の子がいると分かり、勇気を出して「あの、、、ぼぼぼぼくも吃音を持っているんだ、よかったら一緒に話さない?」と声をかけた。すると受け入れてくれたのだ。その瞬間の溢れかえった僕の涙は忘れない。一瞬にして重荷が外されたような心地がした。これまでの吃音経験で苦労したことを共有しあったことで、人生で初めて、このような吃音で苦しんでいる人は私だけではないんだと実感した。本当に泣きそうだった。大学生になった今では、吃音の発症頻度は当時と比較すると減ったが、自らの口で「吃音症というハンデを抱えています。どうぞご理解いただきたいです。」と、伝えることもできるようになった。本当に成長したね。
推測するに、同様の経験をしている人は日本中に多くいらっしゃると思う。吃音を持っているということを打ち明けるのが怖いと思ったことのある人も多いことでしょう。上手に話すことができる人、話すことが苦手な人、両者とも多くいらっしゃる。当事者同士で会話し、過去の経験を共有することが僕にとっての転機となり、自然と見えない言葉の壁もなくなったように感じている。人に馬鹿にされたことも話し方を真似されたこともいじめられたことも全てが風に流されていった。障がいだけでなく、病気、人種差別、貧困といった国際問題までも「取り残される」といったことは、あってはならないことだ。しかし、それらは口だけで解決できるものではないと思う。そのような苦しいと感じている人たちに、心を軽くして前を向いてもらうためにアクションを起こさなければならないと切に思う。
僕は今、このような過去の経験から大学と通信制高校と協同で行っている不登校経験者や学校へ行くことが苦しいと感じている人たちのための居場所づくりプロジェクトを運営している。様々な障がいを持っている、不登校を経験している高校生や大学生がたくさんいる中、同じ障がいや生き方をもつ当事者同士での交流や対話といったイベント企画に複数回携わっている。少しでも前を向いてほしい、話し合える人がいることで少しでも心が軽くなればという想いはいつまでも変わらずに僕の心の奥底にしまっている。
「このような場を開いてくれて、お兄さんありがとう!」、参加者から一言いただけたことによる安堵する気持ちが芽生えると同時に、次なる交流機会の提供に向けて動き出す。まさに僕の夢だ。
・佐久間 未桜 東洋英和女学院高等部2年 いつも心におすそわけの精神を
我が家は、両親の仕事柄いただきものが多いいわゆる、恵まれた家庭だ。しかしながら贅沢な悩みだと叱られそうな悩みがある。3人家族では、すべてのいただきものを消費期限内に食べきれないのだ。その場合は、近所に住む祖母や友人家族にお裾分けをすることになるのだが、とても喜ばれる。我が家も捨てる罪悪感がなくなる上に喜んでもらえて嬉しいし、地球規模で考えればゴミ削減にも貢献、密かな満足感を得ることもできる。まさにwin-winである。
私は、これは社会問題である貧困とフードロスと同じ構造なのではないかと気づいた。個人と個人を繋ぐ手軽な手段があれば、お互いに助かる人達がいる。調べたところ、現在企業や自治体がフードロスやフードドライブの取り組みを行い、貧困に苦しむ人々を支援しているが、個人間を結ぶ取り組みはなかった。
しかし、フードロスの実態の40%は家庭ゴミであり、我が家もそれを実感している。食品を食べきれず捨てるのは、本当に罪悪感が伴う。貧困に苦しみ、お腹を空かせている方がいると思えば、なおさらだ。そのため個人間をつなぐ「おすそわけアプリ」を開発し、対極的な理由で困っている両者を繋ぎたいと考えた。
食品は消費期限があり短時間でのやりとりが必須。しかし貧困はデリケートな問題のため、個人情報は守りたい。
そのため、やりとりの拠点(ステーション)を区役所等の公共施設と、社会のインフラとなったコンビニに設置して、提供ユーザーは登録した住所に基づき提示される最寄りのステーションに、食品を持参して委託。金額を設定し、売上の半額がユーザーへ、残りはアプリ運営会社の収益にする。
消費ユーザーは、同じく登録住所から最寄りのステーションの品をアプリ上で検索。欲しいものがあれば購入してステーションに受け取りに行く。あくまで「おすそわけ」の相互公助の意識を持ち、金額は500円を越えないように設定。また食品は未開封のものに限り、安全性を保つ。
このような循環型のサービスこそが、まさに今後目指していきたい「誰ひとり取り残さない」全員参加型の取り組みではないかと思う。一見、なにも不足がないように見える恵まれた人にも、実は手を差し伸べる余地はあったりする。我が家にとって、それが過剰な食品を食べきれずに捨てる罪悪感だ。しかし、もしその食品で喜んで受け取ってくれる人がいれば、双方とも救われ、幸せになれる。一方通行の支援ではなく双方向の支援ならば、お互いに感謝しながら、負担を感じることなく持続することができる。
私は、小さな善意があれば、皆が気軽に参加できるおすそわけ「OSUSOアプリ」の開発によって、誰ひとり取り残さない共に助け合う未来を作っていきたい。誰かを助けることで自分が助けられるなんて、こんな素晴らしいことはない。
ちなみに、気づかれにくいように、アプリ名にはSOSがこっそり入っている。小さなSOSと、小さな善意を互いにおすそわけしていける、そんな願いを込めて。
・佐々木 颯太 宮城県名取高校 3年 いじめの加害者と被害者を取り残さないために。
いじめの「原因」は加害者である。誰もが思うだろう。もちろん、いじめにおいて「悪い」とされるのは加害者だと思う。しかし、「原因」は本当に加害者にあるのだろうか。
まず、絶対にしてはいけないこととしていじめの加害者と被害者の二者関係のみを見て判断するということがある。目に見えるところのみで単純にこっちが悪いと決めてしまうのは危険行為だ。なぜなら、いじめはかなり根深いところから繋がっているからである。AさんとBさんとの間でいじめが起こっていても、実はCさんが原因であったり、かなり遠くのFさんが原因かもしれない。はたまた家族や親戚にあるかもしれない。このように考えると、いじめにおいて本当の意味で加害者とは存在しないのではないか。必ず誰しも生活している環境や周りの人に影響を受けながら生きている。つまり人間は受動的ということが前提として能動的であるということだ。
つまりいじめを解決するためには被害者よりも加害者と呼ばれる本当の被害者に目を向けるべきなのである。もちろん全部のいじめがそうだとは思わないが、大抵のいじめは加害者の何らかの不安やストレスが原因になっていることが多いと言われている。勉強が上手くいかない、家庭でのストレス、人間関係の悩みなどの原因が根底にあり、不安だから人を攻撃してしまう。つまりこれは個人の問題ではなく、環境的な問題でもある。
では私たちにどんなことができるだろうか。それは子どもたちの生活環境を整えて、逃げ道を作ることである。日々の生活の中で逃げ場のない気持ちをいじめに形を変えて、誰かを傷つける前に私たちが阻止しなければ。「いじめはしてはいけないよ」だけでは何も解決に繋がらない。正しくは「いじめをさせてはいけないよ」である。いじめざるを得なかった人はもはや被害者なのである。
日本では、いじめを受けた被害者側へのフォローが主にされているが、アメリカではいじめをした加害者側にカウンセリングを行う。そこで、加害者側の家庭や友人関係に原因となるものがなかった考える。このやり方は日本にも反映するべきだと私は考える。
いじめは正直減るものでも無くなるものでも増えるものでもないと思う。いじめの増減を調べるいじめ認知件数の調査はいじめを認知できている件数でもあるため、一概に増えているとも言えない。私は平均的に見てあまり変化していないと思う。いじめは連鎖的である。誰かがいじめない場合、代わりに誰かがいじめられているかとしれない。そのいじめられた人がその怒りを誰かにぶつけるためにいじめるかもしれない。このように、いじめは一生なくなるものでもない。
このいじめ問題をよりややこしくしているのが、いじめの定義である。近年のいじめの定義は「被害者が嫌だと思ったらいじめ」。これはもはや、客観的にいじめかどうか判断するのは許されない状況にある。もちろんある程度の客観性は通されると思うが、最終的には本人の主観が決め手となると考えると、かなり複雑な問題になってくる。思いやり、優しさはあくまで主観であるため、よかれと思ってした言動が誰かを傷つける。
先述した加害者側に対するカウンセリングの前段階として、次に、閉ざされた教育空間の中で起きうるいじめについて話していく。人は皆、今まで生きてきた生活の中で「当たり前」という殻に閉じこもりたがる。「普通こう考えるよね」「それおかしくない?」と思い、自分とは違う考えの人を否定し、敵視する。これがいじめ問題の「ずれ」を起こす原因となる。「自分とは違うが、そういう考え方もあるな」と思える人が増えればいじめも減り、より思いやりが強い社会になるだろう。綺麗事のようだが、一歩留まって考えるだけで社会は大きく変わる。しかし、子供たちにはかなり難しいことだ。同じ地域の同じ学校の同じ教室で過ごすとなると、ある程度の「普通」が出来上がってしまう。そして異質なものは排除しようとする。そして異質なものは「普通」に比べて弱い。
これらの問題を少しでも解決に繋げる方法として、道徳教育が有効である。例えばP4C(philosophy for children)。普段の会話ではなく、哲学を通して根本的なことについてみんなで考える。そしていっその事、全員が集合している空間で、「普通」と「異質」をごちゃ混ぜににしてしまおう。いや、実際じっくり話し合ってみると、みんな「異質」だということに気づくだろう。同じだと思っていた人が実は異なっていた。これはじっくり話さなければ分からないことである。みんな個性があって、それは悪いことではないと子供のうちから教えることがとても重要である。そして自分の当たり前の殻を割ってもう一度外から見てみよう。見えなかったものが見える。これでようやく広い視野を持ち、「許す」ことができるようになるだろう。
・武田 結香 宮城県名取高等学校3年 あれから止まったままの時間
皆さんの記憶の中の「震災」はどのようなものでしたか。今はどんな印象ですか。
私が通っていた学校の隣の学校は津波に飲まれた学校でした。その為、震災前に通っていた生徒は私が通っていた学校に通っていました。
私が通っていた学校は、防災に活発に取り組んでいる学校で、週に1回は防災という授業がありました。もちろん、防災訓練も活発に取り組まれていました。
ですが、防災訓練に使われる警報音は私たちが思っている以上に被災者にとってはトラウマでした。泣き出す子、過呼吸になってしまう子、手が震えて動けない子。見ていられませんでした。防災の為というものの、被災者はまだ震災から止まったまま、一生忘れられないのです。皆さんは「震災を伝えよう」と言いますが、それを強要する必要はあるのでしょうか。
被災者は震災を忘れたい一方で、世間はそれを許してくれないのです。現に私もその経験をしました。また、私は逆に防災の授業を経て、トラウマになったという経験をしました。私は幼稚園の年長に被災しました。まだ小さかったこともあり、被災当時のことは覚えていませんでした。しかし、震災から10年経った頃、小さな地震が来ると過呼吸を起こすようになりました。10年経ってトラウマになったのです。
この経験を経て、私は震災経験を強要するのではなく、震災を伝えようとして伝えるべきだと思います。
例えば、駅の構内にポスターを貼ることです。ポスターを貼ると言っても、QRコードにして、読みたいと思った人だけわかるようにしすることで、震災の風化を防ぐことができ、且つその意思がある人、興味を持った人だけに伝えることができます。また、駅の構内に貼ることで、人目につき、宣伝効果があります。そしてこの提案の最も良いところは、”読み取りたい人だけ”読み取れるというところです。逆手に読めば、読み取りたくない人は無理に知ることがないということです。このことによって、震災にトラウマを持つ人、思い出したくない人は無理に思い出す必要がありません。
また、QRコードで被災者の言葉を綴った動画を配信することで、被災者自身の言葉を直に知ることができます。今現在、被災者の言葉を受け取ることができるのは、「語り部」という震災を発信する施設があります。「語り部」は宮城県に数少ない施設であり、一つの施設は宮城県石巻市にあります。しかし、「語り部」では、語り部の人としての認定もあるため、数少ない人数となっています。そのため、震災のことを一度に発信できる人数は限られています。しかし、QRコードで震災のことを発信することで、一度に人数の制限が無く「語り部」の方の話を発信することができます。また、「語り部」の方々も永遠に語ることができる訳ではありません。ですが、「語り部」の方々の言葉をQRコードに動画として保存することで、半永久的に保存することができます。当時の震災の状況というのは被災した当事者自身にしか理解することができません。動画にすることによって、当事者自身の言葉の抑揚だったり、感じ取れるものだったりするもので、初めて現場を想像し、全ての情報を受け取ることができます。また、後世に伝えていくとなると、いつかは震災を知らない人から知らない人へということを通して、誤った情報や当事者でない限り伝わりにくいという点もありますが、QRコードにはその心配もする必要がありません。
それらの点を踏まえて、今回のアイデアであるQRコードにし、動画や情報を駅の構内などの人目のつく場所で発信することは、震災を忘れたい人、震災を知らない人などの未来の後世の人々に伝えたい人双方にとって明るい未来へと導く鍵になると考えています。
そして、これらのアイデアだけでは、簡単に震災から一歩踏み出すことは不可能です。私は「震災を乗り越える」にはその人自身の意識を変えることから始めることが重要だと考えています。
・田中 佑京 追手門学院大学3年(休学中) 普通に囚われた結果、世界から取り残される
普通とは何であろうか。それは、私にとっての人生最大の疑問である。誰かに普通と私は言われたことはない。人々は、普通かそうでないかで人を区別することがある。また、多くの人が普通になりたいと感じる。なぜ、普通にならなければいけないのか。私には理解できなかった。
私が小学生の時、普通を押し付けられたことがある。それは、ある人に「あなたの話し方が標準語ではない」と馬鹿にされたことがある。それは、九州のとある盆地での出来事であった。そこでは、一般的に標準語といわれる方言は話さない。だが、そこに住む人にとっては、関東から転校してきた私の話し方は標準語ではなかった。果たして、どちらが正しいのであろう。確かに、東京で話される言葉を標準語というのかもしれない。しかし、地方に住む人にとっての普通の言葉は東京で話される言葉ではない。だからこそ、そこに住む人にとっての標準語はその地域の方言だったのかもしれない。だが、そこでの常識が普通だからといって馬鹿にし、方言を話すことを強制することはしてはいけない。逆もしかりである。地方から東京に来た人に対しても、話し方を笑うことは許されることではない。場所によって普通は変化するが、その普通を押し付けることは悪である。
私も普通を誰かに押し付けたことがある。それは、韓国の方々に対してだ。私はニュースの一連の報道やSNSなどによってあまり印象はなく、韓国の方々に対してはすべて悪い人だと決めつけていた。しかし、現在ではそうは思わない。私はカナダに留学に来ているが、留学先で初めて優しくしてくれた日本人以外の人は、韓国の留学生だった。私は英語ができなかった。だからこそ、語学学校の授業についていくことができなかった。そんな中、助けてくれたのが韓国の留学生だった。私を助けることによって、授業についていけなくなるにも関わらず、嫌な顔をせずにジェスチャーをしながら英語を教えてくれた。また、授業外でも声をかけてくれたりする人も多かった。留学する前は、韓国の方々と私は関わったことがないのにも関わらず、韓国の方々を悪だと決めつけていた。日本人にもいい人や悪い人もいれば、韓国にもいい人や悪い人もいる。私は個人で人を判断するのではなく、日本のニュースやSNSなどで得た情報によって人々を決めつけていた。人によって性格は違うのに、自分の中の普通を押し付けていたのかもしれない。だからこそ、私は「知る」ということが大切だと思う。私は、相手のことを知らないからこそ自分の中の普通を押し付けてしまう。確かに、普通に生きることは大切なのかもしれない。だが、普通ということに囚われすぎて、自分の中の普通ではない人をないがしろにしてはいけない。同じ普通を押し付ける人が多ければ多いほど、変わった人として取り残される人が現れるかもしれない。それは、あってはいけないことだ。確かに変わっている人がいることは悪いことではない。しかし、それは他人誰もが自分が変わっていることを理解し、自分の普通は他人の普通ではないことを理解するべきだ。
私たちは、どうすればそれを解決できるのだろうか。それは自分と違う人と交流することだ。つまり、言葉、人種、年齢、性別などが違う人と交流することだ。自分と価値観が同じ人と話していても新たな価値観は生まれない。そして、自分の考えと違う人を否定してしまうことがある。その考えをもとに、私は留学先で多言語交流会に参加している。私はそのイベントに参加する際あることを心掛けている。それは、「私の普通は、相手の普通ではない。相手の普通は、私の普通ではない。」ということだ。私はその心がけによって相手を否定することなく交流をしている。私は日本に帰国したらあることをしたい。それは、「多言語交流会」である。留学前の私と同じ考えの人に、「知る」ということを大切にしてもらいたい。多言語交流によって、相手の考え方を知り自分と異なる人が多いということを理解してもらいたい。そして、取り残されている人は、多数派によって馬鹿にされる少数派だ。それと同時に、自分のことが普通と思っている人も、世界から取り残されていると思う。それは、どの問題においても言えることである。私の考え方は、他の人とは変わっているかもしれない。あなたにとっての普通は何ですか。私にとっての普通は、人と違うことである。
・森 美唯菜 立命館大学1年 世界インクルーシブ駅伝
「We」、それは誰が含まれているのだろう。誰もかもが同じ人間として生まれてきているのに、今日、取り残されている人について問題になっている。私はアメリカに引っ越した時に、ある先生と友達がきっかけで、インクルーシブな世界へ魅了されていった。
私がアメリカへ引っ越したのは高校1年生の頃。空気の読める年齢だからこそ、英語がカタコトの私には、ネイティブの輪に入るのが難しかった。声をかけてくれる子はいるのに愛想笑いで終わってしまう。やがて、孤独を感じるようになった。ひょうきんな性格だった私は、そんな自分が嫌いになり、涙が止まらなくなってしまった。そんな時、救ってくれたのは一人の先生だった。先生はいつも私の英語の宿題をサポートしてくれ、その間に沢山の会話をしてくれた。悩みを聞いてくれる日もあれば、日本の文化や食を共に楽しんでくれる日、雑談をして共に笑ってくれる日もあった。教室に入ると、先生が覚えてきた日本語で「こんにちは、元気ですか?」と挨拶してくれることもあった。私はそんな思いやりのある先生のことが大好きだ。そんなある日、先生が紹介してくれたダンスのクラスで一人の友達ができた。彼女は常に私の隣にいてくれ、私を安心されてくれる存在だ。孤独に悩んでいた私にとって、彼女の存在は大きく、彼女と話すことが高校へ行く意味とまでなっていった。彼女は、パートナーや他の友達といる時でさえも、私を置いていかなかった。誕生日会や卒業パーティーまで私を誘ってくれて、アメリカでの思い出は親友との思い出でいっぱいだ。気が付いたら、彼女の友達を始め、友人関係が広がっていった。私は一人取り残されることのなく、先生、そして親友に助けてもらった。私は周りの人に恵まれている。私は感謝すると共に、これから先ずっと、彼らから受け取った思いやりの気持ちを強く持ち続けると心に決めた。
私も彼らのような人になりたい。思いやりを持って、誰一人へと隔てがなく、人を大切にできる人。彼らは私の恩人であり、目標だ。正直、私は日本にいる頃、そんなことを考えたこともなかった。何不便なく友達と楽しい学校生活を送り、それが当たり前だと思っていた。しかし、それが当たり前ではなくなった時に、思いやりの大切さを知ることができた。駅伝のように、思いやりを届ける襷をもらったようだ。そして、その襷を繋いだ先にはインクルーシブな世界が待っているに違いない。世界には、人種や性別、障がい、見た目など、様々な理由で、孤独を感じている人がいる。私はそんな彼ら、何人にでも、この襷を繋げていきたい。そして、繋げていって欲しい。そんな強い思いで日本へと帰国した。
私は帰国後、大学へ入学した。私の専攻学科は英語で学位を取ることができ、秋入学ということもあり、私は留学生に囲まれて生活をしている。私は、アメリカで受け取った襷を握り締め、留学生たちに思いやりの心を持って、分け隔てなく、時間を共にしている。日本語の宿題をサポートしたり、日本のことを教えてみたり、翻訳をしてみたり、沢山の方法で思いやり精神を届けようとしている。また、彼らから英語を教えてもらったり、彼らの文化を共有してもらったり、私自身も親切にしてもらっている。思いやり溢れるこの専攻学科で、誰一人残されることのなくインクルーシブに襷は広がっていっている。いつかは、学部を越え、大学を越え、日本を越え、世界でこのインクルーシブ駅伝が広がっていって欲しい。私はそこに力一杯貢献したい。
「We」、それはまだ世界規模で完成していない。思いやりで「I」と「I」を繋げていく事で、「We」の規模は大きくなっていく。私たちはみんな共に生きている。世界中の誰一人残されず、全地球人が口を揃えて「We」と言える時こそが、世界インクルーシブ駅伝のゴールテープを切る瞬間だ。
・寺田 尚布 愛知学院大学文学部日本文化学科2年 みんなちがう、みんなおなじ
「私」という人間は、私一人しかいない。「あなた」という人間も、あなた一人しかいない。「私」が「あなた」になることもなければ、「あなた」が「私」になることもない。どれだけ仲が良くても、どれだけ共通点があっても、「私」と「あなた」はずっと別人のままだ。そんなことは当たり前だと、誰もが思うだろう。それなのに、なぜ人は、「おなじ」ばかりを好んで、「ちがう」ことを嫌うのか。なぜ、自分と少しでも「ちがう」人間を排除しようとするのだろうか。
私には、次の春で中学2年になる妹がいる。妹は発達障がいと診断されており、言語だけでなく、学習やコミュニケーションなども遅れている。そのせいかどうかわからないが、友達があまりできなかったり、勉強に集中できなかったりして悩むことが多い。だが、妹にも立派な感情がある。嫌なことは嫌と言うし、楽しい時は笑う。私が泣いていた時に、「ねぇね大丈夫?」と声をかけてくれたこともある。私は、そんな優しい心をもった妹が大好きだし、妹が困ったときは絶対に助けようと心に決めている。
私が帰省していたある日、最近同じクラスの子から嫌がらせを受けていると、妹が話してくれた。それを聞いた私は、妹のことが心配になり、妹の連絡ノートにメモを挟んだ。その日の夜、学校から父のスマホに電話があった。相手の生徒が妹に嫌がらせをしたことを認め、妹に直接謝ったらしい。担任の先生のこの対応が本当に正しかったのかどうか、正直わからない。でも、後日、嫌がらせは収まったと妹の口から聞けて、少しだけ安心できた。もう二度とこんなことが起こらないように、これからはもっと妹の様子を気にかけようと、私も反省した。
そもそも、なぜ妹が嫌な思いをしなければならなかったのか。たしかに妹は、他の生徒と比べて遅れている部分が多い。違う部分も多い。でもそれは、みんなも同じである。運動が得意な人がいれば、苦手な人もいるし、本を読むのが好きな人もいれば、嫌いな人もいる。それぞれがそれぞれの個性や才能を持ち、一人の人間として生きている。他者と「ちがう」ことは、おかしいことでも恥じることでもない。みんな違って当然なのだ。だから、他者と「おなじ」であることばかりを求める必要はない。むしろ、他者との違いを受け入れることの方に重きを置くべきである。時には、違いを受け入れることを難しく感じることもあるかもしれない。そんな時は、無理やり「おなじ」にするのではなく、「おなじ」と「ちがう」の真ん中の、第三の視点を考えればいい。そうすれば、自分の中の視野が広がり、柔軟に物事を考えることができるようになるだろう。
でも、一つだけ、みんな「おなじ」ことがある。それは、誰にでも“幸せに生きる権利”があるということである。人はみな、この権利を行使することができる。だが、同時に、他者の“幸せに生きる権利”の行使を妨害しない義務が発生する。よく考えれば、当たり前のことではないだろうか。人の幸せを邪魔する権利なんて誰にもない。それぞれが持つ個性や才能を、馬鹿にしたり踏みにじったりする権利なんて誰にもない。そんな当たり前のことを理解しようとしないから、喧嘩や争いが起こってしまうのだ。
このたった一つの「おなじ」を大切にしながら、「ちがう」を受け入れていく意識がみんなの中にあれば、誰一人取り残されない社会になるに違いない。
・渡邊 二葉 神戸市立高取台中学校 学校生活で取り残されやすい私が願うこと
「まずやってみよう」「書くだけだよ?」「発達障害とか関係ない」
その時私は取り残されていると思いました。
私は文字を書くという行為がすごく苦手です。
疲れてしまうし、時間もかかります。何より、字を書かなければならない、と分かったときにすごく苦痛を感じてしまいます。でも、書けないわけじゃないんです。ただ苦痛を感じるだけなんです。だからこそ、取り残されやすいんだと思います。
私は今の発達障害に関して学校の体制に多くの問題があると思っています。
1つ目は「学習をしない」ということです。
小学校の時に、障害者の人から話を聞いて体験してみるという授業がありました。
車椅子に乗ったり、目隠しして白杖で歩いてみたり、手話を学んでみたり。
でも発達障害については学んだことがありませんでした。
どんな種類があるのか、どんなことで困るのか。困ったときどんな対応をしてほしいのか。
学ぶことが出来なければ、何も出来ません。
自分がもしかしたら障害を持っているかもしれない、と気付くことが出来ます。
発達障害で困ったときに対応してもらいやすくなります。
酷い言葉を言われることも減ると思います。
多くの人が発達障害について理解を示してくれると安心して助けを求められやすくなり結果的に取り残される人が減っていくと思います。
2つ目は「多様性を認める」ということです。
書くことが苦手な私にとっては、自筆ということが学校生活で大きな負担になっています。
今は全校生徒にパソコンが配布されています。なので私は作文の提出をパソコンでしたいと先生に言ってみたところ、「まずやってみよう」「発達障害とか関係ない」と言われました。
出された課題は「作文の提出」です。自筆でなければいけない理由も説明されず、ただやみくもに否定される、助けてを求めたけれど拒絶されることはすごく苦しかったです。
そこから、何度も先生に自筆で書くことを求められましたが、親に助けを求め、難しさを説明した時ようやくパソコンでの提出が認められました。
けれども、あの時なぜ自筆を求めたのかは分かっていません。「もういいです。」と話を切られてしまったからです。
もちろん私だって、高校の願書がどうしても自筆でなければいけない、などと言われれば書こうと努力します。時間がかかっても、自筆でなければ受け付けてもらえないのであれば自筆で書きます。校内の作文で、掲示するときはパソコンで学年だよりに打ち込まれているのに自筆でなければいけない理由が分かりませんでした。
もっと多様性を認めてもらえれば、先生の言葉に傷つかなくて良かったと思います。
そして、発達障害を持つ人だけでなく、パソコンの方がいいという人にはパソコンでの入力を認めてほしいです。もちろん手書きが良いという人は手書きで提出して、他にも選択肢があればその選択肢を最大限に活用できるようにしてほしいんです。
学校に行くことの苦痛が減るし、自分から勉強にも取り組めるかもしれません。
私は発達障害を打ち明けることがすごく怖いです。
馬鹿にされてしまったら、自分ができることも奪われてしまったら、そう考えると打ち明けることが出来ません。
誰も取り残されない未来のために、まずは学ぶことから始めてほしいと強く思います。
安心して支援を求められること、学校が苦痛にならないこと。
私たちはまだまだ学ぶことがたくさん残っています。
学び続けた先には「誰も取り残されない未来」に近づくことが出来ると思います。
・横山 芽 宮城県名取高等学校3年 私だから言えること
私は、どうしたら入院中の学生の心を和らげることが出来るのかについて研究をした。
その背景には、自分の実体験が重なる。自分が入院を繰り返す中で、学生時に入院した時期が最も精神的不安が大きかった。その結果パニック障害になってしまったのがきっかけである。
私は、学生の入院環境に問題があるのではないかと仮説を立てる。学生にとって入院とは、その期間が短くとも長くとも、大きな人生の分岐点であることに変わりはない。毎日当たり前にしていた勉強、朝起きて学校に行き、沢山活動をして家に帰ること。しかし、病気と判断され、入院を告げられた日から、これまでの当たり前の日常を急に奪われてしまう現実。その現実に打ちのめされた時に気持ちが追いつかず、鬱状態に陥ってしまう。そんな事例が、特に悩みや、人生の分岐点に立つ学生が最も多いのだ。そこで私は、学生が多く入院する大学病院と、子供が通う子供病院に視点を向けた。子供と学生の入院生活で何が違うのか、どのような差があるのかを追い求めた。
まず第一に、患者さんが視覚的に目に入る、情報量の偏り。大学病院では、医師や看護師、医療関係者おおよそが真っ白な白衣であり、トイレや入院部屋、検査室、廊下、全てが白を基調としていた。一方、子供病院では、医療関係者はピンクやオレンジ、ベージュなど全体的に柔らかい色を着用。また、病院内が基本的に、程よく色とりどりであり、視覚的に患者さんがリラックスできる工夫がなされていた。第一印象として、白を基調とする大学病院も良いのではないかと思う。しかし、患者さんは長期入院をしなければならない現状にいる。少しの期間で家に帰れず、承諾を得ない限り、病院で生活をするしかないのだ。そんな中、家とは真逆の真っ白な空間でずっと生活しなければならないと考えると、気づかぬうちに視覚的に日常とは異なる差にストレスを感じてしまうのではないか。
第二に、医師や看護師、医療関係者の対応の仕方の違いである。大学病院では、基本的に朝昼晩に体調チェックが入る。検査があればそれ以外にも看護師と関わる機会は増えるが、主に体調や病気の話題が中心となる為、学生が素直に本音を吐いたり、楽しく話をしたりする場が限られてくるという問題があるのではないかと考える。それに対して子供病院では定期的に看護師が患者さんの元に行き、体調のチェックだけでなく、個人の相談や気軽に日常会話をできる環境にある。やはり、患者さんにとって1番近い存在である看護師が一人一人それぞれの患者さんと向き合う姿勢が大切であると確信している。実際私も6歳の頃と16歳の頃に入院を経験したが、沢山コミュニケーションをとってくれるのは6歳の入院の頃であった。家にいるという感情まではいかなかったが、不安や悲しみは全て看護師さんに気軽に伝えていた記憶がある。そこで私は沢山の人に話を伺ってきた。その中でも、2人を取り上げたい。3年間入院している小学四年生の男の子と怪我で入院した17歳の男子高校生だ。その2人話を伺うと、年代や所属している場において、一人一人の心境が大きく異なっていた。まず、小学四年生の男の子はこんなことを私にふと言った。「いいな今日家に帰れるんだ。」「今日お母さんのご飯食べるの?」と。私はそう言われた途端に胸が締め付けられるように苦しく、涙が溢れ出るのを力強く我慢して喉が痛くなったのを鮮明に覚えている。こんなに小さい子が家族と一緒にいることが許されず、お母さんの味も忘れるほど長期入院をしている現実を目の当たりにした私は、本当に男の子がたくましく思えた。担当の看護師に聞くと、「この子は決して弱音を吐かないの。治療に前向きで、家に帰ることを目標にしているんだよ。」と話してくれた。また、17歳の男子高校生は、「勉強、進路の面が1番不安。」と言っていた。病院にいることで毎日の授業や課題が通常ではなくなり、全部オンラインになったり、分からないことがあっても病院に教師がいるわけではないので勉学について話せる人がいないという不安が大きいらしかった。確かに、他の友達はどんどん進んでいるのに自分はベッドの上で出来ることしか許されない。そんな場に突如置かれ、自分の身体のことで精一杯な患者さんは、身体的にも心理的にも様々な不安が高まるだけであった。加えて、私は、市立病院脳神経内科の医師と、市立病院や老人ホームの看護師さんにも話を伺った。その3人の医療関係者の話の中で共通していたことは「患者さんに寄り添う」という言葉だった。個人個人の患者さんに合った寄り添い方、患者さんの身体、心理と向き合う寄り添い方など、医師や看護師であるからこそできる支援。ずっと手厚くサポートし続けていく熱意が全身を通してしっかり伝わった。
これらを通して私は、学生が医師や看護師を信頼できる関係に築くことが最も大切であると考える。そのためにも、患者さんが負荷なく、心を安定にして過ごせる環境を看護師が日々作っていく必要がある。医療関係者は患者さんに寄り添う心を忘れず、真摯に向き合うことで、学生の心は和らぐのである。
・岩間 夏美 創価大学2年 教 育格差と学歴主義
教育格差について、考えたことはあるだろうか。
「教育格差 定義」で検索すると、教育格差とは、子供本人に変更できない親の学歴や収入など経済的、文化的な要素や出身地域等によって学力や最終学歴といった結果に差があることを意味する。と出てくる。
私は、中学まで公立の学校に通っていた。中学3年生の受験シーズンに入ると、当時の私は、様々な高校を見学したうえで、東京にある私立高校を第1志望に決めた。その高校は、当時の私の偏差値よりも遥かに上であった為、私は塾に通っていた。それも自宅から1駅隣の、比較的偏差値が高い高校を第1志望にしている生徒が通う塾だ。結果から述べると、私は第1志望の高校に合格した。
教育格差という問題があることに気付かされたのは、この頃だ。無事に第1志望に合格して浮かれている私の耳に入ってきたのは、「この高校に行きたいけど、家の経済的に無理かな」「この高校行きたいけど、自分の頭じゃ塾に行かなきゃ無理だ」など、「行きたい高校があるけど、その高校を選択肢に入れられない」ということを嘆く同級生の声だった。
「自分はなんて幸せな人だったんだろう。」そう思った。公立・私立関係なく、高校を選べるのも、その高校に行くために塾に通えるのも、当時の自分は当たり前だと思っていた。自分で高校を選べて、塾に通えて、その高校に合格するための勉強を不自由なくできる。それは、家族の一定のラインを超えた経済状況と学歴の上に成り立っているものだと気付かされた。自分で自分が通う高校を選択できない生徒もいる、本当はもっと勉強して行きたい高校があるけれど、家庭の事情で勉強時間を充分に確保できない生徒もいる。そのような生徒たちも居ると知り、それまでの自分の考えを恥じた。
大学に入ってから、「教育格差」という問題をより顕著に感じるようになった。2023年の夏に他大学の学生と関わる、とあるコンペティションに参加した。そのコンペティションに参加しているのは、大半が東京大学や慶應大学、早稲田大学といった世間で名の知れた大学だった。私が関わったそれらの大学に通っている大学生は、ほとんど浪人経験者だった。自分は浪人を経験していない。だからこそ、浪人してまで行きたい理由は何なのか知りたくなり、関わった他大浪人経験者に「浪人してまでその大学に行きたかった理由は?」と端から聞いて周った。そこで得られた解答はほとんどが、「就職に強いから」「有名な大学だから」という解答だった。
私はそこである種の憤りを感じた。何の憤りだったのかはよく分からない。でも恐らく、「大学に行きたい人が行けなくて、勉強することを目的としていない人が何故大学に行けるんだろう」という憤りと、実際問題、自分がその人たちよりも能力が圧倒的に劣っていると気付いた悔しさが入り混じった感情だったのだと思う。更にこの質問の答えから分かるのは、大学が「就職予備校」になりつつある、いや、なっている。ということだ。
ネームバリューのある大学の方が就職に強いというのは事実だ。そしてネームバリューが強い大学は偏差値が高いのも事実だ。しかし、ネームバリュー欲しさにその大学に入り、特に勉強に力を入れず4年間過ごし、卒業していく学生がどれだけ居るだろうか?
大学は就活予備校なのか?違う。大学は自分が学びたいことをとことん学ぶ場所だ。
生まれた場所や親の学歴によって、子ども本人の学力や最終学歴といった結果に差が生じるのは当たり前だ。しかし、勉強したいのにできない、受けたい教育を受けられない生徒、学生たちが存在するというこの現状は、とても哀しいことだと思う。教育を受けるのにもお金がかかる。奨学金制度もとても充実している。ただ、それでも行きたい学校に行けない子がいる。その一方で、何不自由なく勉強できる機会を得られている人が、その機会を無駄にしている。この現状にとても嫌気がさす。就職のために入った大学で何も学べずに就活時期になって焦るのでは本末転倒である。世界に目を向ければ、教育を受けられる人間はマイノリティーだ。
「誰一人取り残さない世界の実現」その為には、教育を受けられている我々が取り残されている人々に目を向けて動くことが重要だ。なぜ大学があるのか、何のために大学に入ったのか、大学生一人一人が考えられるようになって欲しいと思う。
・磯野 青哉 創価高等学校 3年 「孤独」から一人でも救うために
その日、彼女は死んだ。何もない平凡な一日が始まろうとしていた。でも、どこかおかしかった。先生は来ないし授業はすべて自習、何かがおかしいと思いながらも「ラッキー」程度にしか考えていなかった。しかしクラスメイトのある一言で空気が凍りついた。
「〇〇が自殺したらしい!」
後に学年全員が集められ、隣のクラスの女子が家で自殺したという報せがあった。信じられなかった。彼女は去年いじめに遭っていたけど丸く収まったはずだったし、今年になっていじめられている素振りや雰囲気は全く感じられなかった。否、気づこうと、知ろうとしなかった。学校に押し寄せる多くのマスコミ。ニュースに映し出される事件現場。警察が家に来るというイレギュラー。その日から私の中でなにかが変わったように感じた。
これは私が小学校6年生のときに実際にあった出来事だ。私の学年は5年生の時から本格的な学級崩壊が起こり、いじめのターゲットは生徒だけでなく担任の先生にさえ及ぶこともあり、それが理由で担任の先生が体調を崩し何度か変わることもあった。6年生になってからは学級崩壊やいじめなどが少し落ち着いてきたと感じていた。その矢先の事件である。何が彼女をそうさせたのか。なぜ自殺を止めることができなかったのか。彼女の自殺の原因は恐喝や強要に晒され、それを自殺に追い込むまで続けたことだ。彼女は誰にも頼れなかった。誰も救いの手を差し伸べなかった。なぜ?
これが孤独なのではないか。「一人って可哀想だよね」なんてありふれた事を言うつもりはない。ひとりでもいい。けど、「ひとり」と「孤独」は違う。孤独はその人の居場所を奪い、精神を蝕むだけでなく、周囲の人や物すべてが敵に思えてくる感情や状況だ。彼女は頼る人も環境も全てを加害者に奪われてしまった。同じ教室に加害者がいるし誰かに相談したことがバレてしまったらもっと酷い目に合う。そのような恐怖を彼女はいつも感じていただろう。そんな人がこの日本に、世界にどれだけいるのか。「孤独」な人を減らす方法はいくつかある。でもそれは個人で、しかも和らげることしかできない。完全にゼロにすることはほぼ不可能だろう。この「孤独」な人こそ「取り残されている」、最も救うべき存在なのではないだろうか。
それでもこの地獄から一人でも多くの人を救うために大事なことは「居場所」をつくることと「対話」ではないだろうか。ここで指す居場所とはそこにいるだけで気持ちを安らげる事ができ、自分という存在が受け入れられる場所のことだ。また、対話は一対一でも複数人でもいい。色んなことを話せる人を一人でも持つことだ。安心できる場所で他愛もない色んな話をすることで孤独感というのは次第になくなってくるだろう。浅はかだ、傲慢だ、と思うかもしれない。傍観者ごときが何を言ってるのか嘲笑したくなるかもしれない。でも、「自分がここにいてもいいんだ」と自身が必要とされる人間ということを知ってほしい。そのことを教える事ができるのは家庭や学校など人と関わることです。一人ひとりの可能性を信じぬき、全員が社会に必要な人材であることを感じさせる。そんな教員や生徒がひとりでも増えるだけで今後の日本だけでなく世界まで「誰ひとり取り残さない」社会の建設に繋がっていくと思う。その教員の一人を目指して揺るがない努力をしていきます。
・田代 英奈 山梨県立大学2年 0地点からの一歩
『100円が集まると、、病気で苦しんでいる子どもに注射を打てる、、、』
詳しい数字は覚えていないが、自分にも遠くの困っている人を助けることができるのだと初めて思った瞬間だったと記憶している。小学生の時、学校で配られたユニセフの募金袋に書かれていた文だ。100円の寄付でできること、数百円の寄付でできることが載っていた。この募金袋に300円をいれるために、必死に家のお手伝いをしてお小遣いを貯めたことを鮮明に覚えている。現代の日本に住む私達からすると「たったの300円」だが、あの300円が誰かの命を救ったことを今でも願っている。小学生のあの頃から約10年が経ち、現在大学2年生である私は看護師・保健師を目指して日々勉強をしている。
世界では5歳に満たない子どもが、毎日1万4500人、年間で530万人、命を落としていると授業で学んだ。肺炎や感染症で亡くなるケースが多く、ワクチンを受けていれば助かった命が多いという。それに比べて日本は、生まれてから着々と予防接種を受けて大人になる。罹患すると重症化する可能性のある疾病や予防できる疾病に対して正しく対策ができ、もし病気になってしまったとしても高度な医療をうけることができる。非常に恵まれている。また世界には、好きなものを好きな時に好きなだけ食べられる人ばかりではなく、いまだに栄養失調に苦しんでいる人が大勢いるのだ。他にも、親やこども、愛する人が病気になってもお金が無くて治療出来ずに亡くなるのを見届けたり、その日分の水を確保し生き延びるのに必死だったり、、、、今の私たちの生活からは想像もできないような苦しみや悲しみを味わっている人が存在する。あなたも以前、このような話を中・高の総合の授業などで聞いたことがあるかもしれない。だが、その話がただの「音」になっていないだろうか。今すぐ海外に行って、困っている人や悲しんでいる人を助けるお金・勇気・時間は私にもない。だが、日々満足に、いや、贅沢に生きているのとは反対にそういう人がいるということを知り、自分の幸せをかみしめ、自分にもできることを探し行動することはできる。
私の今の夢は、医療分野で貢献し、一人でも多くの人が苦しい思いをせずに好きな場所で好きな人と好きなことができる環境をつくることだ。誰ひとりとして、医療を受ける権利を、生きる権利を、大切な人と幸せに過ごす権利を奪われてはいけない。母子家庭だが、仕事も家庭のこともしてくれて、大学にも行かせてくれて、誰にも劣らない愛をくれた母。自分がなにをしようとしても、どんな状況でも味方をしてくれて背中を押してくれる姉。楽しい時、嬉しい時はもちろん辛い時に自分の事のように悲しんでくれて悩んでくれる友人。私の身近にいる大切な人たちだ。あなたにも、自分のことを無条件に肯定してくれるかけがえのない存在はいると思う。自分や自分の家族が同じ苦しい状況にあったらどう思うか、たった今、想像してみてほしい。
以上は海の向こうの遠い地域の話のような気もするが、在留外国人が保険に加入していないがために病院にかかれなくて、日本で一番心臓治療に強い病院の前で心臓発作によって亡くなったという残酷なことが日本でも起きている。2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された持続可能な開発目標。その一つである「すべての人に健康と福祉を」をどうしても達成したい。SDGsの目標が設定されてから8年、満期まで7年。過去に生きた人も、今に生きる人も、未来に生きる人も誰ひとりとして取り残さない。
『過去が現在に影響を与えるように、未来も現在に影響を与える。』これは、哲学者ニーチェの名言だ。過去から学び今の行動を選択し、同時に、未来に描く理想のために今できることを私もしたい。小学生の頃から続く道を見失わないように、今自分にもできることするために、そして誰かの原動力となれるように、誰ひとり取り残さないために、この文を書くことからはじめた。今、私は0地点からの一歩を踏み出した。
・保坂 優子 創価大学理工学部情報システム工学科1年 無意識のバイアス
「リケジョ」この言葉を聞くと、どのようなイメージが膨らむだろうか。2010年ごろからニュースや新聞、テレビでよく耳にした言葉である。この言葉に当てはまる私は、まるで「あなたは普通でない」と世間から宣言されたように感じる。私はただ私らしい人生を歩みたいだけだ。何故普通でないのか、普遍的な人生が正義なのか、と少しの怒りと不安がふつふつと心の中で沸き上がり、渦巻く。「誰も取り残さない」世界を作るために、私の感じた疎外感の要因を考えてみたい。
この違和感・不快感のもとは何か。この問いを深める前に言葉の定義を確認したい。「リケジョ」とは「理系女子生徒」の略語であるが、数学・物理等の理系科目を専攻する女子生徒、及び研究者を含む理系専攻の職種に就く女性のことを指す。私は高校で理数科に進み、大学では情報工学専攻に在籍している。将来はSEになりたい。周囲から見れば、生粋の「リケジョ」だろう。「『リケジョ』はかっこいいし、すごい」という文面は一見すれば誉め言葉であり、私もそう言った周囲の言葉に嫌悪感を抱くことはない。実際女子学生は情報工学専攻では1割程のため、相対的にマイノリティであることは客観的事実である。しかしそもそも「リケジョ」=かっこいい、また「理系女子」=すごいという考えはどこで生まれたのか。ここに私が感じる疎外感の原因があるように思えた。
そこで、友人に「なぜ『リケジョ』はかっこいいと思うのか」と尋ねた。すると「わからない。なんとなくのイメージ。」との返事だった。つまり「『リケジョ』はかっこいい」というイメージは無意識のうちに創出されているようだ。他の友人に聞けど、同様の返答だった。私の周囲の十数人は異なる人生のバックグラウンドを持つにも関わらず、「リケジョ」に対して似通った価値観を抱いていた。
私はこの結果から共通認識が生まれる要因を考察した。1つは個人の見聞からくる価値観の創造である。理系の女子は少ないという事実から女子は理系科目が苦手であり、理系を選んだ女子はかっこいいという価値観の連鎖、統計学的でいう「交絡」バイアスが存在する。もう1つはメディアによる価値観の共有である。個々が事実から創造した価値観がメディアにより普遍化され、価値前提となる。きっと「リケジョ」に対する概念、もはや「リケジョ」という言葉自体が2つの要因から形成されたのだろう。
この固定的価値観に疎外感を感じているのは私だけではない。試しに、周囲の理系女子に尋ねると、「リケジョ」への認識は不快であると感じる人は多かった。理系の男子を指す呼称はあまり見聞きしないが、少数派の女子に対して「リケジョ」を多用することはジェンダー平等の観点で良くない。さらに「リケジョはかっこいい」というイメージから人格や好みを固定化されるという問題もある。友人はピンク色が好きだと言うと周囲に驚かれるという。理系・文系や男女の区分けに関係なく、ピンク色が好きなことは個性であり、驚くことではない。世間がスポットライトを当てる善意の目的で使い始めた「リケジョ」という言葉が呼ばれた当事者にとってはステレオタイプや悩みの種となり、そのフレームのなかで生きづらさを感じている現状が見える。なんというジレンマであろうか。
私が望むのは「リケジョ」という言葉がなくなることである。「理系女子」に対する無意識のバイアスを消すためには「リケジョ」という差異のシンボルを無くす必要がある。誰でも理系進学すること、エンジニアになること、理系分野の研究者になることが自由な選択肢として当たり前に存在してほしい。理系女子の少なさに関しては、本人の意向だという意見もよく耳にするが、本当にそうだろうか。私は無意識のバイアスから女子が理系に進学することを親に否定され、高い学費のうえに労働環境が不安定なのではという心配から理系をやめた友人がいる。だからこそ、私は無意識のバイアスによる不自由が起きない世界になってほしいと願うのだ。
このように、私は今回「リケジョ」という言葉から共通認識として生み出されたイメージや価値観に理系の女子が取り残されている現状を見つめた。しかし、これは「リケジョ」に限った話ではない。看護師、SE、主婦、サラリーマン。この4つの例を聞けば、男女を分けてイメージする人が多いだろう。問題提起している私も、読んでいるあなたも、様々な単語に自分なりの解釈やイメージを持っているのである。大切なことは自分の言葉には無意識のバイアスがあることを知り、周りの考えがたとえ自身の価値観と違っていても耳を傾けてみることではないかと思う。もしある言葉によって誰かを取り残していたと気づくことができたなら、その時点から変えていける人でありたい。一人ひとりがそんな風に少しずつ身近な行動を変えていけば、誰もが心地よく共生できるのではないだろうか。
・沈 鳳璽 東京女子大学 2年 暗闇の中に潜んでいる陳腐から
私は小さい頃から性教育を受けたことがなかった。しかしながら、祖母と両親は私に家事を学び、マナーを身につけ、将来的には賢い妻と母になるようにと教えてくれた。
なぜ家事を学ぶ必要があるのだろうか、彼らはこう言う:「料理ができなければ、将来あなたが結婚したときには夫の家族に非難されることになるだろう。家事ができなければ、将来子供が生まれたとき、どうやって子供を育てるのだろう。」 また、女性のマナーにとしては脚を開かないで、椅子に脚を掛けないなどが挙げられる。「なぜパパは食事中に脚を椅子にかけていて、私はできないの?」と反論すると、「なぜなら君は女の子だから。女の子はそういった優雅でない態度は取ってはいけない。そんな悪い習慣が身についたら、将来誰も君を嫁にもらってくれないよ」と言われた。その時私は、一体何が優雅であり、優雅であるためには誰に向けて優雅でなければならないのか、家事を学ぶ目的は一体何なのか、ただ自分の夫と家族により良く仕えるためだけなのか、女性は一生をかけて誰かを喜ばせないと良い生活が得られないのか、と考え始めた。こういった言葉を聞くたびに、両親や祖父母がまだ伝統的な男尊女卑社会の産物であることに気付いた。しかしながら、私一人では長い歴史のある中国式の教育やこのような思想を矯正する能力がない。
中国古代の男尊女卑制度は、現代の人々の様々な行動や思想に依然として影響を与えていて、私が小さい頃から浸透してきた儒教思想は、男性優越を強調し、家族の血脈を継ぐことは男性の責務であり、その結果、女性の地位は通常結婚、出産、家事に制約されている。女性は伝統的な考え方によって、家族の血脈と家庭の安定を維持するために優れた妻と母親になることが期待されている。社会は、女性が進学する必要はないとし、「女子無才便是德(女子は才能がない方が美徳である)」と考えられている。このため、正規の学習や教育を受ける機会がほとんどない女性は、夫や子供に依存せざるを得ず、男尊女卑の思想をさらに深刻にしていくと考えた。
更に、かつて生理中の女性は汚らわしいとされ、他人から隔離するために別の部屋に閉じこめられていた。 その後、女性は通常の活動をすることは許されるようになったが、神仏や線香を拝むような冒涜的な行為をすることは許されなかった。 現代社会では、男女平等を唱え、生理学の知識も普及しているが、生理用品を買いに行くとき、黒いビニール袋に包む必要があるのかと聞かれるし、月経についても、とても話しにくいことのようだ。昔から伝わる思想は、女性の原始的、正常的、生理的な存在を完全に抹消しまい、「純粋で清潔で、女性を抑圧するための聖域」と呼ばれる領域が作り上げられ、各世代の女性はこの「聖域」で無限の規則と制度に押し潰され、抑圧される。もちろん、窓を破り、社会に反抗し、思想を変えようとする「神経症的」な人々も出てきた。彼女たちは結婚や出産に消極的になり、親に決められた生活に反抗し、自意識を持って立ち上がり始める。しかし、彼女たちは相対的に進んだ思想を持っているため、適応しづらく、理解されづらい存在となっている。最終的には世間や舆論の圧力から逃れることは難しく、将来的にはかつて嫌っていた姿になって、自分の子供に対しても同じように説教することになるだろう。ただ、彼女たちも自分の子供の考えが正しいことを意識しているが一度経験した自分自身の結果を子供たちに背負わせる勇気はない。
では、男女は本当に平等なのだろうか、一部の人が決めた社会のルールのもとで、女性は本当に男性と同じ土俵に立てるのか、本当に恐れずに自分のセックス観とセックスに対する欲求を表現できるのか、本当に恐れずに好きな服を着ることができるのか、本当に自由に選ぶことができるのか、現代社会で成功したければ、女性は男性以上に努力する必要があると考える。
SDGsは一種の制度、一種の思想であり、外側から内側への救済。この基盤の上で、私たちはむしろ内部から外部へ、精神的な解放を考えるべきだと思う。言い換えれば、それは暗闇の中に潜む、私たちが直接触れることはできないが、人間の思考世界に影響を与える陳腐な慣習であり、または自分自身ですら当然のように感じている無感覚なものだ。制度的な救済は何百万人もを水から火から救い出すものであり、精神的、意識的な解放は今後の何百万世代もを解放することができる。日本、中国乃至世界中には、私の母、おばあちゃんのような女性がたくさん存在し、さらにはより深刻な不公正な扱いを受けている第三世界の女性もいる。性平等の目標を達成することは物質的な援助ではなく、むしろ意識と意識で闘う。SDGsがすべての人類の問題を十分かつ完璧に解決することはできないが、それにより内面からの推進力は、SDGsがもたらす力をはるかに超えるのではないか。
・塩満 理恵 お茶の水女子大学4年 一人ひとりがジグソーパズルのピース
「ろう者は、障がい者だと思いますか。」
そう問いかけられて、即答することができなかった。
ろう者と聞くと、非ろう者から聞こえを引いた不自由な存在を思い浮かべる人も多いだろう。しかし、ろうの当事者たちは、病理的視点から短絡的に障がい者というラベルを貼られることを望んでいるのだろうか。
大学の授業で、CODA(Children of Deaf Adults、聞こえない親を持つ聞こえる子ども)当事者の方のお話を伺う機会があった。
その方が講演の中で繰り返し強調していたのは、ろう者に対して向ける「障がい者である」という病理的視点を、言語的少数者という社会的文化的視点に転換することの重要性である。つまり、ろう者に対して私たち聴者が無意識に持ってしまう「かわいそうな障がい者」というまなざしを、「手話を使う日本社会の言語的少数者」というまなざしに変えていこうということだ。
日本社会の言語的少数者には、ろう者以外にも様々な属性の人が含まれる。外国にルーツを持つ人々、地方方言やアイヌ語、琉球語などの少数言語の話者などがよく例として挙げられるが、ここに手話を使うろう者たちを加えることによって、耳が聞こえないという彼らが持つ身体的な特徴にばかり注目するのをやめようというのだ。
話を聞いて、実際にろう者が自分たちのアイデンティティーをどう位置付けているのかについて語るインタビュー記事を数本読んだ。聞こえの程度や属性は当事者ごとにそれぞれ違っていたが、「ろう者である自分をかわいそうだとは思わない」という強い気持ちがあることは全員に共通していた。
授業を受けているうちに、ろう者たちが用いる手話言語を、「音声言語を使えない人たちが使う補助的な言語だ」と思い込んでいた自分の偏見に気が付いた。ろう者たちが共有するライフスタイルや言語を包含する幅広い概念である「ろう文化」は、私が想像していたよりもずっと豊かで、長い時間をかけて独自に発展してきたものだった。
「ろう文化」について学んでからは、ろう者たちを障がい者と見なして線を引くのではなく、非ろう者とは異なる文化と言語を持つ人々としてとらえるようになった。障がい者だからと同情するのは、当事者たちが望んでいることではないだろう。これからは、異なる文化の中で生きている人たちとの交流を、旅行や留学の最中に異文化と接するときのように、違うところも同じところも全部まとめて楽しめるようになりたい。
ろう者に限らず、誰も取り残さずすべての人が共生できる社会を作るためには、「勝手に線を引かないこと」が最も重要だと感じる。肌の色、背の高さといった目に見えるところから、自分で定義するジェンダーや、何を信じているかといった一見しただけではわからないところまで。私たちはひとりひとり、似ているところはあっても異なる存在だ。誰もがマジョリティにもマイノリティにもなり得るし、マジョリティになるかマイノリティになるかの基準も時代や場所によって変わる流動的なものだ。だからこそ、自分とは違う人と出会ったときに、「この人はこうだ」「自分とは違う」と線を引いてしまうのではなく、その違いを、社会の多様性を維持するうえで欠かせないジグソーパズルのピースのようにとらえることが大切だと思う。誰しもがこの社会を形作るうえで欠かせないパズルのピースなのだ。
・菊池 隆聖 早稲田大学社会科学部3年 居心地の良い場とは何か
今年の夏、指定難病である潰瘍性大腸炎を患った。生活に大きな支障はないものの、意識や行動等には小さな変化があった。また、私自身、市民農園やコミュニティガーデンからシティズンシップ教育の効果を検証することに関心があり、現地の調査や研究に注力している。これらの持病による変化と自身の興味関心から、誰一人取り残さないとはどのような状態であることが望ましいのか論じる。
まずは、自身の持病と生活からの気づきについて述べる。重症度は軽症にあたり、下痢等が主な症状となる。寿命も変わらないため、大きく精神的な負荷がかかっているわけではない。しかし、些細なことではあるが、診断された後に、生活や社会の見方に変化が生まれたように感じている。例えば、私が若者の世代にあたるため、弱音を言いにくい場面があったことだ。電車で混んでいるときに、席が空いていても座りづらかったり、他の人に迷惑をかけないために誰でもトイレを使用したいが入りづらかったりなどの経験をした。大腸炎の病気のため、外見では辛さを伝えづらい上に、病症によっては相談しにくいこともある。また、軽症のため、学校やバイト先に何か大きな変化を求めるほどの要求はない。しかし、潰瘍性大腸炎によって生じる些細なことが少しづつ精神的な負荷を与えているように感じる。症状が軽いため、大きな支障はないものの、潰瘍性大腸炎というレッテルが自身の考えや行動を制限しているとも捉えられる。自身の経験からの見解であるため、全ての患者が同様の見解を持っているとは限らないが、精神医学が先行するような当事者研究として、自身の考えは示しておきたい。ただし、意識や精神への影響にデメリットのみが生じているわけではない。潰瘍性大腸炎を通じて、難病や障がいを持つ人々の気持ちに寄り添えたり、自身の生活や社会への見方に多様さが生まれたりと、新たな一面を持てたと自負している。
一方、普段は市民農園やコミュニティガーデン等の農の場からシティズンシップ教育の効果を調査することに努めている。農の多面的機能の一つである教育機能とは、多岐にわたる文脈で語られており、その機能にシティズンシップ教育の効果や特徴も持っていないかを調べることを目的としている。シティズンシップ教育はシビックアクション等の文脈より、各主体の「参加」や「行動」することに注目する。教育現場では学校教育等のプログラムを通じて、児童生徒の主体的な活動より、成長や効果を示す。一方、私の研究対象であるコミュニティガーデン等は、いわゆるインフォーマル教育に分類され、何かを教えることを目的とせずも教育機能が生じる現場と考えている。その現場では、参加者が一から関係と場づくりをはじめ、必要な環境を議論等のコミュニケーションを通じて創り上げていく。子ども連れが増えれば遊具を追加するなどの行動は、何か提言したから生まれるというよりも、普段のコミュニケーションや経験からの「気づき」が話題となり、いつの間にか議論を通して行動に移っていく。
このような場の形は、サードプレイスの考えと似ている。オルデンバーグは、家庭や学校、職場以外の場をサードプレイスと定義づけた。明確な定義はないが、誰もが対等で利用しやすい環境はコミュニティガーデン等の農の場とサードプレイスは同様の特徴を示す。オルデンバーグはカフェやバーを対象に論じているが、農の場もどちらも「議論」への参加に抵抗が少ないことが特徴であろう。家庭や職場以外で作り上げた「ゆるいつながり」が、日常生活を通して、いつの間にか何かに気づき、少しずつ変化を起こしていく。この状況における「気づき」といつの間にかという感覚は、マイノリティの人々の精神的負荷を与えづらい。今回の題材である潰瘍性大腸炎等の軽症の難病や障がいの人々の考えも、農の場ではコミュニケーションから気づき、いつの間にか互いにとって居心地の良い場を創り上げている。また、必ずしも農の場でなくても、サードプレイスの特徴を備えた場では、誰一人取り残さないために必要な要素が生じる。ただし、サードプレイスに対する研究は未だ進んでいないことを踏まえ、適切な構築やその要素は何かを調査・検証していく必要性があると考え、社会からの認知と研究等の推進を主張する。
軽症かつマイノリティーに分類される私たちが過ごしやすい環境や社会を創っていくのは難しい。けれども、見過ごしてはいけない人々である上、マイノリティで軽症な人々にとって居心地のよい場の推進や構築には社会が積極的に行わなければならないだろう。その解決策の一つとして、「サードプレイス」の考えの浸透・活用と更なる改善だと考える。コミュニケーションを通して、誰もが居心地の良い場を、皆が主体的に創り上げられる可能性を秘めたサードプレイスは、誰一人取り残さない社会の構築に必要不可欠である。
・小野 亜里沙 会社員 言葉の毒を花束に変えるために。
「今やっと打ち明ける決意ができました。それは僕がゲイであるということです。」そう告げたのはAAAの與真司郎さんだ。今までの自分の葛藤や苦悩を語った動画を見て、私は衝撃を受けた。私は現在私立高校で講師として働いており、自身のセクシャリティについて悩んでいる生徒と接する機会は私自身が想像していた以上に多かった。そして2015年からSDGsが提唱され始めたことで、「多様性を認める」時代になりつつある。男性でもメイクをしたり、女生徒の制服はスカートではなくパンツスタイルも選択できるようになった。私はそのような時代の変化に賛成であるし、自己表現として必要なことだと考えている。そのためもちろん、先述した衝撃とは彼の告白に衝撃を受けたというわけではない。私が衝撃を受けた理由は、その動画に寄せられたコメントの内容だ。「勝手にすればいい」、「イケメンなのにもったいない」などの心ない言葉たちは、おそらく與真司郎さん本人にも届いているのだろう。そのような言葉の刃物をぶつけてしまう人が、「多様性を認める」ことを謳っている現代にまだ多くいるのだということを私は目の当たりにした。
私は「多様性を認める」とは非常に便利な言葉であると感じている。なぜなら、「多様性というなら、私は私の好きにするからそれも多様性として認めてね。」という都合のいい解釈も成立してしまうからだ。しかし、それは本当の意味での「多様性を認める」ことには繋がらない。異なった環境で生きてきた人間が、自分とは違ったものをもつ他者と共に生きていくために歩み寄る、ということが本来の「多様性を認める」ことであり、「誰一人取り残さない」世界だと私は考えている。だからこそ各々が好き勝手に自我を通すことは、SDGsが目指す「誰一人取り残さない」グローバル社会の結果だとは到底思えない。私たちは一人で生きているわけではなく、他者と共に社会の中で生きているのだ。だからこそ、「私は私で勝手にします」という考え方では、周囲との孤立化や少数派の差別化を生んでしまうように感じている。そのため、私たちが本当の意味での「多様性を認め」、「誰一人取り残さない」世界にするためには自分とは違う他者を理解して尊重することが必要だと考える。また、與真司郎さんの告白について、AAAのメンバー末吉秀太さんは自身のSNSでこのようなことを述べている。それは「否定からではなく、理解しようとして認め合える優しい世の中にしていきたいね。」という言葉だ。
以上をふまえて、やはり私は一人一人の少しの勇気や考え方の変化でいつか必ず本当の意味で「多様性を認める」世界に近づいていくことができると考えている。そして、様々な個性を持つ人々と関わることで私自身の視野を広げ、私自身の人生をより深いものにしたいきたいと望んでいる。
・Caytap Jennee 東濃高等学校3年 ありのままの自分を愛する
「太りすぎ」「そのドレスお前に似合ってない」「醜い」
これが、私がSNSや周りの人たちから通常聞いたり読んだりするコメントです。メディアが存在するする社会では人の見た目を馬鹿にしたり、批判したりすることを「ボディーシェイミング」といいます。美の基準を達成することは不可能です。
「美の基準」って一体何だろう。
社会にはすべての性別に異なり基準と期待があると思います。「女性は体毛を持ってならず、白色としないといけない。背が高すぎちゃいけない。」「男性は背が高く、筋肉質で鋭い特徴があり、しっかりしている。」などです。
私は子供の頃よく「太りすぎ」と周りの人からからかわれました。兄妹と比べて肌が黒くて「男子」っぽいことも。このように自分ことをからかわれるような言葉が投げかけられるのを聞く度に私は作り笑いをして話の流れに乗っていました。しかし心の奥底では傷ついていました。メディアに投稿されるのではないかと私は怖かったです。カメラが私に向けられるとすぐに、お腹に吸込み、カメラが私のシワや吹き出物にズームインしないようにしていました。私はあまりに多くの有名人を調べすぎて、彼らのようになりたいと思い、自分を傷つけ続けた多くの女の子の中の一人です。減量に挑戦し、ダイエットにも挑戦しました。自分の見た目を変える為に最善を尽くしました。お腹が空いているのに、食べる量を減らそうとしました。本当の自分を隠して、変えれば変えるほど、他人の言葉が増えました。
しかし私は自分がこのよう変っていた結果には一つも満足していませんでした。誰かの人生や夢を生けているような気がしました。存在はしているけど自分自身がいない。鏡で自分を見る度に、自分は幸せなのかと自問しました。
「Be yourself」と姉が私に言いました。その言葉を聞いた瞬間にこの自分が必死に変えるのを誰のためなのか疑問に思いました。それに気付き、少しずつ好きなことをやりながらself-care の練習に頑張りました。一歩一歩自分のために変わりたいです。
ソーシャルメディアが進歩につれて、世界中の情報が自由に手入れるようになりました。それによってニュースが共有され、素晴らしいアイデアが世界に広まりました。しかし、悪意のある人の手に渡ることによりメディアは個人のレベルと社会のレベルの両方で甚大な破壊を引き起こす可能性が高まりました。ボディーシェイミングは虐めの発端として世界中の人々や文化に損害を与えています。例えば、2018年2月12月のBBCのニュースによるとモデルであるジジのハディッドも細すぎるなどという人が多いでした。しかし彼女は批判のためではなく自分の為にLove your selfと言いました。世界で活躍されている人はが、理想的な体型外見に左右されず「ボディーポジティブ」であることを主張しました。これをメディアで見たとき、私は嬉しくなりました。
私は「本物の女性」とは疑問だった。それはごく自然なありのままの「女性」を表現している言葉だからです。私は、肌の色、身長、体重、体のサイズ、顔の特徴など、メディアの多様性を更に高める必要があると思います。身体がメディアに左右されたコントロールの対象ではなく自分の性別や性的アイデンティティーを安全安心に表現できるあらゆるメディアの形態の平等に向けて取り組む必要あると思います。
私は、個人はそれぞれ異なり、個人の好きなことを尊重し、自分自身の最高のモチベーションであって自分の為に正しいことすることが大切だと思います。ボディーシェイミングは消えることがないですが小さな変化から始めることができると信じています。すべての人が自分のありのままの体を愛せるように、今後もさらにボディーポジティブがもっと世界に広まるにまずは私から発信したいです。
・川井 和 長崎県立諫早高等学校2年 「当たり前」を超えた先に
「誰ひとり取り残さないために」私がこのコンテストと出会ったのは Instagram だった。始めは正直、興味なんてなかった。しかし、今どうしてもみんなに伝えたいことができた。だから、コンテストに応募することにした。
私が小学生6年生のころ修学旅行で「わぁ!朝ご飯だ!」と喜んでいる子がいた。それが私の中の「当たり前」を超えた瞬間だった。どうもその子は朝ご飯を毎日食べていないらしい。 その子はいつも帰ったらご飯を作って、洗濯物をして、皿洗いをして…と家事全般をしていると言っていた。 私にとって朝ご飯を食べる、家事をしないというのが「当たり前」だった。しかし、その子にとって家事をしたり、一人で食事をしたりするのは「当たり前」だった。
私が子ども食堂を開催したりお手伝いに行ったりするようになったのはこの経験があった
からだ。小学生の時も中学生の時も私はその子に何もしてあげられなかった。そして、何もできないまま中学校を卒業し疎遠になった。高校に入ると彼のような子がたくさんいることを知った。私はそんな子達の少しでも救いになれば良いなと思い活動を始めた。
話は変わるが、私はアセクシャルだ。つまり恋愛に興味がない。小・中学生の時は打ち明けることもなくすことができた。しかし、つい先日後輩から「好きな人いないんですか?」と聞かれたとき「興味ないんだよね。」と答えると「薄情ですね」と言われた。その時初めて普通ではないことに気づき、取り残されたように感じた。みんなにとって誰かを好きになるというのは「当たり前」かもしれない。しかし、私にとって誰かを好きになるというのは今までの自分の「当たり前」を超えたものだった、
「誰一人取り残さない」ということの一番難しい点は誰もが自分の置かれた状況を「当たり前」だと思い込んでいるところにあると思う。 だから、取り残されていることに気が付かない。私はこの問題を解決するためにはコミュニケーションや経験が重要だと考える。私自身、活動を通していろんな人に出会い、たくさんの経験をさせていただいた。そして、活動を通じてセクシャルマイノリティの人にも出会うことができた。そして、その人がたくさん話を聞いてくれて、「気にしなくていいよ。思っている以上に仲間いるんだよ」って言ってくれたことが私にとってすごく救いになった。今では恋バナも苦ではなくなった。子ども食堂やフードバンクに来る子の中にはみんなとご飯を食べるなど人と交流する機会が今までなかったというような子もいる。また、本当に困っている人たちの中には相談する人がいない、誰に言っていいのか分からないという人がいる。そんな人たちも巻き込んだコミュニケーションの場を作りたい。そうすることで自分の置かれた状況を理解し、仲間や助けてくれる人と出会い、改善に向けて行動ができると考えた。今、私は 2 つのことに取り組もうとしている。 1 つ目は子ども食堂同士をつなげること。もう一つは食べるるはだけでは終わらない誰もが来やすい子ども食堂を開催することだ。世の中は「当たり前」であふれている。私にとっての「当たり前」は誰かにとって特別かもしれない。たくさんの「当たり前」に出会い、理解してきた。そのことが私にとっての救いにつながった。自分の「あたりまえ」を超え、人とは少し違うことに気づくのも、それを問題に思ったときに解決するのも出会いや経験だと思う。 その中で他人を知り自分を見つめなおす。そして解決する。どんな人でも自分の「当たり前」を超える出会いや経験をできる環境を作っていきたい。私が救われたようにひとりひとりをを知り、寄り添う。そんなことが出来る人になりたい。そんな活動をしたい。あなたの「当たり前」を超えた先には何がありますか?
・吉田 莉恩 人間総合科学大学1年 すべての声に耳を傾けて
「一人でもいいから、誰かに理解してほしい」そんな風に考えたことは誰しもあるだろう。自分が困難な壁に直面したとき、心が負の気持ちに包まれたとき、マイノリティーな存在になったとき、他者からの理解や支えは欠かせない。「だれひとり取り残さない」というのは、「誰かの理解を得たい」という声に耳を傾けることではないかと考える。環境問題、教育問題、そういった大きな括りで社会課題を見ると、解決策を考えることはとても難しく感じる。しかし、問題の根源にあるのは課題そのものではなく、課題によって苦しむ人々の存在である。
「誰かの理解を得たい」という気持ちとその気持ちを理解してもらえる場面は、私たちの日常生活には数多く存在する。学生の身近な例を挙げると、勉強をしていてモチベーションが保てなかったり、集中が続かなくなったりしたとき、学校やインターネット上に、そのような状況を理解してくれる人、その対処法を教えてくれる人がいる。そして、抱える問題との向き合い方を自分なりに見つけることもできる。しかし、モチベーションは保てて当たり前、集中力が続いて当たり前、そんな状況が普遍的であったとすれば、勉強に対する悩みを安易に人に相談することができるだろうか。また、その問題に一人で対処できるだろうか。それはとても難しく、大きな壁のように感じると思う。そんなときに、自分の状況を理解してくれる存在がいれば、きっと大きな支えとなり、前に進む力に変わるはずである。理解しようとしてくれる存在、それは私たちが生きていく過程に欠かせないものであると考える。私は、そのことを深く実感する経験をした。
私は高校2年生の秋ごろ、メンタルヘルスの悪化により、日常生活を送ることが難しくなった。食事を取ることや眠ること、勉強すること、人と話すこと、当たり前にできていたことが、当たり前にできなくなってしまった。同じ状況に置かれた人が身近にいない中で、誰に相談すれば良いのかわからず、自分でどう対処すれば良いのかも全く分からなかった。毎日学校に行き、授業を受け、課題に取り組む、その全てがとても高い壁に感じていた。しかし、丁度その時期は、受験生として当たり前のことを当たり前にこなすことが求められる時期であった。学校で失望されることを恐れ、同級生と同じように振舞う日々が、とても苦しく逃げ出したかった。日に日に孤独感が増し、ひとり別世界にいるかのように感じるようになったころ、「どうしたら良いのかわからない、誰かに理解してほしい」その私の声に耳を傾けてくれた存在があった。それは学校の先生方である。私の声を聴き、できなくても頑張ろうとしている姿勢を認め、私の抱える問題を理解しようとしてくれる、それが私にとって大きな支えとなり、高校卒業まで頑張りきることができた。理解してくれる存在を実感したことで、孤独も軽減され、どうにか対処していこうと前に進むことができたのだ。これは、ひとりだと感じていた私が、ひとりではないと思えた経験である。
私はこの経験から、抱える問題を理解しようとしてくれる存在は、孤独に苛まれているときに安心感を与え、解決への一歩に導くと実感した。解決することだけが重要なのではなく、声に耳を傾けて受け止めること、そして理解しようとすることも、大きな力を持っていると考える。元気そうに、楽しそうに見えるけれど、外見だけではわからない孤独や苦しさを抱え、「誰かに理解してほしい」と声を上げている人もいる。その声は時に小さく、見逃してしまいがちだが、どんなに小さかったとしても、私はその声に気づき、手を差し伸べられるようになりたい。そのために、単なる先入観や目に見える形だけで考えるのではなく、日々の生活の中で、あらゆる視点から人や物事を捉えていきたいと思う。そしてこれは、社会課題にも通ずることである。多くの社会課題において、問題を抱える当事者の視点を大切にせず、課題そのものだけを見て解決策を探っても、それは時に善意が転じて災いになることもあるかもしれないからだ。
「誰かの理解を得たい」という気持ちを持つ理由に、抱える問題の大小は関係ない。小さなことでも大きなことでも、その声に耳を傾ける人が増えていくことで、誰ひとり取り残さない世界に近づいていけると考える。すべての声が誰かの耳に届きますように。
・本馬 愛美 富山大学 3年 『日本人』クリスチャンとして生きる
『宗教』と聞くと、多くの日本人は何を思うだろうか。カルト、危なそうなもの、自分とは世界が違うもの、お金をとられる場など、基本は悪いイメージが先行する。日本人は宗教に対して忌避感が強い。しかし、本当に宗教は悪いものなのだろうか。私は生まれたときからクリスチャンホームの中で生きてきて、様々なことを経験し、学んだ。客観的に日本人の宗教観を見てきた私の経験から、宗教の本当に持たれるべき考え方を伝えていきたい。
多くの日本人が持つ宗教のイメージは悪いものである。しかし、自民党と統一教会の不祥事、カルト団体による家庭崩壊等、これらのイメージは主にメディアから来るものがほとんどだ。ここで少し考えてみてほしい。もし日常生活の中で『悪いこと』をしたら、何が起こる?年末年始はどこに行く?恐らく思い浮かんだことは、悪いことをしたら「バチが当たる」、年末年始には「神社・寺に行く」ではないだろうか。きっとそれが普通だ。しかしこれは、我々多くの日本人が触れている神道もしくは仏教から来る教えである。これでも宗教は悪いものといえるだろうか。宗教と文化は非常に密接に関わっている。ゆえに日本人は当たり前に存在している仏教と神道を『信仰』している。言い方を変えると、信仰を『強制』させられているのではないだろうか。私は、日本で生まれ、日本で育った。しかし多くの日本人と違う点は、クリスチャンホームであったことである。生まれてから小学生の時まで、毎週日曜日に教会に通っていた。クリスチャン、もしくはクリスチャンではない人、いろいろな人が集まって聖書を楽しく学び、交流をしていた。私はその場が大好きだったし、小学生ながら教会に興味がある友達をよく誘って一緒に教会へ行った。しかし、中学生になり思春期という精神的に難しい時期になってから教会に行くことをやめた。やめてから気づいたことは、日本人は自分自身のことを無宗教といいながら、神社や寺には行くし、お祈りだってする。クリスマスの行事にも参加する。当時の私には不思議で、みんなが結局何を信じていて、何に祈っているのかよく分からなかった。私はアメリカに1年間留学し、そこで出会ったアメリカ人や日本人ではない他の国の人たちに私がクリスチャンであるというと、大体は自分もクリスチャンである、もしくは他宗教を信仰していると言う。残りの人は、ライトな信者であったり、まだ模索中と言っていたりする。無宗教であると言う人は、今まで私が会ってきた人たちの中で、日本人以外だれもいなかったのである。無宗教であると言う数人の日本人の友達に、なぜ神社や寺に行って祈るのかを聞いたことがある。彼らは、「何となく」、もしくは「神頼みをするために」と言っていた。無宗教であるといいながら、『神頼み』をしている。彼らが神を信じていることは明らかであるのに、全く気づいていない。このような曖昧な宗教観を持つ日本人の中でクリスチャンといて生きていくことは非常に苦難であったし、今でも苦しい。なぜなら、多くの人が理解を示さないからだ。特に田舎にいくとそれが顕著である。異端者として見られ、彼らとの関係性に線を一方的に引かれてしまう。しかし日本人以外で他宗教の人と出会うと、日本人は理解しようとする。他宗教を信仰する日本人には仏教や神道を強制させ、「外国人」は受け入れようとする。私の地元でこのような理不尽にあったことがあり、とても生きづらかった覚えがある。むしろアメリカの生活の方がクリスチャンとして生きやすかった。
信仰している『宗教』があるだけで日本では生きづらさを感じる原因は、他者からの理解が得られないことであると考える。日本では、『宗教』という言葉が一人歩きし、触れてはならないものと考えられているのかもしれない。しかし、本来宗教とは人が救われるためにあるものである。例えば、あなたが面白い本に出会ったとする。するとあなたはそれが『いいもの』だから他人に勧めたくなるのではないだろうか。宗教も同じである。自分が『いいもの』と思うから他者に勧める。そして進められている人にはそれを選ぶ権利がある。求めるならば与える。同じクリスチャンでも人によって解釈が違う可能性があるが、これが私なりに解釈しているキリスト教の言葉にある『福音』である。幸い、日本は信仰の自由が許されている国である。一人一人が宗教を知り、理解を示すことで、『何となく』そこにあった宗教というものが、視野を広げる『面白い』ものになり、本当の多様性が認められる社会になると、私は祈っている。
・宮澤 正虎 成城学園高等学校1年 性別に囚われず自分らしく生きるために
多様性の時代。最近耳慣れた言葉だと思う。テレビを見れば、本を読めば、たくさん目にする。僕の周りでは「まぁ多様性の時代だからね(笑)」と小馬鹿にした感じで使われることもある。だが多様性、ダイバーシティの考え方が日本で認識され男女差別を是正するための法律が次々と制定され始めたのは、1980年〜1990年代にかけてと言われている。職場における男女の雇用問題、さらには「男女共同参画社会基本法」が制定され、企業において男女の人権を尊重することが義務化された。これに伴い、昔に比べたら、「企業の差別(表の面)」での差別化は明らかに減っている。他方で「日常生活における差別(裏の面)」は減っていないと僕は考える。
このように考えるようになったきっかけは、僕が12年間続けているサッカーである。小さい頃の自分は、何となくサッカーは男子がやるものだと思っていたが、なでしこジャパンがW杯で優勝したのをテレビで見て、女子のサッカーもあるんだと知った。男性の試合では一瞬で事が起き、卓越したテクニックで一気に勝敗が決するスピード感と臨場感が見る人を惹きつける。女性の場合は男性に比べスピードが劣る分、ボールを持たない選手の動きや、選手同士の連動など、チームの戦術を時差なく自らの視点として見つけることが出来る楽しさがあると思う。そんな僕は、サッカーを始めて数年たった小学校低学年の時、女子のサッカーチームがグラウンドから爪弾きにされているのを見た。その頃の僕は、「女子がグラウンド使ってても自分たちが来たら退いてくれるんだラッキー」と思って使っていた。さらに数年、高学年次に、再びその現場を眼前にした際、やにわに疑問が浮かんだ。なぜ性が異なるだけで優劣がつけられるのだろう。そもそもスポーツに男も女も関係ないのに偏見が存在するのは何故だろう。
きっかけは他にもあった。小学生の時、学校に髪の毛を短く切っていて、いつもズボンを履いている女の子がいた。一方周りの女子は皆長い髪をして、スカートを履き、俗に言う””女の子らしい””格好をしていた。そのため、その子は「あ、男だー」「おかまだー」などとよく弄されていた。「女子=髪が長い。スカートを履く。」という偏見があったのだろう。僕にはその感覚がわからなかったが、何もする事ができない自分を情けなく感じたことを良く覚えている。
上記では男女差別に関する実体験を述べてきた。しかし自分の周りだけの問題ではなく、相似的な事は世界各地、僕たちが普段知ることの無い遠景の中でも起こっている。最近の出来事でも男女差別が顕著な一例がある。男子は2020年、女子は2023年にサッカーW杯が行われた。ここで問題視されたのは男女間格差の問題だ。具体的には出場国、優勝国への賞金、グラウンド整備や準備に使われた価格の圧倒的差異である。数字で表すと、女子の賞金総額は3000万ドル(32億6000万)なのに対して、男子賞金総額は4億ドル(434億4000万)であった。つまるところ10倍以上だ。この資金格差は女子サッカー界に様々な波紋を広げている。男子と比べて、圧倒的に少ない資金による競技環境の下落、スポンサー料や所属チームからの給与の低さ、協会や連盟から払われる給与への依存度の上昇など深刻な問題が多々ある。実際に、男女差別に関する探究活動を進めていく中で出会ったとある大学教授は女性の方で、昔からサッカーをやっており、弁別を身をもって体験したそうだ。親に、女の子なんだからサッカーなんてやるなと否定されたり、サッカーをやる上で髪の毛が邪魔だったので短くしていたら、生徒だけでなく先生にも男と言われたと陳じてくれた。大学ではそれを議題として生徒たちと議論していると言う。教授の話を聞いて、尚更このままではいけないと痛感した。
先述してきたように、昔に比べ、男女差別は減ってきてはいるが、無くなっていないのも事実である。僕はこれを0にしたい。確かに、どう感じるかその人をどう見るかなんて自分次第だ。とは言え周りが、環境が、各個人が「男女の偏見はおかしい」と皆がこのような結論に辿り着けるように促進していく事は可能だと思う。いずれ世界から男女の偏見、差別を無くし、皆が周りの目を気にせずにありのままの自分でいられる世界を作ることが僕の夢である。その目標達成のために、本を読んで知識を広げたり、SDGSゴール5「ジェンダー平等を実現」に向けて取り組みをしている企業や教授にお話を伺ったりして、自分なりに学びを深めてきた。まだまだやらなければならない事はたくさんあるため、これからも問題解決に向けて様々なアクションを起こし、夢を叶えたい。
・髙野 春奈 宮城県名取高等学校 3年 ありのままで
女性だから男性だからと性別によって格差が生まれる社会を変えていく必要がある。性別によって区別されることなく平等に、暮らすことのできる社会を実現していくことが今の日本には必要だ。実際に、2023年の日本のジェンダー平等指数は146カ国中125位で過去最低で、主要先進国の中でも最下位と、とても低い順位であることが分かる。その中でも、特に政治や経済の部門におけるジェンダー平等が課題となっている。このような現状を踏まえて、性別にとらわれることなく誰しもが活躍できる社会を目指していくべきだと考える。
学校生活では校則によってメイクをすることはほとんどの学校で禁止されている。しかし、私は少しでもコンプレックスを隠したいと思う気持ちや自分に自信を持ちたいと思う気持ちから、バレないようにメイクを行ってきた。メイクをすることで少しでも自分に自信を持て学校生活が送れているような気がした。当然、メイクをしていることがバレてしまった人がいたのなら落とすように言われていた。しかし、その光景を見た私は、どうしてメイクをしている大人に言われなければいけないのだろうと反発心を持った。メイクをすることを禁止するので、あれば大人である先生方もメイクを禁止すれば良いのではないかと思ってしまった。
一方で、社会人として社会に出れば、メイクをすることはマナーとされ、メイクをしなければマナー違反と言われてしまう。当然メイクをしたくない日もあるし、肌荒れが気になる日はメイクをすることを控えたいと思う日だってある。メイクをしたくなくてもマナー的にしなければいけないという風潮があることが分かり、先生方もメイクをしたくくてしている訳ではないかもしれないと言うことが分かった。
メイクをすることを禁止されたり、メイクをすることをマナーとされてしまったりすることに対応しきれないのではないだろうか。メイクが上手くなるにはある程度の時間がかかるし、当然お金もかかる。私は、メイクをすることは自分のモチベーションを上げるために行ったり、自分のために行ったりすることだと考えている。誰かに強制させられて行うことではないと考える。そのため、いつメイクをしてもメイクをするの有無も個人の自由であるべきだと考える。
私が、授業の一環で行ったメイクに関する調査では30名の高校生に「社会生活においてメイクは必要かどうか」という質問を行った。調査結果は、80パーセントの高校生が社会生活においてメイクは必要であると回答した。メイクをすることは清潔感がある、社会人として必要なことだから、身だしなみマナーであると教わったなどという理由が挙げられた。一方で、社会生活においてメイクは必要でないと回答した20パーセントの高校生は、メイクをするをしないも自由である、固定概念として浸透してしまっているがメイクをするしないはその人の個性や考えがあると思うという意見が挙げられた。やはり、メイクはマナーであるということが社会に固定概念として定着してしまっていることが伺えた。高校生の私たちさえも女性は社会に出たら、メイクをしなければいけないと思っていることが分かり、このような固定概念が広く定着してしまっていると感じた。
社会に出てたら、男性のすっぴんは良しとされるのに、女性のすっぴんはマナー違反されていまうことに反対だ。女性は仕事のためにメイクをする必要があるのだろうか。他者に顔を見せて仕事をすることは男性も同様であるのに、ありのままの姿ではいけないのだろうか、女性はこうあるべきだ、こうすべきだという社会的風潮に納得がいかない。たしかに、ある程度の身だしなみは社会人として必要ことであると思う。身だしなみを整えることで清潔感が生まれ
相手に与える印象も良いのだと思う。しかし、メイクをすることまでも身だしなみの一環として扱うのならば女性のすっぴんは清潔感がなく、ありのままよ姿ではいけないと言われいるような気がしてならない。
女性はメイクをすることがマナーであるという固定概念があるように、性別によって区別し、何かをほぼ強制するような社会にしてはいけない。考え方は人それぞれでそれはその人の個性である。性別によって生まれる固定概念を無くし、それはその人個性であるということを十分に理解し、個人の自由として尊重していくべきだと考える。そうすることで性別関係なく誰しもが活躍することのできる社会になるだろう。
・大西 花音 神戸松蔭女子学院大学4年 性別を悪にしてはいないだろうか
性別なんて無くなってしまえば良いのに。
それが私の意見だった。自分の性別に違和感があった訳ではない。それでも私にとって性別はとても邪魔な存在だったのだ。小さい頃から女性アイドルやスーパーヒーローが好きだった。好きな理由に性別など関係が無いはずだ。それなのに。
「もしかして女の子が好きなの?」
「女の子なのにそれ好きなの?」
今でこそ同性を応援することも当たり前になってきているし誰が何を好きであろうと良い風潮になってきてはいるが、幼い頃に自分や他人に向けられた言葉によって、性別で決めつけられることに対する嫌悪感を抱き続けていた。皆が性別を考えずに生きることが出来る世界になって欲しいと心から願っていた。
「やっと女の子として生きていくことが出来ます」
ある日SNSを見ていた私の目に、可愛いという言葉を具現化したような写真が目に留まった。その人は男性として生まれたが、どうしても女性として生きたい想いからお金を貯めて性転換手術を受けたという。よく頑張ったね、祝福のコメントが並ぶ画面をスクロールしながら、私は衝撃を受け止めるのに精一杯だった。性別なんて無くなってしまえば良いと思っていた。性別なんてない方が皆幸せになれるのではないかと思っていた。
違う。
私は性別によって決めつけられることが嫌だったはずなのに、いつの間にか性別そのものを悪にしてしまっていたのだ。そして無意識のうちに、「性別を持って生きたい人」の存在を取り残してしまっていたのである。
その出来事をきっかけとして、私はジェンダーについて興味を持つようになった。関連する講義に参加したり本を読んだりした。するとジェンダーレスという言葉に違和感を持つようになった。目指すべきなのは、どちらかというとジェンダーフリーな社会なのでは無いだろうか。
今LGBT法が話題になっているが、批判の声が多く聞こえてくる。それはジェンダーレスを主軸にしているからでは無いかと考える。性別を無くそうとするジェンダーレスの考え方は、以前の私のように見方によっては性別を悪にしてはいないだろうか。
性別を無くそうとする考え方を突き詰めるとどうなってしまうのか考えてみた。まず男性として女性として生きたい人が生き辛い、生き難い社会になるだろう。そして、1番問題視されているのが性犯罪である。例えばトイレを性別の区別無く共用にしてしまえば、安心して利用出来ないという意見が多く挙げられている。特に女性が性犯罪に巻き込まれる危険性が高くなるのではという懸念からだ。この件において私は、女性はこうだ、男性がどうだという決めつけでは無いと考える。客観的な事実として、身体の性別によって体格差、力の差が大きい。心の中まで決めつけている訳では無く、人を守る為の区別だと捉えることが出来るからだ。ルールというものは、基本的に誰かを守る為や傷付く人を出来る限り減らす為に定められている。性別を無くすことに固執するあまり、何故そのルールや仕組みが存在してきたのかを考えることを放棄してはいないだろうか。考えれば考える程、平等を求めて区別を全く無くしてしまうことは本当に全員が幸せになる方法なのか疑問が大きくなる。
このように私は、誰も取り残さない為には性別を悪にしないように注意すること、誰かを守るための区別を差別と混同しないことが必要であると考えている。性別を無くすのではなく、性別に囚われずに生きたい人、男性として生きたい人、女性として生きたい人が皆お互いを尊重出来る社会になることを望みたい。そして私自身も無意識のうちに自分だけの価値観に閉じ込められないように、多様な意見を取り入れて考えて続けていきたい。
・山中 このみ 静岡県立藤枝東高等学校 2年 あなたは他人より劣っている点はありますか?
あなたは他人より劣っている点はありますか?
この質問に対し、多くの人は小さな声で「はい」と答えるでしょう。
私は他人より劣っているところだらけです。中学受験には落ちましたし、今通う高校では散々んな成績を取っているし、3年付き合った彼氏には振られたばっかりだし…。
中学受験に落ちてしまった私は中学3年間、合格した人と差がどんどん開かれていく焦燥感に駆られていました。静岡に生まれた時点で東京の子達とはずっと差が開かれている。こんなところで滑る訳には行かなかったのに…。そんなふうに思っていました。
しかし、中学時代の私が常に取り残されているように感じていたかと聞かれればそうではありませんでした。むしろその逆かもしれません。自分で言うのもなんですが、中学受験のために勉強してきた私は受験をしなかった子達と比べ成績が良かったのです。そのため同じクラス、同じ学校内では上位層に属していました。「もっと早く授業を進めて欲しい。」「もっと応用問題を取り扱って欲しい。」自分がとてもできる人間のように思えていました。夜遅くまで勉強する必要もなく、心身共に余裕のある生活を送っていました。そして、次こそは必ず合格すると心に決め、挑んだ高校受験で、私は合格を掴み取りました。
しかしそこでの生活は私の想像するものとは、かけ離れたものでした。学校の授業が分からない。課題が期限内に提出できない。単元テストは追試ばかり。ここで初めて気が付きました。私は中学時代、授業においてクラスメイトを取り残してしまっていたのだと。そして私は劣っている人間なのだと。今、私は取り残されているのだと。
そんなことを感じていた私に希望の光を投げかけてくれたのはある人の言葉です。オリエンタルラジオの中田敦彦さん。彼はこう言いました。“優れるな、異なれ”彼が言うにはコンプレックスは才能の裏返しなのだ。人と違っていること=劣っているのではなく、それを才能として見ることができるのではないかと。他人と違う行動をすることは勇気のいることだけど、それは新しい道を切り開く可能性を秘めた行為である。
努力すればするほど、上位の学校に入れば入るほど私は取り残される。取り残す側にいた時の私は、余裕のある生活をしていて、取り残された人の存在にすら気づかなかった。これはどの人についても共通して言えることだと思う。人は今現在属している集団の中で優劣をつけ差別をしたり、自分や他人にレッテルを貼ったりする。しかし属する集団が変わればその立場は一気に逆転することもある。私は初め、取り残される側になりたくなければ属する集団を変えれば良いのではないかと考えていました。しかしながら考えるうちにそう簡単なことでは無いと思うようになりました。
私が日本人であること、女だという集団に属していること、これらは簡単に変えることは出来ません。では取り残されてしまう人をなくすためにはどうしたら良いのでしょうか?
解決策の1つとしては、取り残す側が1度立ち止まって後ろを振り返ることにあると思います。今彼らは余裕のある生活をしているのだから。その余裕を少しだけでも、分け合えば良いのです。しかしながらこれでは取り残されてしまった人自身はどうすることも出来ないということになってしまいます。
本当にそうなのでしょうか?助けてくれる人、親切にしてくれる人は、確かにこの世界に沢山います。しかし、たまたま運悪く良い人に出会えない時、出会えない環境に置かれることもあります。では、そんな時どうしたら良いのか。私が出した答えは、“集団を作ること”です。集団になった時、初めて大きな発言力を持ちます。発言力を持った時、初めて社会が動きます。社会が動いた時、初めて取り残させる人がいなくなります。
しかし、これはあくまで私が考える解決策です。解決策は1つではありません。問題は様々な種類があるのだから、1つの手段で解決しようとする方が不可能です。ただ、1つだけ言えるのは“自分だけ人より劣っているということは絶対にない“ということです。皆それぞれコンプレックスを持っています。しかしそれは才能の裏返しです。失敗のその先にある成功を掴めたとしたら、最初の失敗は成功への過程です。私が他人より劣っていると感じていたことは、経験という私の財産です。中学受験に落ちたからこそ、受験の厳しさを知り、高校受験に本気になれました。今、学校の授業についていけない経験をしているからこそ、勉強を苦手とする子の気持ちがわかるようになりました。失恋も私の青春を彩ってくれた1ページです。
あなたは他人より劣っている点はありますか?
今の私なら自信を持って答えられます。
「はい」と。
・阿部 真彩 日本大学芸術学部 優しさの責任
差別のない平等な世の中というのは、差別を受けていない人が声を大にして言っている印象が拭えないのは私だけだろうか。私の弟はかなり重めの色育で、ADHDでもある。彼は小学校低学年まで何も周りとの違いを感じずにいた。しかし、周りとの違いを感じた当時の担任の先生からの提案で検査を受けたところこのような結果が出たのだ。そしてそこから私の弟は先生から過度な特別扱いをされるようになった。この先生はもちろん優しさで行動してくれたのだ。しかし弟は周りと違うことを意識するようになり劣等感でどんどん内気になっていった。差別を認識することさえ差別なのでは、と疑ってしまうようになった今日この頃。
考え方がこれまでの何倍も増え、そしてそれが認められる社会に変化している。多様性という言葉が浸透していき今まで差別だと思っていた考え方や行動も多様性の一部になっていたりする。だから、私は安易に差別を認識しそれに想いを馳せることが正しいのか分からなくなってしまった。今回のテーマの誰一人取り残さないという文言ももちろん救う側の言葉なのである。誰も見捨てたくないけど、善意で誰かを傷つけるのは嫌だ。私の優しさで誰かに劣等感を感じさせてしまう可能性もある。だから、誰かを救うという行為は100%の善意で行わなければならないのだ。見返りや優越感に浸ることが目的化した善意は時に人を傷つける。私たちは行動に全て責任を持たなくてはいけないのだ。話が外れてしまったが、「行動に責任をもつこと」が誰一人取り残さないことに繋がると考える。優しさはもちろん、私たちがこれからsdgsを意識し行動する機会があるとする。その時も救いたい誰か、救わなければならない誰かの為に行動するのだ。その行動は、優しさは自分のためになっていないかだろうか。誰しも全て人のためと思って行動するのは難しいと思う。しかし、それができる人が増えなければ誰一人取りこぼさない社会は実現しないのだ。誰一人取りこぼさないという言葉はきれいごとではあるが、それをきれいごとに終わらせるか実現させるかは私たちにかかっている。
・跡部 奏真 秋田大学 2年 内面に耳をすまして
以前、僕は大学で取り残されていると感じていました。なぜなら、発達障害を持っていて目立ってしまうからです。
高校生くらいになると心の発達が進み、その発達に遅れてしまう人が浮き彫りになれば、次第にレールから外れていきます。そのため、進学とともにコミュニティ内における定型発達の人が占める割合が必然的に多くなり、僕のような発達障害を持つ人はふるいにかけられることになります。よって、大学という閉鎖的なコミュニティでは発達障害を持つ人が目立ちやすくなるのです。
大学に入学したのは良いものの、馴染むことができず、疎外感がつきまといます。単位をとるためには同級生との交流が欠かせません。グループワークや実習など、誰かと協力する場面が多く、受ける授業もさまざまです。それにより、定期的に決まった人とペアを組んでいれば良いというわけではなく、流動的かつ普遍的なコミュニケーションが求められる機会が多くなります。通信制高校に通っていたために、三年間ほとんど同級生とのコミュニケーションがなかった僕は、大学という流動性の大きい舞台に飛び込んで、情報の海に溺れてしまいました。
大学では、僕の服装や振る舞いについて偏見を持たれたり、自分という存在を変わっていると言われたり、周りが何も言わない場面で堂々と発言するとそれを奇行だと言われたり、学生に目をつけられ、行動や言動を晒されたりしたことがあります。
発達障害があるから、変わっていることは仕方がないのことなのに、どうしてこんなにも、自分は他人に何かを言われなくてはならないのだろうということが、大学に入って一年半くらい続いた大きな悩みでした。
そして、人に何かを言われるたびに、純な自分は濁っていき、やがて率先して変わり者を演じなくてはならないという衝動に駆られることになりました。
しかし、色んな人からの言葉で気づいたことがあります。
それは、まずは自分から相手を知ろうとすれば、相手も受け入れやすいということ、次に、全員から好かれるのは無理だから、僕を拒絶する人もいて当然だということ、そして、障害を持っているからと、自分が卑屈になってしまえば取り残されたままになってしまうということです。
これらの気づきから、自分の障害の中で工夫できるところを見出すことができました。すると、自分の考え方が変わり、特性はそのままでも生きにくさが減り、取り残されていると感じることが少なくなりました。
良くも悪くも自分が変わっているというのは事実です。そのため、目立ってしまうときがあるのは当然のことです。取り残される場合もあると思います。一口に発達障害と言ったとしても、特性は十人十色だからです。
ただ、発達障害だから自分が変わっているのではありません。自分が目立つ特性を持っているから発達障害と区分されているだけなのです。つまり、定型発達の人にも同じことが言えます。目に見えない何かを定型発達の人も背負っているのです。家庭環境然り、生活水準然り、人は何かしら考えながら生きています。さらに、感受性と価値観は、人の数だけ存在します。
だから、コミュニティで目立つ僕だけが特別なわけではないのです。人間はみな、目に見えない何かを抱えているかもしれない。そう考えて、相手の話を聴いて寄り添ってみる。人の発言の心意と背景を、まずは僕から考えてみる。そうすることで、取り残されていると感じることがかなり減りました。僕としては、多数派は少数派を、少数派は多数派を相互扶助的に尊重しあうのが大事なのだと感じます。また、名前が付けられる区分のみで判別せずに、多数派や、少数派といった外面ではなく、その集団に所属する個人の内面を聴きあうことが大事だと思います。
最後に、僕にとって心地良かった方法や工夫が、全ての人に適切だとは限りません。だからこそ、自分と異なる人のことを、多数派や少数派といったフィルターを無視したうえで、受け止めて聴いていきたいです。
・山田 優杏 成立学園高等学校 取り残されることを恐れない自分になるために
誰一人取り残さない、そんな社会が実現する日は来るのだろうか。誰一人取り残されない社会にするために私たちには何ができるのだろうか。1人1人が自分だけでなく周りに配慮すれば実現できる?それは不可能だろう。そもそも私自身、自分が取り残されないために必死だからだ。私は、自分がみんなの輪から取り残されるのが嫌でいつも人に合わせてばかりいる。昔から気が弱く見られやすいのか、周りからなめられたり、標的にされやすかった。いつからか、人の目ばかり気にして、自分の思ったことを素直に言えなくなっていた。どうすれば1人にならないか、どうすればみんなの輪から取り残されないか、そんなことばかり考えていた。中学の頃、自分のしてしまったことが原因で1人になってしまった子がいる。私はその子と仲の良い方だった。グループになる場面でその子は私のグループに入ってもいいか声をかけてくれた。いいよ、そう言いたかった。でもその子を輪に入れたくないという周りの悪い空気を読み、「他のところって空いてたりしないのかな」そう言ってしまった。ここで入れたら後で陰口を言われるのではないか、1人だけ取り残されてしまうのではないか、自分が1人になるのが怖くてその子を1人にしたのだ。今でもすごく後悔している。その子が周りから悪い印象を持たれていたとしてもそれを1人にしていい理由になんてならない。だいたい、私がその子を輪に入れたとして、本当に私はみんなから取り残されるのだろうか。確証もないくせに自分で決めつけているだけなのではないだろうか。もし取り残されたとしてそれを友達と言えるのだろうか。それが原因で取り残されるくらいならその程度の友達ということだ。そう思えば、あの時私はあの子を1人にすることはなかったかもしれない。逆に私と同じ思いをしている友達もいたかもしれない。私は私と同じように周りの空気を読み、自分の思ったことが言えない、できない人に伝えたい。世の中には絶対自分の気持ちをわかってくれる人がいる、と。世の中には何億もの人がいて、人種、言語、見た目、多種多様な世界だけど、自分と同じ価値観をもっている人は絶対いる。100人の人に、スイカとメロンどちらが好きかアンケートをとるとする。票数に違いは出るが、選ばれるものがどちらか一方に100%ということはないだろう。それと同じことだ。2択の選択肢なら必ずどちらにも考えを持つ人がいる。自分と価値観が合う人を見つけていけば良い。今、1人で辛い思いをしている人も、自分と価値観が合う人を見つけることができれば取り残されることがなくなり、生きやすい毎日になるだろう。これから私は、自分が1人になるのを恐れず、取り残されている人に寄り添える人になりたい。
・北川 桜子 東北大学 3年 「孤独で寂しい」SNSでは解決できない問題にどう挑むか。
「いつもなんとなく孤独で寂しい」大学に入ってから度々感じていることである。友達と楽しく飲んでいても、SNSで数百人の友達と繋がっていても心のどこかで「寂しい」という感情がぬぐい切れない。大学進学と同時に1人暮らしを始めたからか、私のネガティブな性格が故か。
孤独感、そこから生まれる寂しい、という感情をどのように解消すればいいのか。私は家族のようにお互いに支え合える関係性にヒントがあると考える。この考えを持つようになったのは、コロナ禍の入学で友達がほとんどいなかった大学1年生の春休み、島根県隠岐郡海士町での島留学がきっかけだ。本土からフェリーで3時間、コンビニもスーパーもない一見不便な島は、外から見える何倍も豊かな環境だった。海に囲まれ、山もある、という環境的な豊かさはもちろん、人との繋がりによる豊かさであふれていた。各家庭が持つ小さな畑でとれた野菜の「おすそわけ」は日常茶飯事で、年配の農業のプロに家庭菜園の改善点を聞いたところ休日返上で畑の大改革をしてくれたり、椎茸農家さんが使う原木を山から運び出す作業を島の若者が集まって手伝い、お礼に椎茸をふんだんに使ったお弁当が振舞われたり、地域のセンターに行くとお母さん・お父さんがお茶をしている横で、たまたま居合わせた若者が子どもたちと遊んでいたり、という風に都会にはない人との繋がり、そこから生まれる豊かさ、があった。東京で生まれ育ち、マンションで人とすれ違うくらいしか地域の人との交流がなかった私にとって、人との繋がり・顔が見える関係性が生み出す豊かさ、それが生み出す心が満ちる感覚は新しいものだった。
次にこの感覚を抱いたのは、宮城県川崎町の公衆浴場「じゃっぽの湯」に行ったときのことである。おばあさんが更衣室に入ってくるやいなや、そこにいた人と最近はどうだ、とか、野菜が取れすぎて困っている、という会話が始まった。また、赤ちゃんを2人連れたお母さんが浴室に入って来たときには、湯船につかっていたおばあさんが「赤ちゃんは見ておくから、あなた先に洗ってしまいなさい」言い、そのお母さんも「いつもありがとうございます」と返した。衝撃だった。なんの気なしにコミュニケーションが生まれ、困っている人が居れば助け合える、そんな場所は素敵だったし、そんな関係性を沢山作りたい、と感じた。
海士町での活動・川崎町での経験を通じて、孤独感を解消するには、生活の中において家族以外の家族のような人との関わりがカギになるのではないか、と考えるようになった。お互いを理解し合い、助け合える関係性。助けを求めたら助けてくれる人がいる、と分かっていることの安心感、そして自分でも誰かを助けることができる、と知っていることによる自己肯定感を持つだけでも、生活が豊かになる。
生活の中で人との関わり、相互の助け合いをどのように自分の日常に取り入れられるか。私は、シェアハウスでの生活が挙げられると思う。プライベートな空間を持ちつつ、生活に他者がいる空間では、相性の良いハウスメイトが見つかれば、家族同然の関係性を作ることができる。お互いに理解し合い、助け合える関係性を1つでも多く持つことが孤独感の解消に繋がるとするなら、生活に人との関わりが自然と生まれるシェアハウスがそこはかとない寂しさの解消、ひいては取り残される人を減らす助けになるのではないか。実際に、血縁に縛られず子育てや生活を支え合う「拡張家族」を作るためのコミュニティも存在しているようだ。(“Cift”) シェアハウスに隣接する畑などがあればなおよい。農作業を通じみんなで汗をかきながら、仲を深める。シェアハウスで他人の考えを知り、自分の思考を深めたり、他人との化学反応で1人では成し得なかったことができたりするかもしれない。核家族化、都市化、SNSの普及によって深い人との関わり・助け合いが減った現代社会だからこそ、あえて人との関わりを生みだす方向に社会で舵を切っていく必要があるのではないか。
もちろん孤独を感じている全員が全員、生活空間を他人と共有、という方法が適しているとは思わない。けれども、埋められない寂しさを解消する一手段としてシェアハウス、そこでの生活を通じた、言うなら昭和時代の地域社会のようにお互いに助け合えるような関係性の構築が、誰一人取り残さない、の目標達成のカギになると思う。
・阿部羅 好恵 創価高等学校3年 知ることで変わる世界
先入観はどのようにして生まれるのだろうか。
親の発言からなのか。もしくは、授業で習う事柄からなのか。歳を重ねていくうちに自然と””普通””が出来上がってくるのだろう。
事実として、先入観という言葉の定義は””実際に見たり聞いたりする前に、頭の中にできている考え””である。だからこそ、知ろうとすることが大事だと思う。私自身、「男なんだから力あるでしょ」だの「帰国子女だから英語なんて余裕でしょ」だの、「〇〇だから〇〇でしょ」というフレーズを何回も聞いてきた。こうやって人は勝手に先入観を持たれ期待される。さらには、「日本人はメガネをかけていて真面目だ」のように国籍に対する先入観まである。
先入観を持たれた人はどう感じるのだろうか。私も何度か先入観を持たれたことがある。その場では笑うことしか出来なかったけど、ふとその時言われた言葉が蘇ってくる時、勝手に落胆する。それまでは気づいてもいない、必要と思っていなかったことだとしても「〇〇なのに」と言われると、「なぜ出来ないのだろう」と思うようになってしまう。このようにして、言っている側は軽く言ったつもりでもその言葉を受けた人は意味もなく自分に自信を持てなくなることもあるだろう。一方で、私自身先入観を持っているなと感じることは少なからずある。なぜそう思うのか聞かれても答えられないだろう。だから、私含め1人でも多くの人が、相手が持っている能力よりも、その人の存在自体に目を向けていきたい。そうすれば、どんな人にもそれぞれの価値があるという事に気づき、尊敬の念が増すと思うからである。また、読書も先入観にとらわれないために必要だと思う。たくさんの書物に触れて、いろんな視点から物語を見つめていく中で多様な価値観を身につけていけると思う。これらを意識するだけでも自分が持っている固定観念から少しずつ抜け出せるのではないだろうか。
私が考える「誰ひとり取り残さない」意味の一つは、その人がどのようにして生まれてきたとしても、どのような過去を持っていたとしても””今””のその人を知り、受け入れる事だと思う。まずは知ろうとしている姿勢を見せるだけでも相手は安心することができるだろう。先入観を持つことは仕方ないかもしれないけど、それにとらわれすぎずに””今””の相手を見つめてみる努力をしていってほしいし、自分自身もしていきたい。そして、自分の周りにいる人たちが自分にとってどれほど大切で大きな存在なのかをしっかり発言や行動で示していきたい。
・宮﨑 一輝 和歌山大学 2年 体格による取り残しが本当に“しょうがない”のか
中学2年の夏、柔道の団体戦メンバーとして同級生の中から選ばれたのは、自分と大して実力は変わらないが身長・体重ともに私より大きい子だった。団体メンバーを決めた先輩方は、「一輝にもっと体重と身長があればなぁ」と笑っていた。
私は小学4年生のころから柔道をしており、中学生になっても学校の柔道部に所属し稽古に励んでいた。私は当時、身長はクラスで一番小さいほど小柄であり、体重も柔道の階級の中では一番軽い階級であった。多くの人は柔道に向いていないと考えるかもしれないが、実際はそうでもない。「柔よく剛を制す」という言葉があるように、私は小さいなりの戦い方をすることによって、部活内では自分よりも大きい人にも簡単には投げられなかった。
私の所属した柔道部は、人数も少なく、決して強豪と呼ばれるようなものではなかった。その為、団体戦に出場するメンバーは顧問の先生による選出ではなく、学生の間で決められていた。初めに決まった団体戦メンバーは一つ上の学年の先輩方だった。控えメンバーを合わせて7人決める必要があるが、先輩方だけで5つの枠が埋まった。残りの2枠のうち1つは、私を合わせて3人いる同級生の中で一番実力のある子に決まった。その子の実力は明らかに私より強かったため、私は何の異論もなかった。残りの枠はあと一つ。残ったのは私と、実力の変わらない同級生の子の二人であった。どちらが選ばれるのだろうかと鼓動が早まる中、選ばれたのは私ではなく同級生の子だった。
私は先輩方になぜ私が選ばれなかったのか質問した。すると、「団体戦は体重順で先鋒から決めるから、体重ある子の方が都合がいいんよ」という、予想外の回答が返ってきた。「実力から考えた」という回答であれば、まだ納得することができた。しかし、「体重」という体格によって決められたということにはとても納得することはできなかった。しかし、先輩方に反論することはできず、団体戦は私以外のメンバーで決まった。
このような体格によって取り残されるという事例は、私のように小さい場合に限らず、身長が高い場合にも考えられる。例えば、小中学校などの義務教育の中で見られる「背の順」である。「背の順」では、身長が低い子を先頭にして並んでいくため必然的に身長の高い子が後ろの方に並ぶことになる。この並び方によって「前の子が大きくて前が見えない」という問題は防ぐことができるが、これは本当に誰も取り残していないのだろうか。子供たちが実際に近くで学ぶという機会から身長の高い子を取り残しているのではないだろうか。
以上のことから、SDGsの基本理念である「誰ひとり取り残さない」を達成するためには、スポーツの対格差や学校での背の順などの無意識に「しょうがない」と思われている要因を排除することが必要であると考える。現代で無意識下に取り残しが起こっている状態では、「誰ひとり取り残さない」を達成することは不可能なのではないだろうか。
私は今、小学生から大人までが集まる町道場で柔道を続けている。小学生の中には「僕は小さいから勝てやん」と悲しんでいる子がいる。このような体格によって悲しむ子を私自身と重ね合わせ、私は小学生に指導を行うこともある。このような問題が少しでも減ることを願う。
・西村 公希 山口県立大津緑洋高等学校普通科二年 本当の「多様性」
「多様性」この言葉は誰一人残さない世の中を創り上げるために切り離してはいけない言葉であり、私たちの根底になければいけない考え方であるとも言えよう。人と人とのつながりが重要視される現代でこの多様性について自分自身、考える機会が多くなったように思う。
教室で過ごしていたある日、休み時間に一人で作業をしていると、不意に自分に孤独感が降り注いだ。他の人たちはいくつかのグループを作って楽しそうに遊んでいる。自分が見放されている、まさに「取り残された」感覚がして、身震いがした。体の力が抜け、その後の授業では内容が頭に入ってこなかった。そして、家に帰って泣いてしまった。自分が他人と比較し、考えすぎてしまう性格のせいでもあるが、今までにない感覚がした。そんな自分に対して、両親が寄り添ってくれた。そんな時こんな言葉をかけてくれた。
「自分なりの良さがあるのだから、それを大事にしなさい」
シンプルな言葉であるが、あの時の自分の心にすごく刺さった。人とのつながりが多ければ多いほどいい。世間一般的なイメージでは交友関係が広い人は好かれやすいし、他人からもいい印象を持たれる。しかし、そのような固定観念は捨て、決してそのような人に無理やりなろうとしなくてもいいことに気づいた。「自分は自分なりの生き方をしよう」と。
このような出来事があって以来、私は改めて「取り残される」ことについて考えた。取り残されること自体にはどうしても否定的な思いが先行する。「いじめ」にも連想してしまう。しかし、取り残されることは悪いことではない。自分は自分の好きなように生きていくことが一番であるし、それぞれ一人一人が持つ独自のものをすべて自分にしかない武器だと考えることが重要である。私のこの言葉に対するイメージが百八十度変わったのだ。自分の考えが変わったおかげで、より物事を客観的にみるようになった。人との関わりをより一層大事にし、困っている人に手を差し伸べることは欠かさないようにした。そうしたことで、学校生活の中に「楽しさ」を取り戻し、日ごろの授業、友達との登下校といった当たり前に日々行っていることにも今まで以上に喜びが感じられるようになった。
自分の個性を大事にしながら、自分の生きる道を見つけ、人とのつながりを大事にして歩んでいく。これこそが自分の中での「多様性」なのだと思った。多様性という言葉に対する鬱憤や曖昧な感情は消えた。こんな多様性に満ち溢れる人間がいたら、世界はもっと明るくなる。日々暗闇に閉ざされた報道は必ず減っていくだろう。自分の生き方はまだ明確にはなっていないが、方向性は一つの直線としてはっきり見えている。もし、自分自身について先が見えないような人がいたら助けてあげたい。「誰一人残されない社会」は自分で創り上げることができる。この大きな学びは今後に人生の中でも重要な教訓となり、大きな経験をすることができた。
最後に、自分を支え、方向性を見出してくれた両親には感謝している。
・伊藤 陽香 関西外国語大学 2年 Leave No One Behind
想像してみよう。もしあなたが学校に行けなかったら。想像してみよう。みんなと同じ教室で勉強したいのに、耳が聞こえないという理由でみんなと違う教室に行かなければならなかったら。このようなことを考えることなく教育を受けてきた人たちなら、想像するのは難しいだろう。しかし、教育を受けたくても受けることが出来ない人がいるのが現状だ。教育の場において、取り残されている人たちがいる。
私は今年、約3ヶ月間、オーストラリアのクィーンズランド工科大学に留学に行った。そこで学んだのはSDGsだ。元々少し興味があったSDGsの留学があると知り、英語で学べるならと思い、すぐに応募した。学内の選考を通過し、留学に行けることになった。この留学プログラムは、教科書を使って各ゴールを勉強し、週の終わりに実際に見て学んだり、ボランティアをされている方々のお話を聞いたりした。また、3ヶ月かけて1つのゴールについて深く調べ、レポートを書き、プレゼンテーションをした。そこで私が選んだゴールが、4番の「質の高い教育をみんなに」だ。私はSDGsの中で鍵となるのは教育だと考える。教育の大切さを多くの人に知って欲しいと思い、この作文・小論文コンテストに応募した。
私のレポートやプレゼンテーションのテーマは「Leave no one behind」だ。日本語にすると「誰1人取り残さない」となる。授業で教育について学んでいるうちにあることに気づいた。学びたくても学べない人が沢山いる。その人たちに教育を受けて欲しいと思い、「誰1人取り残さない」をテーマに、約3ヶ月間取り組んだ。レポートの中で調べたのは障害についてだ。
周りの施設や設備をよく見てみよう。車椅子を使っていても使いやすいか。耳が聞こえなくても授業を受けることが出来るか。私はそうは思わない。学校の机には椅子が固定されている。耳が聞こえない人が他の人と一緒に授業を受けることの出来る設備が整っていない。留学先であるクィーンズランド工科大学は、障害者もみんなと同じ教育を受けることの設備が整っていた。図書館の机は、車椅子を使っていても使えるようにカーブしていた。教室には先生の声を拾い、文字としてプロジェクターに表示される設備が整っていた。今ある設備をすぐに全部変えることは難しい。少しずつ誰もが使いやすい設備に変えるべきだ。私たちができることは、困っている人がいたら助けてあげることだ。開けにくいドアがあったら開けてあげる、運びにくいものがあったら手伝ってあげるなど、今すぐできる小さな優しさが、誰1人取り残さないための手助けになる。
障害には、身体的なものだけでなく精神的なものもある。精神的な障害を持った人たちも、周りの人に理解して貰えなかったり、特別教室に行かされたりなど、同じ教室で教育を受けたくても受けることが出来ないことがある。このような人たちを減らすために、インクルーシブ教育を行っていくべきだ。インクルーシブ教育とは、「障害がある子どももない子どもも、その子の特性に応じた学習環境や配慮を行っていき、一緒に学ぶことが出来る教育理念」のことだ。教育の質が高いと評価されているフィンランドを例にあげてみよう。フィンランドは、インクルーシブ教育を積極的に使い、教育の質を維持している。インクルーシブ教育を取り入れることによって、障害の有無に関わらず、同じ教室で学ぶことが出来る。障害がない人は、障害について理解し、困っていたら助けてあげることで、より同じ教室で学習しやすくなるだろう。また、世界中の教育に関わる組織は、フィンランドを参考にインクルーシブ教育を取り入れ、みんなが同じ教室で学べるようにするべきだ。
SDGsの一つである質の高い教育をみんなが受けることが出来るようにするために、まずは現状を理解し、周りの人に手を差し伸べることから始めよう。今、教育の場で取り残されている人たちがいる。勉強したくても出来ない人がいる。あなたの小さな優しさがSDGsを達成するための鍵となる。
・山崎 隆斗 長崎県立鶴南特別支援学校五島分校小中学部 中学2年 僕の夢が見つかった
僕は、自閉症スペクトラムという障害をもっている。
他にも障害や病気をもっていてこれまで何回も死にそうになったことがある。
いつもわけがわからなくなり泣いてさけんだりする。
ずっとなんで僕は、こんなんだろうと思うこともあった…学校にもいけない時期もあった。
そんななか去年僕が住んでるとこで日本ジオパークが登録された。
ジオパークとは、ジオ(大地)とパーク(公園)を組み合わせた動物や植物とともに、大地の上で生活し地質や地形は、人の暮らしや文化に直接結び大地と自然、人々とのつながりを学び、地球をまるごと楽しむ、それがジオパークです。
というのを学校で習った。僕は、そのジオパークに興味をもちお母さんと夏休みの自由研究でジオパークについてたくさん調べた。
途中なんかいももうやめよう嫌だと思いながら最後まで完成させた。
夏休みに学校で展示してその後は家にそのノートは、保存してあった。
でも今年の夏に木下さんという方と出会いそのノートをみたいていうことで貸し木下さんが古里さんというかたにそのノートをみせて僕の人生は、大きくかわる。
古里さんという方が市役所のジオパーク担当の方と話したりして何と子供で初めてあぶんぜビジターセンターに期間限定でノートがおかれることになった。
お母さんにすごいことだよ。頑張って完成させたかいがあったね。とほめてくれた。
古里さんとあうことになり待ち合わせの場所に行く途中に僕は、すごく不安になり車の中でパニックにもなった。
古里さんとあったときも僕はパニックになったり一方的に話したりしてもいなやな顔せずにずっと話をきいてくれてさらにジオパークノートをうまくまとめてるとほめてくれたりした。
話してる中で色んな不安もあったりするし怖いこともあるけど色んなことにチャレンジすることはすごくいいことだしおじちゃんとこれからジオパークを盛り上がっていこうとも話してくれた。
その中でジオパーク(観光地)案内人の話をしてくれたりもしてそのとき僕は、ジオパークの人になりたいという夢をもった。
でも僕は、人の多いとこ先の見通しがないと凄く不安になることも古里さんにつたえると、周りには大人も沢山いるしなっても周りの人がささえるから大丈夫と
いって色んなことをおじちゃんと体験して頑張ろといってもくれた。
すごく嬉しかったし僕のことを理解してくれる人だとも思った。
ジオパークの人になるには、色んな課題がたくさんあるけど今僕にできることは、自分でできることを一つ一つ増やすことだと思う。そして僕は、自分が抱えている病気や障害から逃げず頑張ろうとおもう。
・髙橋 幸太朗 関西学院大学3年 誰一人取り残さない住宅政策
本コンテストのサイトにも説明があるように、誰ひとり取り残さないとは、社会活動から誰もが排除されないことであり、だれもが社会的排除を受けないと説明することができる。一方で社会的排除の対となることば「社会的包摂」である。本稿ではこの社会的包摂の視点から誰ひとり取り残されない社会の達成のために私自身の意見を社会に提言しようと思う。
私は今大学生として一人暮らしをしているが、大学入学までは母子家庭で生活保護を受けながら生活をしていた。当然、毎月の食費や住居費、水道光熱費などの最低限の生活を維持するだけで精一杯であった。そのため、常に周囲の友人と衣服、文房具など生活のすべてに対して格差を感じながら生活を送っていた。しかしながら、今はアルバイトや奨学金を受けながらなんとか大学生活を送ることができている。
このように幼少期から現在にいたるまで社会的排除を身近に感じながら生活を送ってきた私だが、大学入学後に大阪の西成区を知り、私以上に社会的排除を受け、誰ひとり取り残さない社会的包摂を必要とする人々がいることを学んだ。私は大学の講義を通して、日本以外でも様々な少数民族が社会から排除を受けていることを知り、普遍的な社会政策・包摂について文献調査を中心に学んだ。
文献調査では、フランス郊外の移民・ ドイツのトルコ人ゲットー・日本の東九条の3つの事例をもとに西成区にも適用可能な社会的包摂について考えた。3つの事例を分析してわかったことは、住宅環境の質が悪いことで貧困の集中を招き、ゲットー化した住宅や地域からは中所得・高所得者が流出するということだ。その結果、貧困に苦しむ人々は、低賃金による生活不安だけでなく、差別など複合的不利に苦しめられ社会から取り残されてしまっている。つまり、誰一人取り残さないためには、住宅や地域に様々な社会階層の人が混ざり合うソーシャルミックスが必要だ 。これを達成するためには、入居条件に所得上限を設けずに低所得者層を包摂しながらも、住宅の質を保つことが求められる。
実際にデンマークの公営住宅では所得制限が設けられておらず、低所得者層には政府と市から収入の15%が家賃となるように家賃補助がされている。このような「ユニバーサル・アクセス」を可能とした住宅政策は、住宅の質を保ちつつソーシャルミックスを促すことを実現でき 、誰ひとり取り残さない社会の実現に貢献できると考える。
西成区においても同じようにソーシャルミックを起こすことで、誰一人取り残されない社会を実現できる のではないだろうか。具体的には、空き家のリノベーションによって家族世帯向け住居を増やすことや、民間企業の誘致を行い、積極的に社員寮として空き家を活用してもらうという手段が挙げられる。中間層や、企業の誘致を行うことで地域の自治意識の向上、官民連携によるお祭り・イベントの開催の機運を高め、西成区の活性化にも作用すると考えられる。イメージとしては企業城下町だ。西成区の再編に伴う住民の立ち退きなどの懸念もあるが、住人が住まいを奪われるような状況の広まりは無いとされていることに加え、企業による新たな雇用創出も期待できる 。私はこのようにして誰ひとり取り残されない社会が実現されて欲しいと心より願う。
現代社会では誰一人取り残さない社会の達成に向けて様々なアクターによってSDGsの取組が行われている。一方でSDGsウォッシュという言葉があるように、SDGsがキャンペーン化している側面も否めない。だからこそ私たちは、誰一人取り残さないというSDGsの基本理念を尊重し、誰ひとり取り残さないためにSDGsアクションを起こしていくべきだ。私は、これまで社会的排除を受けた経験があるからこそ、西成区の人々が取り残されない社会の実現を望む。私は現在大学公認のSDGs団体で代表を務め、他のユース世代よりは取材やイベント登壇などを通して社会に声を届ける機会がある。私はこれからもいただいた機会を存分に活かして、西成区の事例をはじめとした誰一人取り残されない社会の実現のため社会にアプローチし続けていくことを止めない。
・村上 凜音 北海道苫小牧市立緑陵中学校 社会の連鎖
あなたは、ブレスレット運動を知っているだろうか。ブレスレット運動について説明したいと思います。ブレスレット運動には5種類の色があり、色によってそれぞれの意味が違います。青色は自傷行為を過去にしてしまったことがある人、赤色は今してる人、黒色は生きるのが辛い人、また、オレンジ色は起立性調節障害、緑色は過敏性腸症候群など見た目では分からない辛さを色で判断してもらうというものです。ブレスレット運動は病気や環境で苦しんでいる人とそれを少しでも支えて、助けになってあげたい人のしるしです。このように、ブレスレット運動にはブレスレットをつけてる人が「支え、支えられる」という前向きな気持ちを運動で表しているのです。では、自傷行為をしたことがないけど支えになりたいという人もブレスレット運動に参加してもいいのでしょうか。
突然ですが、私は約4年前からブレスレット運動に参加しています。と言っても初めは何をすればいいのか分かりませんでした。ブレスレット運動を知ったのはSNSサイトでブレスレット運動をしている人がブレスレットの意味を語るという動画でした。ただ「自分が自傷行為を行ったことがある」という経験があっただけの一般人で、最初は、ブレスレット運動なんて見えないし、意味ないよねと思いつつ、ブレスレット、ミサンガを自分に合う5種類の意味を見つけてつけてました。付け始めて1年経った頃、習い事の後輩が自傷行為をしたことがあるとカミングアウトしてくれました。
なぜ私に話してくれたのか不思議だったので、聞いてみると、ブレスレット運動と同じ色のミサンガをつけていたからという理由で話してくれたそうです。そのとき、私は初めてブレスレット運動の良さと大切さを知りました。最初は意味ないと思っていたものが身近な後輩の胸の奥の気持ちを話してくれるひとつの鍵となってくれたことがとても嬉しくて素晴らしいものだと感じることが出来ました。しかし、私は「後輩の思いを聞いて何をしてあげれるのか。ただ話を聞いた人になってしまう」と思ってしまいました。なにせ、自分が着けたくてつけてることですが、善人ぶってるとか、自己満だとか私じゃなくても他の人もできて私がやらなくてもいいのでは無いか。私がブレスレット運動に参加していてもいいのかと思っていました。そんなに、悩んだり考えたりするならブレスレットをつけなければいいじゃないかと思う友達や家族もいました。ですが、私は現実的に自傷行為をしたくなる時もあったり、そのせいで周りに迷惑を掛けたりしてしまうこともありました。じゃあ付ければいいじゃないか。そんな声もあると思います。ですがそんな安易な考え方で付けるものではなく、重みがきちんとあるもので責任をもって付けるものだと私は思っています。今回のテーマ「誰ひとり取り残さない」を私の意見と重ねると、人は1人では生きては行けません。世界には取り残された人なんて存在しないということです。
誰かが誰かを支えて、支えられた人が誰かを支えてと連鎖していると思います。この連鎖が成り立たないとより良い社会関係が成り立つことは難しいのです。伝えたいことは、私みたいにブレスレット運動に参加して、誰かの助けになりたいと考えている人は沢山世の中にいるということです。ブレスレット運動の意味は「ひとりじゃない」です。人は1人ではありません。必ず理解してくれる人、応援してくれる味方、家族や友達、仲間が付いています。最後に、自傷行為をしたことがなくても、寄り添いたい気持ちがあれば誰でも参加することが出来ます。もし興味を持ってくれたり、役に立ちたいと思った人は少しでもブレスレット運動を知ってくれる人が増えたら、取り残される人は必ず少なくなると思います。
・鈴木 日彩 群馬県立中央中等教育学校 5(高校1)年 僕を『覚え』『感謝』する。あなたを『覚え』『感謝』する。
「泣きたい」僕は時々こう思う。自分でいうのも難だが、毎日、課題、部活動、課外学習、塾と忙しい。その上先生、母、父に怒られる。怒られる。それは仕方がないことだと思うし、何故僕が悪い。僕は周りの友達みたいに利口ではない。明晰な頭脳を持っている訳ではない。だからといって運動ができる訳でもない。他の人より長けていない。だから僕は怒られる。僕は落ち込む。何度、怒られ、落ち込んだとしても、僕は挫けない。絶対にだ。なぜなら僕には友達がいる。友達が声をかけてくれる。友達が助けてくれる。僕は忘れられてないということを感じることができる。彼は僕を覚えてくれている。
ありがとう。僕は助けてくれた友達に「ありがとう」と言う。どれだけ落ち込んでも、逃げ出したくなっても助けてくれたら感謝する。感謝することで僕はこころがあったかくなる。そして友達も嫌な気持ちになっていないだろう。
「誰ひとり取り残さない」とはこういうことだと僕は思う。『覚えている』『感謝をする』これが「誰ひとり仲間から取り残さない」世界をつくるために重要なのではないかとこの人生の中で確信している。
この僕の経験は単なる僕の人生に過ぎないからこんなことを言ったら何言っているんだこいつはとあなたは思うだろう。しかし、僕の経験は、単なる僕の人生に過ぎないが、それはSDGsの基本理念に契合している。誰もが健康な状態であり、誰もが教育を受け、誰もが社会的サポートを受けることができる社会が求められているこの世の中で私たちが築き上げるべき理想の社会は、互いに覚えていることや感謝の気持ちから始まるのだと確信をしている。
あなたはそんな少しの事である『覚えている』『感謝をする』ことがこの世の中にあふれている、いじめ、差別、児童虐待などの比較的我々の身近なものから環境問題、経済格差、人権問題、戦争・紛争などの世界中での協力が必要なものまでの社会問題を解決できるわけないと思っただろう。
僕はこの考えを否定する。なぜならこれらすべての社会問題は「取り残している」からだ。いじめ、差別、児童虐待など身近なものに関しては明らかに取り残しているだろう。“行政機関が“ではない。“あなたが”だ。いや“僕が”でもある。法務省がいじめの特徴を以下のように定義している。これはいじめだけに当てはまらず他の差別、児童虐待にも当てはまるだろう。
「いじめ」の実態として、一人を複数がいじめる傾向にあることから、「いじめ」の首謀者が誰であるかハッキリしておらず、「いじめ」を行う側のこどもが罪の意識を感じていない例が多く存在します。更に、「いじめ」に実際に加担していなくとも、「いじめ」の行為を面白がって見ていたり、はやしたてたりする「観衆」や、それらを見て見ぬふりをしている「傍観者」というこどもの集団が存在しています。
この「観衆」や「傍観者」が忘れずに『覚えて』いて見て見るふりをせずに、『感謝』することなどの日常の些細なことをきっかけに手を差し伸べれば解決できるのではないか。
また、世界中での協力が必要な社会問題に関しても同様の事が言える。例に挙げると現在(2023年12月)パレスチナでの戦いが再加熱してくると、連日報道されていたウクライナでの戦いは報道され、パレスチナでの戦いが報道されているようになった。これはウクライナでの戦いを『覚えている』ことができようか。これはまさに『覚えて』いる必要があるだろう。そして『感謝』があることにより「誰ひとり取り残さない」ことが生まれるのではないか。(この感謝は覚えていることだけへの感謝を指すものではない)こうして「誰ひとり取り残さない」世の中が完成するのではないだろうか。
これは机上の空論ではないことを再確認したい。なぜなら僕たちが1人だけでできることだからだ。自分は「取り残されていない」から今のままで十分だ。こう考えるのではだめだ。『覚えている』『感謝をする』ことで自分の人生がちょっとでも豊かになる。自分にとっては『覚えている』『感謝をする』ことで嫌な気持ちにならない。むしろ誰にでも仲間がいる仲間意識が深まり、仲間が増え、仲間の大切さがわかりほっこりするだろう。そして、全員が同じ考えを持っていれば『覚えている』『感謝をする』ことが返ってくるだろう。どんな人でも絶対に『覚えていてくれる』『感謝をされる』があればうれしいだろう。
私は世界に対してこういいたい。「普段から周りの人を『覚えて』『感謝』をしよう」と。そうすれば自分が明るくなる。仲間が明るくなる。世界が明るくなる。自分は取り残されていない。仲間が取り残されていない。世界のだれも取り残されていない。
普段から『覚えて』『感謝』するためには自分のことから始めればいいだろう。僕は「誰ひとり取り残さない」ために自分を『覚えて』『感謝』したい。
・河角 公太 東海大学国際文化学部2年 視覚障害者とのスポーツ観戦から得られた「誰1人取り残さない」を実現する「気づき」
1. はじめに
「誰1人取り残さない」を基本理念とするSDGsは、持続可能な社会の実現に向けて2030 年までに全世界で達成すべき目標を具体的に設定している。私は、今年大学の授業を通じて得た「視覚障害者と一緒に行うスポーツ観戦」の経験について、SDGsの基本理念から考えてみたい。
2.SDGsと視覚障害者との関わり
私はスポーツ観戦が大好きだ。IT技術の発達で、今やテレビだけではなく、スマホ・パソコンでいつでもどこでも観戦ができる。しかし、私にとってのスポーツ観戦の醍醐味は、なんと言っても「現地観戦」だ。リアルな選手の息づかいや、観客の熱狂を間近で感じることができるからだ。様々な電飾やプロジェクションマッピング、音楽やダンス・MCなどが組み合わされた演出と選手のハイパフォーマンスの組み合わせは、私をいつも興奮させてくれる。
ところで、この観戦の楽しみは「目で見る」ことを前提として行われる活動だと、「普通」は思うだろう。メディアを通じた観戦でも、現地での観戦でも、映像などをフル活用して見る者の視覚に訴えてくるからだ。私も今回取り上げる大学での授業を経験する前まではそう思っていた。しかし、その前提だと「取り残される人々」が生まれてしまう。それが、目の見えない人たちである。
3.視覚障害者とのスポーツ観戦経験
今回、私が経験したのはバスケットボールの観戦である。街の中での「手引き」の方法を事前に学び、また実際に行う中でも当事者の方にアドバイスをもらいながら、観戦に出かけた。初めて視覚障害者とスポーツ観戦を行ってみて感じたのは、「見えないこと」で生じる不平等があることだった。会場内に点字ブロックがなかったり、階段の登り降りが多かったり、会場となったアリーナのつくりは視覚障害者と一緒に観戦するには優しくないと思った。また、音声案内や優先通路もなく、混雑した会場内では、どんなに気をつけて手引きをしても視覚障害者が周りの人とぶつかってしまう。
なんとか座席に到着して、いざ観戦!と思ったらもっと大きな困難に直面した。選手のプレーや試合経過を言葉で表現し、解説しなければいけないことは予め想定していたのだが、思った以上に会場で行われている演出の音や見た目の変化が大きく展開スピードが早くて、言葉で全てを追いきれないのである。「目で見る」ことで自分達はいかに一気に情報を取得できているのかを思い知らされると同時に、一体何を情報として伝えれば楽しい観戦になるのかを考えさせられることとなった。
そこで、今回試したのが、「聞く」「触る」ことに着目した情報伝達・解説方法である。実際に選手がどういった動きをしているのか、ボールがどの位置に動いたのか、チームがどんな戦術を用いているかに特化して、コートをエリア分けして番号(数字)を振り、その数字を伝えることで説明し、同時に、タコ糸を貼り付けてコートの形が触ってわかるように工夫した作戦ボードを使って解説した。
テレビ等での解説とは全く違う方法だったので、実際に行う前までは、この説明だけで観戦を果たして楽しめるだろうか?と正直感じていた。しかし、いざやってみると面白い!楽しい!と言ってもらえた。私たちのような見える人がもつバスケットボールの世界観やイメージとは違ったかもしれない。だが、今回の挑戦を通じて視覚を用いないスポーツ観戦の楽しみ方があることを私は知った。
4.SDGsの基本理念から考える視覚障害者のスポーツ観戦
「誰1人取り残さない」というSDGsの基本理念から、今回の私の経験を振り返って考えてみると、最も大事だったのは「違いへの気づき」だった。普段「見えている」私は、「見えていない」人々のイメージや世界が「見えていない」。見える人は見えない人に気づきにくい、のである。しかし、私たちの周りには「見えない人」が確実にいる。当たり前だが、スポーツ観戦の場にも視覚障害者はやってくる。しかし、何気なく生活しているとそれを私たちは「普通」だと感じられない。だから、会場には、点字ブロックや音声案内、段差解消の措置などはなされず、視覚障害者に気づいてない人が視覚障害者とぶつかってしまう。
私たちに求められるのはまず、私たち自身が「普通」だと思っていることに意識を向けてそれが「普通ではない」ことに気づくことだと考える。その際、何かを「手助けする」という発想よりも、より良く実現できる方法を当事者と「一緒に探る」という発想を重視したい。なぜならば、視覚以外の方法で見ることを念頭においてそれを当事者の人たちと一緒にどうしたら良いか考えて、色々とチャレンジした今回の経験が、私にとっても非常に楽しかったからである。
今回の経験から言えば、スポーツを目で見ることを「普通」と思わず、目で見ないスポーツ観戦もまた一つの方法であると考えること。それが「誰1人取り残さない」を実現する第一歩になると私は信じている。
・春日 絆那 養老町立高田中学校1年 認め合い 助け合い 自由を目指して
先日、テレビでフィギュアスケートの大会の様子を見ていたとき、男子と女子で点数に差があることに疑問を感じた。その理由を母に尋ねてみると、技一つ一つに得点が決められていて、難しい技の得点は高く付くからだと教えてくれた。男子では、ジャンプは4回転ができる選手が結構いるが、女子ではトップクラスの選手でも4回転はなかなかできない。それは、男性と女性の体のつくりに違いがあるから仕方がないことなのだ。ジェンダー平等を目指す世の中で、全てを平等にすることはできないのではないかと、フィギュアスケートを見ていてふと思った。では、SDGsにも掲げられている、ジェンダー平等をどのように実現していくのか、私なりに考えてみようと思う。
私が通っている中学校では、昨年から制服が変わった。制服が変わった背景には、ジェンダーの問題や気候変動などがあったと聞いている。今年入学した私も、新しい制服を着用している。以前の制服は男子は学生服、女子はセーラー服にスカートだった。一方、新しい制服は、ジャケットにズボンかスカート、カッターシャツにネクタイかリボンを男女に関係なく、好きな組み合わせを選べるようになった。私は、スカートとリボンの組み合わせを選んだ。同じ学年の子の中には、女子でズボンにネクタイの子もいるし、スカートにネクタイという組み合わせの子もいる。しかし、男子でスカートにリボンの子は一人もいない。本当はスカートをはきたいと思っている男子がいるかもしれない。もし、今後そういう子が現れたとしたら、私はどう感じるのだろう。ジロジロと見てしまうかもしれない。女子がズボンをはくのは、そんなに違和感がないのに、男子がスカートをはいていたら、やっぱり変だと思ってしまう自分がいる。これでは、せっかく制服が変わって、選べる自由ができたのに、本当の意味での自由にはなっていないように思う。どうしても、少数派の人のことを珍しがって、特別に扱ってしまう風潮が日本にはまだまだある。制服を一層、全員ズボンにしてしまうとか、私服にするとかすれば、もしかしたら性別など気にならなくなるのかもしれない。そう考えると、私の学校の制服が変わったことは、ジェンダー平等を実現したのではなく、ジェンダー平等に一歩近づいたと言えるのではないだろうか。男女関係なく、みんなが本当に着たいと思っている服を着て学校に行ける日が来たら、とても素敵だと思う。しかし、それを実現するには、生徒全員が学校の中のルールを守り、きちんと授業を受け、校内の秩序を守っていかなければならないと思う。誰一人取り残さないためには、ルールを守らない人が、誰一人居てはいけないということなのではないだろうか。
このように考えてみると、ジェンダー平等については、スポーツの世界のように、どうしても男女を区別しなければいけないことと、私たちの努力によって、男女の区別をなしにできることがあるのだと思う。これから私たちが社会に出たとき、ジェンダーの問題に直面することがあるかもしれない。ジェンダー平等とは言っても、やはり男性がやった方がいい仕事、女性がやった方がいい仕事、というのはあると思う。服装や見た目の自由を保ちつつ、自分にできないことは誰かに助けてもらうとか、誰かができないことを自分が助けてあげるとかいうように、互いを助け合って埋め合っていくことで、性別なんて気にしなくなる日が来るのではないだろうか。人が生まれながらにして持っている特性を認め合うことこそが、ジェンダー平等につながり、性別の違いに悩む人が少なくなっていくのではないかと私は思う。
・中本 雛詩 創価高等学校3年 Kaiaが気づかせてくれたこと
“Don’t eat here.”
“NOT 〇〇.”
昨年の7月に初めて来日したアメリカの友人と浅草を訪れたときのことである。このような英語表記が気になった。
「ここで食べないで。」
「〇〇しないで。」
禁止されていることやしてほしくないことばかりが英語で並べられていたのだ。また、お昼に寄ったもんじゃ焼きのお店のメニューが日本語でしか書かれていなかったことにも驚いた。友人は日本語を勉強しているもののなかなかメニューまではわからず、私たちにどんな料理か質問をしたり、インターネットで一緒に検索をしながら注文をした。私はこのとき初めて外国人観光客や留学生にとって日本はまだまだ優しさが足りていないのかもしれないと感じた。
たしかに気をつけてほしいことを書いておくのは大切なことだ。ただ同時に、悲しさも感じてしまうのではないかと思った。知っている言葉、とくに母国語は安心できる材料のひとつである。もしも私が見知らぬ土地にいるときに日本語を見つけ、それが注意事項ばかりであったとしたら…楽しむために訪れた場所で私は悲しくなってしまうと思う。
しかし悲観することばかりではない。日本では、10年ほど前から東京オリンピックに向けて道路標識の英語表記改善をはじめとした外国人受入れのための対策が進められてきた。多くの道路標識には日本語とローマ字が書かれているが、書かれているローマ字が外国人に伝わらないことがあった。例えば「銀座通り口」の表記がローマ字の「Ginzadoriguchi」から英語表記の「Ginza-dori Ave. Entrance」に変更されたのだ。私は今まで意識するきっかけがなく疑問も不自由さも感じてこなかったが、海外に住む友だちと日本を歩いたことで初めて気づけたことがいくつもあった。色んな人の目線に立ち、よりよい社会をつくっていくことが誰ひとり取り残さないことに繋がっていくと感じた。
ここまで英語表記について触れてきたが、なんといってもいちばん大切なのは私たちのおもてなしの心であると思う。人の温かさや優しさに触れると幸せな気持ちになり、その幸せな気持ちはどんどん伝播していく。私は日本という国に興味を持ち、楽しむためにせっかく時間とお金をかけて日本に来てくれた人たちをおもてなしできる力を持ちたい。そのために語学の勉強に挑戦し、魅力あふれる日本についてこれからさらに学んでいこうと思う。
・高野 美侑 宮城県名取高等学校3年 外国人だからという理由で
今日の日本では、多くの外国人を様々な企業などで受け入れている。技能実習生や正社員など、職種や分野は人それぞれ、多種多様である。多くの日本人は日本に旅行へ来ている、日本で生活をしている外国人に対して、身長高いな。顔が全然違うな。のように私たちは外国人に様々なイメージを抱く。外国人に対して、羨ましい、不思議だな、というような相手に対する尊敬や興味の思いを抱く人がほとんどである。このように聞くと日本や日本人は外国人に対して快く受け入れているように感じる。しかし、全ての外国人がこのように優遇などを受けている訳ではない。なんで日本にいるのか。外国人なら自分の国に帰ればいいのに。というような相手を侮辱したり軽蔑したりするような思いを抱く人も少なからずいるのが事実である。このような事実を受け私は常々、逆の立場ならと考えている。おそらく私たち日本人も同じように海外へ行けば現地の人たちから様々な言葉をかけられたり、思いを抱かれたりするに違いない。と考えている。
私は5歳の時に幼稚園に来ていたALTの先生の英語の授業が楽しい、もっと話してみたい、という気持ちから英会話を習い、今も続けている。そのお陰もあり、外国人に話しかけられてもほどんど戸惑うことなく会話をすることができている。会話をしている中で私が思うことは、日本で何をするんだろうか、日本語上手だな、というようなことである。外国人と会話をしてその人の国や地域の情報を知り、自分でもその国や地域について調べてみよう、と思うことが多々ある。そんな中で目にしたり、聞いたりする情報は全て日本は素晴らしいなどというようなものだけではなかった。彼らが日本で生活、旅行をする上で悪いなと感じる、感じたことが多々ある。
例えば日本で働きたいと思っている外国人が感じたこと。生活のためにはアルバイトなどをしてお金を稼ぐ必要がある。しかし、外国人だからという理由でアルバイトができなかったという。日本人が多いから日本語で会話ができる日本人を雇っている、というような言葉をかけられ生活に必要なアルバイトをすることができずにいる人もいる。その人には日本で働きたいという事情があるにも関わらず、何ひとつとして理由を聞かずに断られてしまい、なぜ外国人は日本で働けないんだと感じたという。他にも、災害時に備えた避難訓練。日本は災害大国のため、多くの避難訓練を実施している。しかしこれらはほとんどが全て日本語のみで行われている。災害に不慣れな外国人にとって避難訓練はとても大事なものである。いざという時に備えた避難訓練でも、日本人向けに行われている。日本語が不慣れな外国人は日本語を理解する事すら難しい。実際に災害時の避難所のニュースなどを見ても、外国人が避難所に避難している様子というのをほとんど見たことが無い。そのため、訓練が行われてもどう行動するべきかが分からず、実際に災害が起こった際はさらにパニックとなり避難が遅れ、最悪の場合、命を落としてしまうことに繋がりかねない。今流れているニュースや情報だけを見るだけでは一見すると外国人は日本での旅行や生活を楽しんでいるように見える。しかし、全ての外国人が快い旅行、生活をしているとは限らないのが事実である。
そこで私はこの外国人だからという問題を解決するために、外国人向けに常に情報発信ができるモノや場所をつくることが必要だと考えた。日本語を言語としていない外国人は自分の国の言葉で情報を得るためには限りがある。そのため、気軽に訪れることができ、誰でも最新の情報を自分の国の言葉で知ることが日本で生活、旅行をする上で外国人が求めるのではないかと考えた。場所だけでなく、外国人にも対して専用のラジオなどを配布することで自分の国の言葉で情報を聞くことが出来る。これを実現できれば、外国人でも日本で働ける、住める場所を見つけることができたり、言葉に対する壁を考えることがなくなったりすることや、災害時に避難のアナウンスが分からずに避難することができず命を落としてしまう、ということを防ぐことができる。
言葉に問題があることや外国人だからという理由だけで日本で快い生活や旅行ができないという人が1人でも減ることで今以上に日本が世界で一番と言われる国になり、さらに旅行者、移住者が増えるに違いない。つまりは、旅行者だけでなく日本に住んでいる外国人にも言葉や国だけで壁ができてしまわず、誰もが快く過ごせる空間づくりがこの先の未来、今の私たち、日本に必要不可欠になっていく。
・野田 怜弥 横浜市立大学4年 友達のともだちは友達
私は今年で大学を卒業する。この6年間を振り返ってみると、周りの誰かに助けられる24年間だったと改めて思っている。家族はもちろん、学校・大学の先生や友達、知人が何かのタイミングがある度に手を差し伸べてくれたからここまで生きてきたし、人生を楽しんでいるのだと思う。
生まれた瞬間は母親のお腹の中にいすぎて、誕生した時には無呼吸で肌も黒ずんでいた。お医者さんがお尻を叩いたことでやっとこの世に生を受けることができたのだと聞かされた。父親の仕事のために転勤族で、幼稚園から中学校まで2つずつ行った。人見知りが強かったが、先生と友達に恵まれて問題なく過ごせ、むしろ新しい友達に出会えることを楽しんでさえいた。しかし2つ目の中学校は1つ目の学校との風土の違い(一方は進学校、もう一方は若干荒れ?気味)に慣れず、学校に行きたくなかった時期もあったが、「帰ってきたらジグソーパズル進めようね」という母親の言葉に背中を押され毎日通えるようになった。高校のときに、父が仕事を辞めて両親でフランチャイズのコンビニ経営を始めた。なかなかうまくいかず、家計も苦しく家にほとんど帰ってこない日々が続いた。そのため私が家の手伝いをするようになり、部活に行きづらくなり、「部活最優先」とされていた部には所属できなくなった。ストレスで食に走り、過食になったが、親と先生たちの気遣いで元の食生活に戻ることができた。大学受験期は、理数科の中で文転するというハードな選択をした私を、文系の先生方が休み時間や放課後に補講したり教材をくれたりすることでサポートしてくれた。両親の知り合いが家庭教師をしたり差し入れをくれたり、塾講をするお客さんが塾を無料で開放してくれたり、いろんな人が応援してくれたおかげで希望していた今の大学に合格することができた。
ここまでもたくさんの人にお世話になったが、大学ではそれまで以上だった。アルバイト先では、仕送り無しの生活をしながら留学に行くための資金も貯めようとする私の為に、扶養を超えた分を別の形で支給してくれた。複数のところで働いたが、どこも、資格が必要にも関わらず勉強の為にと福祉の現場に入って働かせてくれたり、ご飯に連れて行ってくれたり、食材や料理をお裾分けしてくれたりして応援してくれた。外国に長期滞在した際も、現地の人やそこに住む日本人が家に泊めさせてくれたり、ご飯を作ってくれたり、車で送ってくれたりした。卒業論文を書くために調査をした際も、インタビューをすべき人を紹介してくれたり、アンケートを代わりにやってくれたり時間を惜しんで手伝ってくれた。大学生活の中で出会った人々も、食事に誘って、応援したり指導したりしてくれる。友人は、もちろん楽しみを共有してくれもするが、面白いコトすごいコトをやって私に刺激をくれ、学び合いもする。
私は特に何かに秀でているわけでもないし、経済的に恵まれているわけでもない。いわゆる「普通の人」だが、人に恵まれているなと心から思う。これから社会に出てからは得た恩を返していきたいと思っている。と同時に、周囲にいるすべての人々を友人として家族として、仲間として、日々当たり前に手を差し伸べる人生を歩んでいきたい。人は「得たら返したくなる」習性があると信じている。この輪を生み、広げがっていくような影響を自然に与えられる人になりたい。
・市川 野乃夏 宮城県名取高等学校 3年 夢に向かって進むために
私は今、社会で夢のない学生が乗り残されていると感じる。私にも夢がなかった。将来の夢ややりたいことがなく、目の前にある小さな目標や楽しみのために生きていた。しかし、高校という場所から社会にでるにあたってどのような場所へ行くかを決める時がついに私にもきてしまった。学びたいもの、目指しているものがあったら進学したり就職するだろう。しかし私には目標などなく、ただじっと不安を感じていた。
夢や目標など簡単に作れるものでは無い。高校生で夢がない人は山ほどいる。しかしなくても作らなくてはいけないのが今の世の中である。働くことが国民の義務であるからだ。働かないと周りから白い目で見られてしまう。「普通では無い」と。だからといって適当にしてしまうと後々後悔や失敗してしまうかもしれない。私は失敗することが怖かった。
夢のない学生が取り残されていると感じる理由は2つある。
1つ目は世間の意見である。ある程度の年齢になっても働かない人は社会でニートと呼ばれ変わり者扱いされる。そして大人は子供には夢があることが普通だと考えていると感じる。しかし高校生で夢がある人はほんの僅かであることが現状だ。たった17年や18年しか生きていないのに将来なりたいと思える職業に出会うことは難しい。それなのに高校では定期的に将来選択のアンケートが行われる。確かに将来について積極的に考えることは大切だ。しかし焦らずもう少し時間をとっていくべきで、労働の義務を少し緩めるべきであると感じる。
2つ目は夢の選択について個人に任せすぎであることだ。例えば、夢がない人は無理してでも自分で見つけようとする。そのために知人から話を聞いたり、インターネットで調べる。しかしそれは自分の興味ある職業、知っている職業について深く知るだけになり、まだ知らない職業を知るきっかけにならないと感じる。それは学校や家庭での職業についての教育が行き渡っていないからだ。職業体験があったとしても1度だけがほとんどで、多くの職業を体験することはできない。私は小学校から高校までで職業体験を多く実施し、様々な職業を深く学べる授業を取り入れるべきであると思う。様々な職業について学ぶことは将来の夢についての選択肢を増やせるだけでなく、働いている人への思いやる気持ちが生まれると思う。将来の夢がないということは何も悪いことではない。乗り残されるべきでは無いと考える。夢がなく何をやるべきかわからない人こそ様々なことに積極的に挑戦し、知識や体験を増やしていくべきだ。そのためには学校や地域や体験出来る場面も増やすことが必要である。私は将来子供が出来た時将来の夢の選択を増やせるよう様々な体験をさせてあげたいと感じた。
・長船 未玲亜 関西創価高等学校 高校3年生 多様性の本当の意味
近年「多様性」を多くの人が受け入れ、理解が深まってきている。これは大変喜ばしく、私達が望んでいたことである。そして「多様性」に理解があるということが当たり前になってきている。まるで「受け入れられない人は最低」と差別するかのように。
少し前に話題になったディ◎ニー作品であるリ◎ル・マーメイドの実写化映画がある。
主人公は黒人の血を引く若手シンガーが選ばれ、「原作とイメージが違いすぎて受け入れられない」「世界観があっていない」など批判が殺到した。そして、主人公の姉役達も黒人に限らず色々な人をキャスティングしたあまり、「血の繋がりが感じられない」とまたもや炎上した。しかし私は物語は特に変更されていないし、イメージは違えど、役者達の実力には圧倒されたし、黒人の方々にとって喜ばしい作品になったならそれでいいのでは?と感じたが問題は次だ。
2024年に公開される名作アニメである白◎姫の実写化での主人公はラテン系アメリカ人が選ばれ、さらに七人の小人達はそれぞれ性別や身長、体型が異なる「魔法の生きもの」として登場。物語も時代に沿って変更が加えられるそう。「名作の作品を全く違うものに変更されがっかりした」と批判が絶えない。私も「そこまでするか?」と疑問に思った。
確かに誰でもプリンセスになれるというコンセプトはいいと思うが、別に黒人が主人公であるディ◎ニー作品がないわけではない。それぞれ輝ける場所があるというのに、なぜわざわざ元々の物語を変更する必要があるのか。多様性を意識するがあまりに黒人が選ばれる可能性が高く白人が選ばれにくくある。これも立派な差別なのではないだろうか?
このように、みんなそれぞれ違う考え方があり、価値観も違う。そんな中、当然「受け入れられない人」も出てくるであろう。だが、そこで「理解できないなんて非常識」「ありえない」と批判するのは差別に値するのではないかと私は思う。SDGsの基本精神は「誰一人取り残さない」であり、「理解しない者は理解するまで受け入れないといけない」ではない。「受け入れられない人」の考え方も理解することによって初めて「多様性」というものが存在すると私は思う。
・牧野 寛太 創価大学3年 多様性を認めること 自分って普通って思っていますか?
普通って意外と難しいですよね。何を持って普通とするのか、線引きをどうするのか。なぜ難しいのか。それは明確に線引きをしようとするからではないのでしょうか。昨今、大人の発達障害が注目を浴びています。社会人になって、大人になっても忘れ物をしてしまう、うまくコミュニケーションをとることができないなどで、悩んでいた方々が「発達障害」だったんだと「認められました」。一般的には、IQが70以下の場合、知的障害であると分類をされるそうです。またIQ70ではないが、平均値より低いIQ85から70程度の場合は、「境界知能」に「分類」されるそうです。発達障害や知的障害に関して社会の理解が広まることは素晴らしいことであり、生きづらさを感じている人にとって救いの手だと思います。そのうえで、本当に「分類をする」こと、「名前をつける」ことが、多様性を受け入れているってことでしょうか? 僕の小学校と中学校には発達障害、詳しくは聞いたことがないのですが、多分ダウン症の同級生がいました。他にも、今振り返ってみると吃音の症状を持った同級生もいました。当時の僕は、ダウン症などの発達障害や吃音というものを知りませんでした。なので、僕にとって彼らは個性を持った人やちょっと話すのが得意じゃない人という認識でしかなく、できないことが人と違うだけと捉えていました。よく考えてください。僕たちだって、多くの人の前や尊敬している人の前で話すと緊張してうまく話せないことってありますよね。吃音の人はそれが少し多いだけです。もちろん、「名前」をつけて、こんな症状やこんなことが不得意とかの理解を深めていくことは大事です。「吃音」だからや「発達障害」だからなどの「名前」ではなく、この子は、これが人よりもちょっと不得意なんだとかでみてあげることが大事なんだと思います。つまり、発達障害などの「名前」ではなく、人間一人一人の得意なこと、不得意なことに向き合うことが大事ではないでしょうか。僕は運動することや細かい作業をすることが得意ではありません、なので、スポーツをするときや細かな作業が求められる時は、友人の手を借ります。お互いに不得意なことを認め合って支えあうということが本当に誰も置き去りにしない、多様性を認める社会ではないでしょうか?
・市野澤 玲衣 湘南医療大学 公衆衛生看護学専攻 保護者の孤立にどう立ち向かうか
現代の日本社会では、高度経済成長期以降の核家族化や地縁関係の希薄化などにより、母親が一貫した長期の子育て支援を受けづらい環境や、対人関係の変化や孤立感、閉塞感を伴う環境の中で子育てが行われている。そのため、孤立している子育て世代が多くいると推測されている。
私には子育てをしている友人がいる。その友人は、子どもが産まれてから1歳8ヶ月で保育園に通うまでの間、家で子どもと2人きりの生活が続き、気が滅入っていたそうだ。また、友人は子育てをする中で、赤ちゃんが何を欲しているかわからないことや子どもの発育に関する不安、保護者自身の時間をとることができないことなど、子育てに関する様々な悩みを抱えたまま、孤独な子育てをしていた。そのような友人に対し手を差し伸べたのは、行政保健師だった。その方が地域の子育てに関するコミュニティを紹介し、これに友人が実際に参加したことで、友人は子育てにおける悩みを感じているのは自分だけではないことや、子どもの発育スピードはそれぞれ異なることを知ることができ、気持ちが楽になったという。これは、子どもと一対一で子育てをする中で抱えていた孤立感やストレスが軽減されたことが大きな理由だ。このように、地域の子育てに関するコミュニティでは、子育てについての情報収集や子育て世代の悩み・不安やその対処法の共有をすることで、安心して子育てすることにつながると考えられる。また、家に篭っているだけでは、ストレスも増大するため、地域のコミュニティに参加するなどの外に出る機会を設けることで、保護者自身のリフレッシュになることも期待できる。また、保護者自身の時間をとることができないという悩みについては、保育園・祖父母・保健師・家事代行サービス・地域の施設といった周囲の理解や支援を得ることにより、保護者が自らに充てる時間ができ、気持ちに余裕を持つことができるようになった。
友人は、子育ては一人では肉体的にも精神的にも負担が大きいものであり、理解者の存在が必要であることを教えてくれた。少子化が社会問題となっている近年では、減りつつある保護者を誰一人取り残さず、地域や社会全体が理解者となっていくような、子育てのしやすい社会を作ることが必要である。
社会から取り残された保護者は、子育てにおける増大したストレスを抱え込み、最悪の場合、児童虐待を引き起こす可能性が考えられる。厚生労働省の統計データによると 2021年の児童虐待の相談件数は207,660件となっており、近年急速に増加が続いている。そのため厚生労働省では、児童虐待の防止に向けた取組を進めている。児童虐待の防止は社会全体で取り組むべき課題となっており、そのためにも子育て中の保護者を孤立させないことが大事になる。
子育てをしている保護者を社会から孤立させないことが求められる中で重要になるのが、行政保健師の果たす役割である。行政保健師は、保護者への訪問や乳幼児健康診査を通じて、保護者に実際に接触する機会がある。そこで保護者が実際に抱えている悩み・不安を把握し、必要な支援を行っていくことで、保護者が孤立せずに安心して子育てをする環境を作ることができる。また、行政保健師は、保護者に地域の子育てに関するコミュニティについての情報提供を行うとともに、そのコミュニティの場では単なる参加している保護者と保健師との間のやり取りに終始せず、保護者間のコミュニケーションを促進させることで地域のコミュニティの活性化を図るという役割も果たしている。そして、行政保健師は保護者の身近な相談相手として、日頃より保護者と顔の見える関係を構築することで、いざというときに頼れる身近な存在となる。これにより、保護者が安心して子育てをすることができるという心理的な支援ができるとともに、実際に何か問題が生じた場合にも早期に対応でき、子どもや保護者への負担を最小限にとどめることができる。
このように、行政保健師は子育てをする保護者を孤立させないために様々な役割を果たしている。これらを通じて、身近な理解者として子育てをする保護者に寄り添い、支援をすることで、子育てのしやすい社会の実現に向けた重要な立場を担っている。
子育てにおいてはストレス・不安感がある程度生じることは避けられないかもしれない。だが、保護者の周囲の理解を促進することを含め、適切に対処をすることでそれは最小限にとどめることができる。これによって子育てストレス・不安感を原因とする児童虐待などを防ぐことにもつながり、保護者が取り残されず、より子育てしやすい社会につながるだろう。私は、行政保健師として、自らが保護者の大きな理解者となるとともに、地域社会全体が子育てをする保護者の理解者として、子育てを支援していくような環境を作るために活動していきたい。
・桐生 莉緒 早稲田大学4年 取り残されないようにし合う
貧困ではない、特に障害もない、右利き、性自認も身体も女性、日本人の両親から生まれた日本語を話す日本人。それが私だ。
私は長年、自分のことを取り残されないマジョリティだと認識してきた。ところが、その認識がここ数年で揺らいでいる。例えば、帰国子女の友達から、現地の学校でアジア人として差別された体験を聞いたとき。就活の集団面接で女子学生が私だけだったり、「結婚しても仕事は続けますか?」と質問されたりしたとき。
私はこの国全体の中で、多くの点でマジョリティである。しかし、もし白人ばかりの社会に行けば、私もアジア人というマイノリティになるだろう。大企業の総合職を目指して行なっていた就活の中では、圧倒的にマイノリティだった。マジョリティやマイノリティという区分は、場合によって変わるものだと気づいた。
この気づきは、「誰ひとり取り残さない」という言葉を初めて目にしたときに感じた違和感の正体でもある。「誰ひとり取り残さない」という言い方は、絶対的なマジョリティの視点に立った発言のようだ。そして、注目されるのは、分かりやすい弱者やマイノリティのカテゴリーになる。「誰ひとり取り残されないようにする」の方が、誰もがマジョリティにもマイノリティにもなるという現実に即しているように思う。
では、「誰ひとり取り残されないようにする」ためには何が必要なのだろう。私がすぐに思いついたのは、自分とは違う立場を想像することだ。
現在、セルフレジやセルフオーダーシステムが広まっている。デジタルネイティブ世代で列に並ぶのが面倒な私には、とてもありがたいことだ。友達の間でも肯定的な意見が多い。働き手不足に対応できるため持続可能なシステムであり、店側も人件費を削減できる。
しかし、機械の操作に不慣れな高齢者や、タッチパネルに何が書いてあるか読み取れない(読み取りにくい)視覚障害者にとってはどうだろう。他の人が自分で会計や注文をしている中でわざわざ店員を呼ぶ必要があり、肩身が狭く感じたり、不便に感じたりするのではないか。セルフレジ専用の無人店舗ではこういった人々は買い物ができず、取り残されたように感じるかもしれない。
このように、メリットづくしに見えることにも、デメリットは必ずある。自分やその属性にとってデメリットを感じた場合に、取り残されないように声を上げることも大切だと思う。だが、さらに視野を広げてみてはどうだろう。多数決や世論では埋もれがちなデメリットも想像力や傾聴力で発掘し、それも補えるように多様な選択肢を作っていく。セルフレジやセルフオーダーシステムの例で言うならば、店員から積極的に「お困りですか?」と客に声掛けをする、一定数有人レジを配置するなどの選択肢が考えられる。多くの人がこれを実践すれば、取り残される人は格段に減るはずだ。
想像力は重要だが、将来低下していくと考えている。インターネットには、その人の関心があるものを表示する仕組みがよく見られる。この商品を購入した人が購入している別の商品、おすすめの動画やアカウントなど、枚挙にいとまがない。自分の興味があるものを効率よく見つけられる一方、新聞などの媒体と比べて、視野が自分の周辺に限られてしまうだろう。
取り残されないように意見を述べることや、自分とは違う立場に立って想像する癖を身につけて互いに「取り残されないようにし合う」ことが、「誰ひとり取り残されない」社会に繋がると思う。
・音田 将吾 フリーター 働きかけ
私は新卒で入った会社で入社2ヶ月後うつ病を患い、早期退職した。その原因は、会社の雰囲気に馴染めなかったことや居場所がなかったためである。過度な明るさを強要されたり、業務上の悩みを複数人の先輩に相談してもまともに話も聞いてもらえず、1人で悩んでしまった結果、体調を崩した。自分の意見を言うことも出来なかったために自分という存在が認められず、必要とされていないと感じてしまった。会社に愛着を持つことが出来ず、先輩と安定した関係を作ることが出来なかったために、安心感や落ち着きというものはなかった。そのため、体調を崩して休職した。休職中、このような会社に復職するのは難しいと考え、早期退職することに決めた。
残念なことであるが、会社に馴染めない人はどの会社にもいるのではないか。私のような新卒だけではなく、障害の有無や国籍、性別など、理由は様々ではあるが、孤立してしまっている人は必ずいるのではないかと思う。
現職でも、「男らしさ、女らしさ」などと度々先輩から言われたり、「あの人ゲイらしいよ」などと発言する人もおり、マイノリティを認めない雰囲気が漂っている。また、アルバイトや派遣社員という非正規雇用に対する偏見もある。試験勉強に励んでいる人々に対する冷たい目線など、まだまだ問題は存在する。
各々の違いは個性である。違いを持った人はどの社会にも存在する。違いを持った人を差別するのではなく、認め合うことが求められている。個性というのは外見で判断できるものだけでなく、内面的なものもあり、なかなか周りの人は気づくことが出来ない。そこで、対話し寄り添うという姿勢が大切になる。
私自身、病気で悩んでいた時に、話を聞いてくれる人のありがたさというものを肌で感じた。早期退職や転職の背中を押してくれたのは家族であった。私はうつ病と診断された時、涙ながらに両親に電話をした。私自身が引け目、恥ずかしさを感じていたため、抑うつ状態になり、閉じこもってしまっていた。そんな時、両親は静かに話を聞いてくれ、寄り添ってくれた。そして電話の最後に公務員の父親から「公務員合ってると思うよ」という言葉をかけてくれた。その言葉がきっかけで、私は現在、来年の公務員試験に向けて勉強を進めている。
これからの社会を変えるのは私たち若者である。私たちはこれからの新社会人が馴染むことができ、自分の意見を発信出来るような職場を作り、自分を見失わずありのままの自分でいられるような社会を作っていかなければならない。自分のやりたいことや強み、得意分野を生かした仕事ができることで自分が自分であることを実感し、ゆるがない自分を持つことができる社会を作っていきたい。一人一人の姿勢・言動が社会を変えると信じている。必ず来年公務員になり、自分のこれまでの経験を活かして、皆が働きやすく、生活しやすい、多様性を認める社会を作りたいと考えている。
・佐藤 知咲 名取高等学校3年 在留外国人を取り残さないために
SDGsの目標の一つに「人と国の不平等をなくそう」というものがある。この目標を達成するためにはまず最初に日本で起きている不平等を知る必要がある。
日本には多くの外国人がいる。観光を目的に短期間日本を訪れに来る人もいれば、仕事をするために長期間滞在する人もいる。もちろん日本を居住地として生活している人もいるだろう。このように日本にいる外国人は実際に日本で過ごす上で日本人とどのような差異があるのか、何に困りどのような支援を必要にしているのだろうか。
私が今までに在留外国人が日本に滞在する上での問題を感じた事例を二つ挙げる。一つ目は1995年に起きた阪神・淡路大震災だ。阪神・淡路大震災は多くの犠牲と多くの被害を出した。その中でも高齢者、低所得者、外国人などが多く犠牲になったと報告されている。更に外国人の死亡率は日本人の死亡率と比較して高かったことも報告されている。大きな災害が発生し、テレビやラジオ、スマホなどで災害に関する情報や避難情報がいくら発信されていても日本語の理解が不十分である外国人はその情報を受け取ることができなかったり理解するのに時間がかかったりする。そのため、非常事態にどのような行動を取るべきなのか分からないため避難に遅れる。また、避難所では外国人を受け入れてはくれないと考えたために多くの危険が残る自宅に戻った人々もいたという。二つ目は外国人技能実習生についてだ。そもそも技能実習制度とは外国人の技能実習生が日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得などを図るものを指す。そんな日本の外国人技能実習生には長時間労働や賃金の未払い、雇用者からのパワハラなどの問題が取り巻いている。一部の人たちの間では外国人技能実習生に対して安い労働力という間違った認識をしていたり日本語が上手く通じないことでの暴言や暴力、度を越した指導を行ったりする人もいる。この二つを通して在留外国人は言語面での問題があるゆえに日本人との格差が生じていると考えた。
私はこの問題の解決作として二つのことを提案する。一つ目は「やさしい日本語」を普段の教育から導入していくことだ。そもそもやさしい日本語とは1995年の阪神・淡路大震災後に災害時の外国人に対する情報提供の手段として簡略化した日本語を使うための研究が行われて作成されたものである。実際、阪神・淡路大震災を通して外国人の言語問題が明らかになりやさしい日本語というものが作成されたもののやさしい日本語は多くの人に知られていないように感じる。そのため、私はやさしい日本語の普及率や知名度を上げていくべきだと考える。英語と同様に外国人と関わる手段の一つとして教育に導入していけば広く認知されるのではないだろうか。二つ目は外国人技能実習生の問題の対策として同僚や上司との日本語交流の促進をすることだ。一つ目で言及したやさしい日本語を災害時のみならず日常でも用いて同僚や上司と日頃から関係を築くことで長時間労働やパワハラなどが未然に防がれると私は考える。確かに、電子機器が発展している現在、わざわざ日本語を用いて外国人に対してコミュニケーションやサポートをする必要は無いと考える人もいるだろう。スマホを使えば簡単に言語が違う人と対話を図る事ができる。また、日本語よりも世界共通語である英語を用いた方が手っ取り早いと考える人もいるだろう。しかし、災害時などの緊急事態の場合は日本語でのコミュニケーションが必要になってくる。必ずしも在留外国人の周りに言語サポーターやその外国人の母語を話せる人がいるとは限らない。そのため、外国人と日本人の双方が日本語でコミュニケーションを取れるということが必要不可欠だと私は考える。
国籍が違うために日本で不当な扱いを受けたり命の重さが異なったりすることはSDGs達成に反する。持続可能な社会を目指すためにも日本人と在留外国人とが平等に暮らしていくためにも私達は国籍関係なく助け合っていくべきだ。
・山口 颯太 一橋大学 みんなが取り残された世界
「昨日のテレビ見た?」
中学生の頃まではそんな会話を朝教室に入った途端に投げかけてくる友達がいた。今考えれば本当に他愛もない会話であったのだが、私はその会話の中にあった温かみがどこか心地よかった。二人で話していたはずの会話は自然と周りを巻き込んで盛り上がり、先生にそろそろホームルームが始まるからと注意を受けることもしばしばあった。だが、静まり返った水面で一つの波紋が優しく周りを巻き込みながら広がっていくように、徐々にみんなが会話に参加していって温かみの輪が広がっていくことにものすごく魅力を感じていた。
しかし、高校に入学をするとそういった話題を大人数で話すことがなくなった。自分を含め多くの人がスマートフォンを持ち始めた影響であろう。スマートフォンにはいくつものエンタメプラットフォームがあり、その中には無限のエンタメが用意されているため、各々が自分の興味関心にあったものを選択する。その他にもSNSを利用して自分の気持ちをすぐに顔の見えない他者に伝え、共有することができる。そのために小さなコミュニティの中で会話が発生して、知らぬ間に話題が消化されている。そんな今を目の前にして「昔は一つの話題を大人数で共有していたのに」と、私は周りの人間とどこか近づききれない溝を感じて一人取り残されたように感じた。これは私が自覚しているだけで、他にも潜在的に孤独感というのを感じている人がいるのではないだろうか。すなわち正確に言えばみんなが同様に取り残されているということになる。やはり生の会話と比べるとどうしてもテキスト頼りのやり取りになる以上冷たさが拭えない。
現代では様々な場所で多様性が謳われているが、その一方で人間同士の繋がりというのが希薄になったように思えて、寂しさを感じてしまう。今一度どこかにいる誰かと顔を見ないで会話をするのではなく、目の前にいる大切な人の顔をしっかり見て会話の楽しんでほしい。私は今日もスマートフォンをバッグに入れ、顔を上げながら歩く。もしかしたら私の人生を大きく変えるかもしれない出会いを求めて。
・三嶋 千尋 宮城県名取高校 3年 高齢者とICT
私は、今まで全くSDGsに興味を持ったことがありません。なので、今回この文を書くために、まずSDGsについて調べてみました。SDGsとは、「Sustainable Development Goals」の略称で、「持続可能な開発目標」と日本語に直訳するとなります。さらに、17の達成目標と169のターゲットを掲げて、2030年までに達成する事を目標としています。また、貧困や飢餓、健康や教育、ジェンダーやエネルギー、気候変動や環境などといった私たちが直面する地球規模の課題に取り組むための目標だそうです。これらをふまえて、私は、「産業と技術革新の基盤をつくろう」という項目に興味が湧きました。そして、様々な機械化が進む中で、高齢者の人でも援助なく使えるような機械とはどのような物なのかを、「誰も取り残されない」ということに結びつけて考えてみたいと思ったので、この項目を選びました。
まず高齢者の社会的参加とICTの関係についてです。高齢者はICTから疎遠しがちかつ孤独になりやすいので、ビデオ通話を利用することで孤独感を少しでも軽減でき、コミュニケーションを活発に行うことが出来ます。また、インターネットを通じた他者とのコミュニケーションは簡単に行うことが可能なので、生活品質の向上にも繋がります。スマートホームスピーカーを用いれば、声での操作が可能なので、高齢者の生活を、便利でより充実した物に出来ます。
私の学校では、総合的な探求の時間というものがあります。その時間の中で、私は「どうしたら将来的な少子高齢化に向け、未来の高齢者でも使いやすいICTシステムを作れるか」というものをテーマにし、研究をしました。スマートフォンのような持ち運びに便利かつプライバシーやセキュリティに特化していて、高齢者でも使いやすくて、見やすいデザインが最も適したデザインなのではないかという結論に至りました。スマートフォンのような持ち運びに便利な物だと、重い物が持ち運びにくくなる高齢者にとってはとても最適なデバイスなのではないかと思いました。また、見やすいデザインとは、例えばスマートフォンのホーム画面やアプリのアイコンが、無駄が無いデザインかつ一目で何のアプリか分かる見やすいデザイン、簡単に言えばシンプルで分かりやすいデザインが1番最適なデザインだと考えます。
高齢者向けのICTの普及は、地域社会への参加の活発化や地域コミュニティの活発化が見込めます。オンラインを通して情報を知ることが出来るため、より早く情報が入ってきます。なので、地域社会への参加がより活発的になります。また、地域コミュニティは、セキュリティに特化した専用のアプリを通じることで、安心かつ簡単に、手軽にコミュニケーションを取ることが出来るのではないかと思います。以上のことから、高齢者向けICTの普及は、地域社会の発展に繋がります。また、高齢者向けICTは産業と技術に与える影響は重要です。高齢者向けICTが進むことにより、高齢者向けのコミュニケーションアプリや、自分の健康管理が手書きよりも楽に記録出来るアプリの開発が活発化されると考えます。
このようなICTを高齢者が難なく利用するのは中々難しいです。やはり、複雑なデザインのものは高齢者にとっては理解しにくく、セキュリティへの不安も伴います。これらを解決するため、先程も述べたように高齢者でも理解がしやすいシンプルなデザインである事が最も重要だと思います。一対一で指導をして、よりICTへの理解を深める機会を設けるのも良いと思います。また、セキュリティ面に関しては、偽メールや詐欺に対する通知を設けたり、セキュリティに関する学びの場を設ければ安心してICTに触れることが出来るようになると考えます。
ICTの技術が進歩し、高齢者でも安心して日常生活にICTを取り入れられるようになれば、オンラインでのコミュニケーションや、社会への参加を積極的に行えるようになります。そして、高齢者向けのアプリケーションの開発や、セキュリティに特化していてデザインがシンプルで見やすく使いやすいスマートフォンのようなデザインの物を取り入れれば、高齢者だったとしても、機械化が積極的に進む世の中からも「取り残されず」に生活出来るのではないでしょうか?





